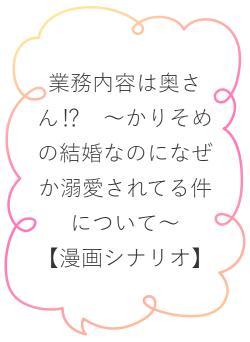紫苑は、華狐なら誰でもいいんじゃないのだろうか……。
自分以外の誰かが華狐に選ばれたとしても、紫苑はきっとその人のそばを心地よく感じるような気がして気分が暗くなった。そんなこと、たらればの話しでしかないのに。
「そうですよ。でなければ、芹香さまはきっと今頃村にお帰りになっていたことでしょう」
実のところ、そうならずに済んでよかったと一番安堵しているのは他ならぬ自分ではないだろうか、と芹香は思う。
あのまま紫苑が姿を見せなければ、きっと自分は用済みだと九宝嶽を下りて村に帰っていただろう。
だけどどうだろうか。
あの村に、自分の居場所などない。両親が生きていた頃は幸せで、芹香の周りはとても明るかったが、両親の死を境に全てが一転してしまい、いい思い出など一つもなかった。叔父夫婦が本家の当主に成り代わり、村の人たちも叔父夫婦の顔色を伺って芹香には冷たい視線と態度をとるようになってしまったから。
あの村での辛い出来事を思い出し、もしまた帰ることになっていたら自分はどうなっていたのかと考えただけで身体が震えた。
すると、いつの間にか目を覚ました紫苑が正座する芹香の肩に顎を乗せてきた。ふわふわな毛が、首や頬をくすぐる。その紫苑の狐姿の向こうで葉奈が一礼してどこかに去っていくのを視界に捉えつつ、そのこそばゆさに抗えずに首をすくめた。
「なにか、辛いことでもあったのか」
「し、おん?」
「芹香の霊力が不安定だ」
そんなことまでわかるのか、と芹香は内心で驚くも、肩に乗った紫苑の首にそっと腕をまわした。
「ちょっと、昔のことを思い出してしまっただけ」
モフモフを堪能していると、逆立った心があっという間に凪いで行く。
「抱きしめても、いいだろうか」
「え? ……えぇえっ⁉」
一瞬にして触れていたモフモフは、上質な絹の羽織へと代わり、自分が腕に紫苑を抱いていたはずなのにいつの間にか紫苑の腕の中にすっぽりと包み込まれていた。
いいなんて一言も言っていないのに。
突然の出来事に、芹香の胸が騒ぎ始める。
今自分を抱きしめているのは、紫苑だけど芹香の知る狐の紫苑じゃない。
そのことが、芹香を落ち着かない気持ちにさせるのだ。
「し、紫苑……」
自分以外の誰かが華狐に選ばれたとしても、紫苑はきっとその人のそばを心地よく感じるような気がして気分が暗くなった。そんなこと、たらればの話しでしかないのに。
「そうですよ。でなければ、芹香さまはきっと今頃村にお帰りになっていたことでしょう」
実のところ、そうならずに済んでよかったと一番安堵しているのは他ならぬ自分ではないだろうか、と芹香は思う。
あのまま紫苑が姿を見せなければ、きっと自分は用済みだと九宝嶽を下りて村に帰っていただろう。
だけどどうだろうか。
あの村に、自分の居場所などない。両親が生きていた頃は幸せで、芹香の周りはとても明るかったが、両親の死を境に全てが一転してしまい、いい思い出など一つもなかった。叔父夫婦が本家の当主に成り代わり、村の人たちも叔父夫婦の顔色を伺って芹香には冷たい視線と態度をとるようになってしまったから。
あの村での辛い出来事を思い出し、もしまた帰ることになっていたら自分はどうなっていたのかと考えただけで身体が震えた。
すると、いつの間にか目を覚ました紫苑が正座する芹香の肩に顎を乗せてきた。ふわふわな毛が、首や頬をくすぐる。その紫苑の狐姿の向こうで葉奈が一礼してどこかに去っていくのを視界に捉えつつ、そのこそばゆさに抗えずに首をすくめた。
「なにか、辛いことでもあったのか」
「し、おん?」
「芹香の霊力が不安定だ」
そんなことまでわかるのか、と芹香は内心で驚くも、肩に乗った紫苑の首にそっと腕をまわした。
「ちょっと、昔のことを思い出してしまっただけ」
モフモフを堪能していると、逆立った心があっという間に凪いで行く。
「抱きしめても、いいだろうか」
「え? ……えぇえっ⁉」
一瞬にして触れていたモフモフは、上質な絹の羽織へと代わり、自分が腕に紫苑を抱いていたはずなのにいつの間にか紫苑の腕の中にすっぽりと包み込まれていた。
いいなんて一言も言っていないのに。
突然の出来事に、芹香の胸が騒ぎ始める。
今自分を抱きしめているのは、紫苑だけど芹香の知る狐の紫苑じゃない。
そのことが、芹香を落ち着かない気持ちにさせるのだ。
「し、紫苑……」