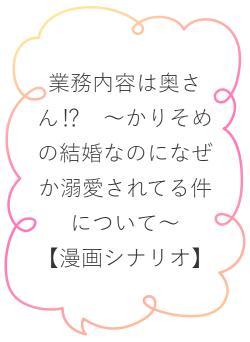「だけど、芹香のそばで過ごす日々は心地よくて、離れがたくなってしまった」
それは自分も同じだと、芹香は胸の裡でつぶやく。
「かと言って、どう切り出せばいいのかわからなくなって……、今更本当のことを言ったら芹香が呆れて帰ってしまうのではと、情けなくも今の今まで言い出せずにいたんだ」
紫苑の視線が、芹香に向けられる。
なにもかもを見通すような琥珀色をした瞳に見つめられて、芹香の胸は高鳴った。これまで毎日のように見てきた紫苑の瞳なのに、こんなに苦し気に揺れる瞳は知らない。
まるで、紫苑が自分にいなくなってほしくないと、そばにいて欲しいと言っているように聞こえて、芹香は着物の衿合わせに指先をひっかけるようにして胸元を握りしめた。
もう片方の手に、紫苑の手がそっと触れる。線は細いが大きな手は男性のそれで、芹香の身体がびくりと跳ねた。
紫苑は芹香の反応に一瞬身を固くしたが、そのまま芹香の手を取りまっすぐ見つめる。
中庭では、木々に止まった鳥たちのさえずりが響いて時折風が葉を揺らす音がするくらいで他に音はない。この場所で、狐の紫苑と過ごす穏やかな時間は芹香の大好きなひと時でもあった。それらの時間がつぎつぎと浮かんできて、触れる紫苑を拒めないでいた。
「どうか、俺のそばにいてほしい」
愛の告白のようにも取れる懇願に、体温が上がっていき顔が火照った。
しかし、
「霊狐の華狐として……、正式に俺と番になってほしい」
──霊狐の華狐として。
その言葉を聞いた瞬間、昇り詰めていた熱が瞬時に冷めていく。
紫苑は霊狐として華狐の力が必要だと言っているのだと、芹香は冷静に受け止める。
お前なんかいらないと言われなくてよかったと安堵しているのに、心の底に流れる冷たい空気はなんだろう。
考えてもわからない芹香は、見て見ぬふりをして蓋をした。
どうせ村に帰ったところで、自分を待ってくれている人も歓迎してくれる人もいないのだから、自分を必要としてくれる紫苑のそばにいたい。それはまぎれもない自分の願望だ。
芹香は、紫苑を見てゆっくりと頷く。
「わかりました。華狐としての役目を果たします」
それは自分も同じだと、芹香は胸の裡でつぶやく。
「かと言って、どう切り出せばいいのかわからなくなって……、今更本当のことを言ったら芹香が呆れて帰ってしまうのではと、情けなくも今の今まで言い出せずにいたんだ」
紫苑の視線が、芹香に向けられる。
なにもかもを見通すような琥珀色をした瞳に見つめられて、芹香の胸は高鳴った。これまで毎日のように見てきた紫苑の瞳なのに、こんなに苦し気に揺れる瞳は知らない。
まるで、紫苑が自分にいなくなってほしくないと、そばにいて欲しいと言っているように聞こえて、芹香は着物の衿合わせに指先をひっかけるようにして胸元を握りしめた。
もう片方の手に、紫苑の手がそっと触れる。線は細いが大きな手は男性のそれで、芹香の身体がびくりと跳ねた。
紫苑は芹香の反応に一瞬身を固くしたが、そのまま芹香の手を取りまっすぐ見つめる。
中庭では、木々に止まった鳥たちのさえずりが響いて時折風が葉を揺らす音がするくらいで他に音はない。この場所で、狐の紫苑と過ごす穏やかな時間は芹香の大好きなひと時でもあった。それらの時間がつぎつぎと浮かんできて、触れる紫苑を拒めないでいた。
「どうか、俺のそばにいてほしい」
愛の告白のようにも取れる懇願に、体温が上がっていき顔が火照った。
しかし、
「霊狐の華狐として……、正式に俺と番になってほしい」
──霊狐の華狐として。
その言葉を聞いた瞬間、昇り詰めていた熱が瞬時に冷めていく。
紫苑は霊狐として華狐の力が必要だと言っているのだと、芹香は冷静に受け止める。
お前なんかいらないと言われなくてよかったと安堵しているのに、心の底に流れる冷たい空気はなんだろう。
考えてもわからない芹香は、見て見ぬふりをして蓋をした。
どうせ村に帰ったところで、自分を待ってくれている人も歓迎してくれる人もいないのだから、自分を必要としてくれる紫苑のそばにいたい。それはまぎれもない自分の願望だ。
芹香は、紫苑を見てゆっくりと頷く。
「わかりました。華狐としての役目を果たします」