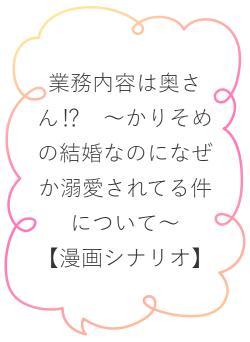「紫苑さまが霊狐さまだと黙っていたことは弁解の余地もございませんが……、この一年間、芹香さまと過ごした日々と私たちの気持ちに嘘偽りはありません。どうかそれだけはご理解くださいませんか」
「それは、理解してるつもりよ……。で、でも……っ、葉奈ならわかってくれるでしょ⁉ 私ずっと……ずーっと紫苑と一緒だったのよ⁉」
気持ちがまた高ぶり、ずっとよ!と何度も繰り返して強調せずにはいられない。
「あぁ! 私もうお嫁にいけない!」
顔を両手で覆った芹香に、「芹香さまはもう嫁がれているので大丈夫ですよ」と葉奈が苦笑する。
「あ、そうだった。……って葉奈、冷静な突っ込みはやめて」
冷めた目で葉奈を見遣るが、葉奈は気にも留めない様子で言葉をつなぐ。
「芹香さまのお気持ちはお察ししますが……霊狐さまは、疚しいお気持ちで芹香さまのおそばにいたわけでは決してありません、ということだけはお伝えしておきます。黙っていた理由については、霊狐さまご本人の口から直接お聞きになるのがよろしいかと」
「うん……、わかった。そうする」
「ありがとうございます。──お腹が空いているんじゃありませんか? 去年仕込んだ梅で粥を作ってきたんですよ。冷めないうちに召し上がってください」
傍らに置いてあった盆をすっと差し出し、土鍋の蓋が開けられる。梅干しの酸味と米の甘い匂いがふわりと鼻をかすめていった。去年の春の終わり、庭の梅の木から取れた梅の実は、半分は梅シロップにして残りの半分を梅干しにしたのだ。
つまようじで一粒一粒へたを取り除き、丁寧に洗って漬けたそれは真っ赤でしわしわで美味しい梅干しになってくれた。
酸味に刺激され、じゅわりと唾が滲みでる。
「美味しそう!」
「一緒に漬けた赤紫蘇も入れてありますよ」
お盆ごと膝の上に乗せて、芹香は匙を手に取り粥を口に運ぶ。適度な塩気と酸味とに食欲を刺激され、食べる手が止まらなくなる。
「うーん、美味しい。この赤紫蘇がまた癖になるしょっぱさ」
気付けば気分はすっかり上を向いていて、我ながら単純だなと呆れる芹香だった。
「それは、理解してるつもりよ……。で、でも……っ、葉奈ならわかってくれるでしょ⁉ 私ずっと……ずーっと紫苑と一緒だったのよ⁉」
気持ちがまた高ぶり、ずっとよ!と何度も繰り返して強調せずにはいられない。
「あぁ! 私もうお嫁にいけない!」
顔を両手で覆った芹香に、「芹香さまはもう嫁がれているので大丈夫ですよ」と葉奈が苦笑する。
「あ、そうだった。……って葉奈、冷静な突っ込みはやめて」
冷めた目で葉奈を見遣るが、葉奈は気にも留めない様子で言葉をつなぐ。
「芹香さまのお気持ちはお察ししますが……霊狐さまは、疚しいお気持ちで芹香さまのおそばにいたわけでは決してありません、ということだけはお伝えしておきます。黙っていた理由については、霊狐さまご本人の口から直接お聞きになるのがよろしいかと」
「うん……、わかった。そうする」
「ありがとうございます。──お腹が空いているんじゃありませんか? 去年仕込んだ梅で粥を作ってきたんですよ。冷めないうちに召し上がってください」
傍らに置いてあった盆をすっと差し出し、土鍋の蓋が開けられる。梅干しの酸味と米の甘い匂いがふわりと鼻をかすめていった。去年の春の終わり、庭の梅の木から取れた梅の実は、半分は梅シロップにして残りの半分を梅干しにしたのだ。
つまようじで一粒一粒へたを取り除き、丁寧に洗って漬けたそれは真っ赤でしわしわで美味しい梅干しになってくれた。
酸味に刺激され、じゅわりと唾が滲みでる。
「美味しそう!」
「一緒に漬けた赤紫蘇も入れてありますよ」
お盆ごと膝の上に乗せて、芹香は匙を手に取り粥を口に運ぶ。適度な塩気と酸味とに食欲を刺激され、食べる手が止まらなくなる。
「うーん、美味しい。この赤紫蘇がまた癖になるしょっぱさ」
気付けば気分はすっかり上を向いていて、我ながら単純だなと呆れる芹香だった。