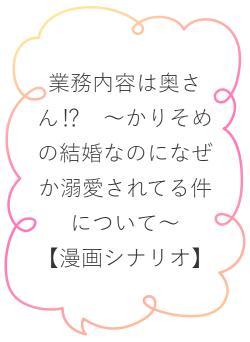戸惑う芹香に数歩近づいた紫苑は、「俺が代替わりした霊狐だ。名乗りはしなかったが、ずっと芹香のそばにいた」だから離縁はできないと、とても真面目な顔で言い放った。
「紫苑が……霊狐さま……?」
あまりの衝撃に、芹香は眩暈がした。
あの日、鳥居をくぐった先で子狐の紫苑に出会ってこの方、ずっと一緒に過ごしてきたのだ。
──そう、寝所さえも共にしていた。
今日の朝も、紫苑のぬくもりを感じながら目を覚ました。そのぬくもりが今日で最後になるかもしれないと思い、昨夜は芹香から紫苑の体に腕を巻きつけて抱きしめるようにして眠った。
それだけじゃない。
暇さえあれば膝に乗ってくる子狐を撫で、毛づくろいをし、そして抱きしめた。そのふさふさの毛並みと温かさにどれほど癒されたか。徐々に大きくなってもそれは変わらなかった。
すり寄ってくれば受け入れ、抱きしめてふさふさの毛並みを撫でてやった。芹香が落ち込んでいる時には静かに隣にいて、手を伸ばせば嫌がらずに触らせてくれた。時には慰めるように、手を、そして顔をぺろりと舐められたこともある。
その凛とした美しい顔に、自分から頬を摺り寄せることもしばしばあった。
なのに、紫苑が自分と同じか、もしくは年上の異性で、さらに自分の伴侶である霊狐だったなんて──。
「な……なんて、こと……」
忘れるほどには時間の経っていない記憶の数々が脳裡を過ぎていき、込み上げる羞恥に耐えきれなくなった芹香は、いよいよその場に膝から頽れそうになった。
「芹香っ──」
それを紫苑が手を伸ばして己の胸に抱える。遠くなる意識の中、ふんわりと香った陽だまりの香りは狐だった紫苑のそれと全く同じで。
──あぁ、この青年が間違いなくあの紫苑なのだと、芹香は理解した。
「紫苑が……霊狐さま……?」
あまりの衝撃に、芹香は眩暈がした。
あの日、鳥居をくぐった先で子狐の紫苑に出会ってこの方、ずっと一緒に過ごしてきたのだ。
──そう、寝所さえも共にしていた。
今日の朝も、紫苑のぬくもりを感じながら目を覚ました。そのぬくもりが今日で最後になるかもしれないと思い、昨夜は芹香から紫苑の体に腕を巻きつけて抱きしめるようにして眠った。
それだけじゃない。
暇さえあれば膝に乗ってくる子狐を撫で、毛づくろいをし、そして抱きしめた。そのふさふさの毛並みと温かさにどれほど癒されたか。徐々に大きくなってもそれは変わらなかった。
すり寄ってくれば受け入れ、抱きしめてふさふさの毛並みを撫でてやった。芹香が落ち込んでいる時には静かに隣にいて、手を伸ばせば嫌がらずに触らせてくれた。時には慰めるように、手を、そして顔をぺろりと舐められたこともある。
その凛とした美しい顔に、自分から頬を摺り寄せることもしばしばあった。
なのに、紫苑が自分と同じか、もしくは年上の異性で、さらに自分の伴侶である霊狐だったなんて──。
「な……なんて、こと……」
忘れるほどには時間の経っていない記憶の数々が脳裡を過ぎていき、込み上げる羞恥に耐えきれなくなった芹香は、いよいよその場に膝から頽れそうになった。
「芹香っ──」
それを紫苑が手を伸ばして己の胸に抱える。遠くなる意識の中、ふんわりと香った陽だまりの香りは狐だった紫苑のそれと全く同じで。
──あぁ、この青年が間違いなくあの紫苑なのだと、芹香は理解した。