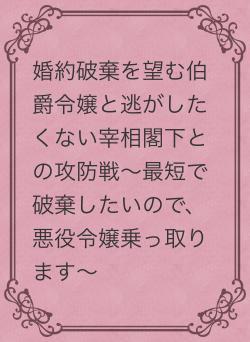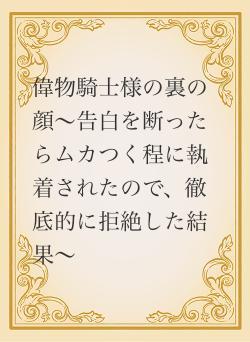「あらあら、まあまあ!」
侍女長であるエマが口を覆って目を輝かせている。その視線の先には、綺麗に着飾ったネルの姿。
髪は綺麗に結われ、香油もたっぷり塗られて全身ツルツルだ。
(ドレスなんていつぶりだろう……)
いつもは司書官の制服に身を包み、化粧なんてもう随分していない。髪も一つに束ねるだけで、髪飾りなんて今回初めて付たほど。
「娘のドレスでごめんなさいね。この屋敷には女性物のドレスは置いてなくって」
「いいえ全然大丈夫です!むしろ、ご迷惑かけてしまってすみません」
恐縮しているエマに全力で首を振って応えた。
「ふふっ、素材がいいから腕が鳴っちゃったわ」
満足げなエマを見ると、こちらもなんだか嬉しくなってしまう。
「ほお?随分と着飾ったな」
「あ、ヴィクトル様」
こちらも風呂上がりとあって、ラフな装いで壁に寄りかかっている。いつもは綺麗にセットされている髪も、無造作に下ろされて雰囲気が大分違って見える。
騎士服じゃないヴィクトルも珍しい。胸元が大きく開いた服なので、肌が露出していて視線のやり場にこまる。風呂上がりで上気した頬に、乾ききれていない髪からは水滴が滴り落ちている。
色気の暴力が凄まじく、直視出来ない。
「食事は部屋で摂る。準備を頼んだ」
「かしこまりました」
慌ただしく使用人達が部屋から出て行くと、ヴィクトルはドカッと目の前のソファに腰掛けた。
「どうした?座らないのか?」
促されるまま向かい合って座るが、どうしても目が合わせられない。
目を合わせなくても隠微な色気は、肌を通してひしひし感じる。
「そんなに怯えなくても取って喰おうなんて思ってないぞ」
私の様子を心配して声をかけてくれたが、怯えてはいない。色気に当てられてどうしていいか分からないだけ。……そんな事、恥ずかしくて言えるわけない。
顔を俯かせたまま黙っているネルに、ヴェクトルはギシッと腰を上げた。
「それとも──」
気配が近づく。
「喰われるのを期待してるのか?」
耳元で囁かれた。甘く、蕩けそうな声が脳内を侵略して、なにも考えられない。心臓が破裂しそうなほど脈打っている。
「ふはっ、まるで子ウサギの様だな。小さくて警戒心が強いのに好奇心が旺盛だ」
頬をなぞるように撫でられ、ビクッと肩が震える。顔を上げれば、息がかかりそうな距離にヴィクトルの顔がある。その綺麗な紺碧の瞳に自分の顔が映っている。そこに映っているのは自分でも見たことない顔をしている自分。
あと数センチでキスしてしまいそう……
視線がヴィクトルの唇に移ると「物欲しそうだな」と言われて、ハッと我に返った。それと同時に、身の程を弁えろと言われているようで、自分が恥ずかしくなった。
「す、すみません」と逃げるように立ちあがったが、すぐに腕を掴まれ押し倒すようにソファーに倒された。
「逃げるな」
狩猟をする猟犬のような瞳に息を飲む。
「何を期待した?」
首筋に息を吹きかけられ、ゾクッと背中が粟立つ。急かすように、ヴィクトルの手が太ももに触れてくる。
「ちゃんと言葉にしないとわからないだろ?」
優しい口調なのに、意地の悪い言葉で責め立てる。絶対に分かっていて聞いているに違いないんだ。
羞恥心で全身焼き尽くしそうなネルは、ヴィクトルの目を見ないように両手で顔を覆っていた。彼の瞳を見たら嘘は付けそうにないから──
「邪魔な手だな」
「あ!」
顔を覆っていた手を頭の上で拘束され、ヴェクトルの視線に囚われた。
「甘い香りがする。……美味そうだ」
それは香油の香りだと言いたいのに、首筋や頬に軽く口付けされて、言葉が出てこない。
唇を避けて執拗にキスしてくる所は、本当に意地が悪い。
婚約者であるオーウェンとすらキスなんて交わしたことない。したいと思った事すらない。だけど、ヴェクトルは違う。
きっと、この人とキスなんてしたら一生忘れなくなる。けど、ここで怖気付いていたら後悔する。三ヶ月後には、団長と司書官と言う関係に戻ってしまうんだから……
(恥は一瞬)
そう言い聞かせ、覚悟を決めた。
「き……」
「き?」
「き、キス……を……」
モゴモゴと口篭り、何を言っているのか分からなかったが『キス』という単語ははっきり聞き取れた。
ヴェクトルは満足そうに口角を吊り上げると、ネルの唇を荒々しく奪った。
「──んッ」
激しくて苦しいのに、蕩けるほど甘くて幸福感と高揚感で涙が滲んでくる。
「ヴェクトル……さま……」
頬を紅潮させ、熱帯び瞳で自分を求めるネルの姿を見たヴェクトルは、体の熱が疼くのが分かった。
熱をぶつけるように舌を絡ませると、不器用ながらも必死に応えようと舌を絡めてくるネルが可愛らしくて、いよいよ止まらなくなってきた。
ヴェクトルはネルの上に馬乗りになり、つと漏れ伝う唾液を拭っていた。
見下ろしてくる眼は獰猛な野獣のようで、怖いはずなのに怖くない。むしろ、目が離せなくて困ってしまう。
どうせオーウェンと別れたら独り身だ。このまま雰囲気に飲まれてしまってもいいかもしれない……
そう思っていたが、ヴェクトルの手が急に止まった。
「すまない……気持ちが急いた……」
自己嫌悪するように肩を落とし、項垂れる姿にネルは戸惑い、かける言葉が見つからない。
私なんかと情事は出来ないと言われているようで、胸が締め付けられる様に痛い。
「初めての女性にがっつくなんて紳士じゃないよな」
沈んだ顔で言ってくる。
あ、私の事を気にしてくれたのかと、この時になってようやく気が付き「ふっ」と眉を下げた。
一瞬でも卑下してしまった自分が恥ずかしい。
ヴェクトルと視線が合えば、何事も無かったかのように二人で笑い合いった。
侍女長であるエマが口を覆って目を輝かせている。その視線の先には、綺麗に着飾ったネルの姿。
髪は綺麗に結われ、香油もたっぷり塗られて全身ツルツルだ。
(ドレスなんていつぶりだろう……)
いつもは司書官の制服に身を包み、化粧なんてもう随分していない。髪も一つに束ねるだけで、髪飾りなんて今回初めて付たほど。
「娘のドレスでごめんなさいね。この屋敷には女性物のドレスは置いてなくって」
「いいえ全然大丈夫です!むしろ、ご迷惑かけてしまってすみません」
恐縮しているエマに全力で首を振って応えた。
「ふふっ、素材がいいから腕が鳴っちゃったわ」
満足げなエマを見ると、こちらもなんだか嬉しくなってしまう。
「ほお?随分と着飾ったな」
「あ、ヴィクトル様」
こちらも風呂上がりとあって、ラフな装いで壁に寄りかかっている。いつもは綺麗にセットされている髪も、無造作に下ろされて雰囲気が大分違って見える。
騎士服じゃないヴィクトルも珍しい。胸元が大きく開いた服なので、肌が露出していて視線のやり場にこまる。風呂上がりで上気した頬に、乾ききれていない髪からは水滴が滴り落ちている。
色気の暴力が凄まじく、直視出来ない。
「食事は部屋で摂る。準備を頼んだ」
「かしこまりました」
慌ただしく使用人達が部屋から出て行くと、ヴィクトルはドカッと目の前のソファに腰掛けた。
「どうした?座らないのか?」
促されるまま向かい合って座るが、どうしても目が合わせられない。
目を合わせなくても隠微な色気は、肌を通してひしひし感じる。
「そんなに怯えなくても取って喰おうなんて思ってないぞ」
私の様子を心配して声をかけてくれたが、怯えてはいない。色気に当てられてどうしていいか分からないだけ。……そんな事、恥ずかしくて言えるわけない。
顔を俯かせたまま黙っているネルに、ヴェクトルはギシッと腰を上げた。
「それとも──」
気配が近づく。
「喰われるのを期待してるのか?」
耳元で囁かれた。甘く、蕩けそうな声が脳内を侵略して、なにも考えられない。心臓が破裂しそうなほど脈打っている。
「ふはっ、まるで子ウサギの様だな。小さくて警戒心が強いのに好奇心が旺盛だ」
頬をなぞるように撫でられ、ビクッと肩が震える。顔を上げれば、息がかかりそうな距離にヴィクトルの顔がある。その綺麗な紺碧の瞳に自分の顔が映っている。そこに映っているのは自分でも見たことない顔をしている自分。
あと数センチでキスしてしまいそう……
視線がヴィクトルの唇に移ると「物欲しそうだな」と言われて、ハッと我に返った。それと同時に、身の程を弁えろと言われているようで、自分が恥ずかしくなった。
「す、すみません」と逃げるように立ちあがったが、すぐに腕を掴まれ押し倒すようにソファーに倒された。
「逃げるな」
狩猟をする猟犬のような瞳に息を飲む。
「何を期待した?」
首筋に息を吹きかけられ、ゾクッと背中が粟立つ。急かすように、ヴィクトルの手が太ももに触れてくる。
「ちゃんと言葉にしないとわからないだろ?」
優しい口調なのに、意地の悪い言葉で責め立てる。絶対に分かっていて聞いているに違いないんだ。
羞恥心で全身焼き尽くしそうなネルは、ヴィクトルの目を見ないように両手で顔を覆っていた。彼の瞳を見たら嘘は付けそうにないから──
「邪魔な手だな」
「あ!」
顔を覆っていた手を頭の上で拘束され、ヴェクトルの視線に囚われた。
「甘い香りがする。……美味そうだ」
それは香油の香りだと言いたいのに、首筋や頬に軽く口付けされて、言葉が出てこない。
唇を避けて執拗にキスしてくる所は、本当に意地が悪い。
婚約者であるオーウェンとすらキスなんて交わしたことない。したいと思った事すらない。だけど、ヴェクトルは違う。
きっと、この人とキスなんてしたら一生忘れなくなる。けど、ここで怖気付いていたら後悔する。三ヶ月後には、団長と司書官と言う関係に戻ってしまうんだから……
(恥は一瞬)
そう言い聞かせ、覚悟を決めた。
「き……」
「き?」
「き、キス……を……」
モゴモゴと口篭り、何を言っているのか分からなかったが『キス』という単語ははっきり聞き取れた。
ヴェクトルは満足そうに口角を吊り上げると、ネルの唇を荒々しく奪った。
「──んッ」
激しくて苦しいのに、蕩けるほど甘くて幸福感と高揚感で涙が滲んでくる。
「ヴェクトル……さま……」
頬を紅潮させ、熱帯び瞳で自分を求めるネルの姿を見たヴェクトルは、体の熱が疼くのが分かった。
熱をぶつけるように舌を絡ませると、不器用ながらも必死に応えようと舌を絡めてくるネルが可愛らしくて、いよいよ止まらなくなってきた。
ヴェクトルはネルの上に馬乗りになり、つと漏れ伝う唾液を拭っていた。
見下ろしてくる眼は獰猛な野獣のようで、怖いはずなのに怖くない。むしろ、目が離せなくて困ってしまう。
どうせオーウェンと別れたら独り身だ。このまま雰囲気に飲まれてしまってもいいかもしれない……
そう思っていたが、ヴェクトルの手が急に止まった。
「すまない……気持ちが急いた……」
自己嫌悪するように肩を落とし、項垂れる姿にネルは戸惑い、かける言葉が見つからない。
私なんかと情事は出来ないと言われているようで、胸が締め付けられる様に痛い。
「初めての女性にがっつくなんて紳士じゃないよな」
沈んだ顔で言ってくる。
あ、私の事を気にしてくれたのかと、この時になってようやく気が付き「ふっ」と眉を下げた。
一瞬でも卑下してしまった自分が恥ずかしい。
ヴェクトルと視線が合えば、何事も無かったかのように二人で笑い合いった。