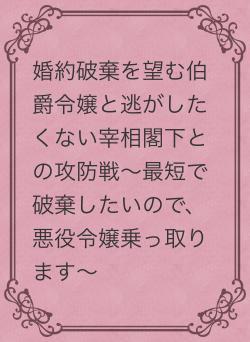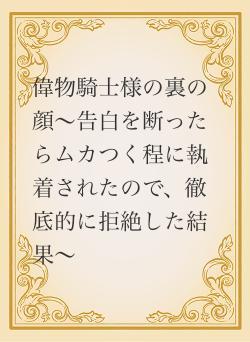ヴィクトルが城に戻ったのは昼間際だった。
「団長。何処へ行かれていたんです?」
書類を手にヴィクトルを呼び止めたのは、副団長であるランドルフ。ヴィクトルが信頼して側に置いている側近だ。
「ああ、野暮用だ」
「はあ?また女性ですか?」
晴れやかな顔をしながら言うヴィクトルを、冷徹に嫌悪感を浮かべた目で睨みつけた。
「貴方がモテるのは分かりますが、いい加減にしてください」
「そう目くじら立てるなよ。いい男が台無しだぞ?ん?」
「はぁ゛ん?」
「ッ!!」
ランドルフの機嫌を取ろうとしたが、地雷を踏み抜いたらしく、綺麗な顔が恐ろしい程歪んでいる。
「いいですか!?貴方は団長なんですよ!いつ何があるか分からないんです!女にうつつを抜かしている場合じゃないんですよ!」
「わ、わかってる。分かってるから、ちょっと落ち着け」
「いいえ。わかっていない!私が口煩く言っても分からないようならば仕方ありませんね」
チャキッと腰につけていた剣を抜き、ヴィクトルの足の間に刃を向けた。流石のヴィクトルもゾッと嫌な汗を浮かばせている。
「ちょ、ちょっと」
「そのだらしのないモノ、斬り落としてしまいましょう」
「──ヒュッ」
ランドルフの眼は瞳孔が開いた状態で、今までと本気度が違う。これは完全にやらかしたと思ったヴィクトルは勢いよくその場に土下座した。
「すまん!お前を頼り切っていた俺が悪かった!」
力では自分の方が強いので屈服させるのは簡単だ。だが、それでは信頼関係が破綻してしまう。こうして叱責されている内が花とよく言われているように、叱責されなくなったら終わりだ。これも一種の愛情表現だと思っている。
「まったく…団長ともあろうお方が簡単に土下座なんてみっともない真似しないで下さいよ。下に示しがつかなくなります」
ランドルはやれやれと、息を吐きながら剣を鞘に収めた。
「──で?今までどちらに?」
「あぁ、オルドリッジ伯爵のところのネル嬢と朝市にな」
「朝…市?」
カッと目を見開き詰め寄ってくる。
「あ、あぁ。なんだ?」
「貴方が健全な男女交際を……?」
明らかに動揺しているランドルを見て、ヴィクトルは苦笑いを浮かべながら頭を搔いた。
今までの俺の行いを考えれば動揺するのも分かるが、体を震わせるほど動揺するか?そんなにも酷かったのか?
これからは少しだけ、行動を考えなければなと考えた。
「ん?ネル嬢?」
「なんだ知ってるのか?」
「えぇ、なんせ彼女の婚約者があれですので」
あれ呼ばわりされる婚約者も珍しい。
「……同情ですか?」
「いくらお前でも許せる言葉と許せん言葉があるぞ」
鋭い眼光で睨みつけるヴィクトルを見れば、同情なんかではない事は一目瞭然。それに、ここ最近城内で囁かれている噂。
『ヴィクトル団長に本命がいる』
それが彼女と決まった訳じゃないが、タイミングが良すぎる。
フラフラしているより、身を固めてくれた方がこちらとしても嬉しいのだが、相手が良くない。
仮にも婚約者持ちの令嬢だ。それに──
「成金の坊ちゃんが黙っておりませんよ?」
「成金ってお前…相変わらず口が悪いな」
こいつの裏の顔を知っているのも俺との信用あってこそ。まあ、そう思っているのは俺だけかもしれんが。
「随分好き勝手やっているようですし、男爵も相当手を焼いている様です」
「あれをあんな風に育てのはそいつらだろ?」
今更手を焼こうが責任は親にある。
「ええ、ですから捨て駒として使うつもりのようです」
「なに?」
「彼が伯爵となり、実質の権力を持たせ所で伯爵家の資産を全て奪い、伯爵家共々切り捨てる算段のようです」
「子が子なら親も親だな」
呆れてものも言えない。
「そんな訳ですし、今後騎士の手が入りそうな家の者に妙な情を抱かれると面倒です。周りから特別扱いしているなんて言われるのは本望ではないでしょう?貴方も彼女も……」
こいつは言葉遣いこそキツイが、的確に的を射ているので文句の言いようがない。こういう時、自分の職が忌まわしく思えてくるから現金なものだ。
「……お前の言い分は分かった。要は、俺が周りから文句を言わせなきゃいいだけなんだろ」
溜息を吐きながら煩わしそうに言い捨てた。
「本当に分かってますか?」
「くどい。俺にこれ以上指図するな」
「……」
都合のいい時だけ権力を翳して黙らせる。最低だ。
(俺も人の事は言えないな)
今まで女の事で口煩く言われたが、ここまで熱くなったことはない。ネルの事になると、どうにも自制が効かない。
「……すまない。少し頭を冷やしてくる」
黙っているランドルフを横切り、その場を後にした。
過ぎ去るヴィクトルを見つめながら、ランドルフは困ったように深く息を吐いた。
「団長。何処へ行かれていたんです?」
書類を手にヴィクトルを呼び止めたのは、副団長であるランドルフ。ヴィクトルが信頼して側に置いている側近だ。
「ああ、野暮用だ」
「はあ?また女性ですか?」
晴れやかな顔をしながら言うヴィクトルを、冷徹に嫌悪感を浮かべた目で睨みつけた。
「貴方がモテるのは分かりますが、いい加減にしてください」
「そう目くじら立てるなよ。いい男が台無しだぞ?ん?」
「はぁ゛ん?」
「ッ!!」
ランドルフの機嫌を取ろうとしたが、地雷を踏み抜いたらしく、綺麗な顔が恐ろしい程歪んでいる。
「いいですか!?貴方は団長なんですよ!いつ何があるか分からないんです!女にうつつを抜かしている場合じゃないんですよ!」
「わ、わかってる。分かってるから、ちょっと落ち着け」
「いいえ。わかっていない!私が口煩く言っても分からないようならば仕方ありませんね」
チャキッと腰につけていた剣を抜き、ヴィクトルの足の間に刃を向けた。流石のヴィクトルもゾッと嫌な汗を浮かばせている。
「ちょ、ちょっと」
「そのだらしのないモノ、斬り落としてしまいましょう」
「──ヒュッ」
ランドルフの眼は瞳孔が開いた状態で、今までと本気度が違う。これは完全にやらかしたと思ったヴィクトルは勢いよくその場に土下座した。
「すまん!お前を頼り切っていた俺が悪かった!」
力では自分の方が強いので屈服させるのは簡単だ。だが、それでは信頼関係が破綻してしまう。こうして叱責されている内が花とよく言われているように、叱責されなくなったら終わりだ。これも一種の愛情表現だと思っている。
「まったく…団長ともあろうお方が簡単に土下座なんてみっともない真似しないで下さいよ。下に示しがつかなくなります」
ランドルはやれやれと、息を吐きながら剣を鞘に収めた。
「──で?今までどちらに?」
「あぁ、オルドリッジ伯爵のところのネル嬢と朝市にな」
「朝…市?」
カッと目を見開き詰め寄ってくる。
「あ、あぁ。なんだ?」
「貴方が健全な男女交際を……?」
明らかに動揺しているランドルを見て、ヴィクトルは苦笑いを浮かべながら頭を搔いた。
今までの俺の行いを考えれば動揺するのも分かるが、体を震わせるほど動揺するか?そんなにも酷かったのか?
これからは少しだけ、行動を考えなければなと考えた。
「ん?ネル嬢?」
「なんだ知ってるのか?」
「えぇ、なんせ彼女の婚約者があれですので」
あれ呼ばわりされる婚約者も珍しい。
「……同情ですか?」
「いくらお前でも許せる言葉と許せん言葉があるぞ」
鋭い眼光で睨みつけるヴィクトルを見れば、同情なんかではない事は一目瞭然。それに、ここ最近城内で囁かれている噂。
『ヴィクトル団長に本命がいる』
それが彼女と決まった訳じゃないが、タイミングが良すぎる。
フラフラしているより、身を固めてくれた方がこちらとしても嬉しいのだが、相手が良くない。
仮にも婚約者持ちの令嬢だ。それに──
「成金の坊ちゃんが黙っておりませんよ?」
「成金ってお前…相変わらず口が悪いな」
こいつの裏の顔を知っているのも俺との信用あってこそ。まあ、そう思っているのは俺だけかもしれんが。
「随分好き勝手やっているようですし、男爵も相当手を焼いている様です」
「あれをあんな風に育てのはそいつらだろ?」
今更手を焼こうが責任は親にある。
「ええ、ですから捨て駒として使うつもりのようです」
「なに?」
「彼が伯爵となり、実質の権力を持たせ所で伯爵家の資産を全て奪い、伯爵家共々切り捨てる算段のようです」
「子が子なら親も親だな」
呆れてものも言えない。
「そんな訳ですし、今後騎士の手が入りそうな家の者に妙な情を抱かれると面倒です。周りから特別扱いしているなんて言われるのは本望ではないでしょう?貴方も彼女も……」
こいつは言葉遣いこそキツイが、的確に的を射ているので文句の言いようがない。こういう時、自分の職が忌まわしく思えてくるから現金なものだ。
「……お前の言い分は分かった。要は、俺が周りから文句を言わせなきゃいいだけなんだろ」
溜息を吐きながら煩わしそうに言い捨てた。
「本当に分かってますか?」
「くどい。俺にこれ以上指図するな」
「……」
都合のいい時だけ権力を翳して黙らせる。最低だ。
(俺も人の事は言えないな)
今まで女の事で口煩く言われたが、ここまで熱くなったことはない。ネルの事になると、どうにも自制が効かない。
「……すまない。少し頭を冷やしてくる」
黙っているランドルフを横切り、その場を後にした。
過ぎ去るヴィクトルを見つめながら、ランドルフは困ったように深く息を吐いた。