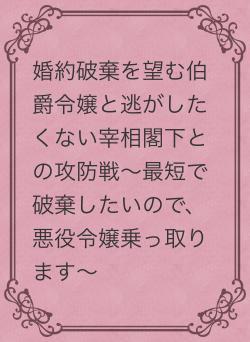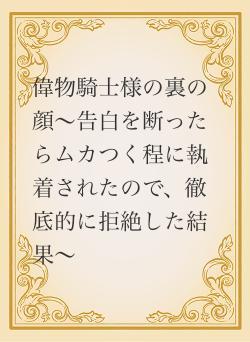朝日と共にカーテンを開け、顔を洗って髪を整える。昨晩の内にテーブルの上に用意しておいた制服に着替え、首元のリボンをキュッと締めればネルの一日が始まる。
「おはようございます」
「お、おはよう」
ヴィクトルの件が尾びれを引いているようで、みんなの様子がよそよそしい。
チラチラと視線を送ってくるだけで声をかけない者や陰でヒソヒソと噂する者。非常に仕事がやりにくい。というか、居心地が悪い。
(休めばよかった)
小さく息を吐き、棚に並べられた本に手を伸ばした。
「婚約者いるんでしょ?」
「なんでも相手の方がとんでもないクズで、あの子相手にもされてないみたいよ?」
「え!それってヴィクトル様に乗り換えようって魂胆!?」
(聞こえてるって……)
棚を挟んでいるからか、私の姿が見えていないようで言いたい放題言ってくれている。
「大人しい顔してやることは大胆よね」
「相手がクズって言われてるけど、自分はいいのかって話よね」
「ほんとそれ。まあ、クズ同士お似合いじゃない?」
「あははは!」と笑う同僚の声を聞いて、まったくその通りだと思った。恋を知りたいから疑似体験をお願いしているなんて説明したところで、共感を得られるはずがない。傍から見ればオーウェンと同じことを私はしている。
「ヴィクトル様もあんな子に目を付けられて迷惑してるわよ」
「でもさぁ、あんな子でもいけるなら私もいけるんじゃない?」
「あんたは無理よ」
「なんでよ!」と揶揄いながら言い争う声が聞こえる。周りからの反応を身に染みて感じた。
──私に彼は釣り合わない。
最初から分かっていた事だが、こうもはっきりと現実を突きつけらると少し、辛い……
『胸を張って隣にいればいい』
俯きかけた時、ヴィクトルの言葉が脳裏に響いた。その言葉が、弱くて臆病な心に灯を灯してくれた。
ネルはギュッと唇を噛み締め、顔を上げた。背筋を伸ばし、胸を張って真っ直ぐ前だけを見据え、一歩足を踏み出した。
その姿は凛として美しく、何よりも輝いて見えた。
そんなネルの姿を陰から見ていたヴィクトルは、愛おし人を見守るように暖かな眼をして微笑んでいた。
「あれ?ヴィクトル様?いつの間にいらしていたんです?」
ヴィクトルの存在に気が付いたバーノンが声を掛けたが、聞こえているのかいないのか、ヴィクトルは前を向いたまま返事がない。その視線の先にネルがいることに気付き、眉間に皺を寄せた。
「ん?あぁ、バーノンか。どうした?」
ようやく自分の存在に気付いたのかと、呆れながら息を吐いた。
「差し出がましい事を言うようですが、ネルは純粋で穢れを知らない娘です。今まで貴方が側に置いていたご令嬢達とは違う。遊び半分で側に置いているようなら今すぐ解放してあげてください」
大人しいバーノンが珍しく喧嘩腰の態度を示してきた事に驚いた。
自分の部下を守る為か、単に俺の事が気に入らないという理由か、それとも……
「彼女の婚約者の話は耳にしているでしょう?あの方は異常にプライドが高いお方だ。そういう者は自分の婚約者を他に取られるのを嫌う。貴方との噂が彼の耳に入れば、彼女は更に酷い仕打ちをされるやも知れません」
(前者だったか……)
「聞いてますか!?」
「聞いてるさ」
気だるそうに返事を返すヴィクトルは、睨みつけるバーノンを見ながら考えた。
遊び半分で彼女を側に置いていると思われていることは癪だが、今までの行いを考えれば仕方ない事だと諦めがつく。だが、婚約者の話は別だ。
単なる感情の捌け口に使い、要らなくなったら捨てようと思っていた女が、俺のような者に目をつけられと知れば、急に捨てるのを惜しがり自分の手の届く所に置きたくなる。
そこには恋愛感情はなく、あるのは単なる見栄と優越感だ。力で屈服させ、言葉で追い詰め支配する。
──本当、反吐が出る。
「お前さ、俺が誰だか分かって言ってるのか?」
頭をガシガシ掻きながら問いかけた。
「は?当たり前じゃないですか。ヴィクトル騎士団長様でしょう?」
「そう、団長様だ。その団長様が一人の女護れないんじゃ示しがつかんだろ?」
「え?は?本気で──!?」
熱い眼差しでネルの姿を見つめながら呟くヴィクトルに、バーノンは驚きで目を見開いている。
ヴィクトルは「どうだかな」と言葉を濁しながら悪戯な笑みを浮かべると、その場を後にした。
「やあ、お嬢さん方」
「ヴィ、ヴィクトル様!?」
その途中、陰口を言っていた2人の元へ顔を出した。間近でヴィクトルの姿を見れた彼女達は歓喜の表情で顔を赤らめている。
「無駄口を叩くのはいいけど、ネルを口説いたのは俺だからね。ネルを侮辱するのは許せないな」
「!!」
まさか聞かれていたとは思いもしなかったと、2人の顔は徐々に青ざめていく。
「そ、そう言う意味で言ったんじゃ……」
「ではどう言う意味で言ったのかな?」
「……」
否定の言葉を口にするが、続く言葉が見つからない。
笑顔で問い詰めるヴィクトルの圧に絶えられず、今にも泣き出しそうな彼女らを目にして、バーノンがやれやれと言った感じに声を掛けた。
「そこまでにしてやって下さい。彼女達も貴方に憧れていたので、ネルが羨ましいんですよ」
「ほう?それは嬉しいが、陰で嘲笑うのは喜ばしくない。……大切にしている人なんかを的にされると特に、ね?」
ギロッと睨みつけると、肩を震わせて逃げるように去って行った。
その姿を見たバーノンは「大人気ない」と呟いたが、ヴィクトルは黙って笑顔を向けるだけだった。
「おはようございます」
「お、おはよう」
ヴィクトルの件が尾びれを引いているようで、みんなの様子がよそよそしい。
チラチラと視線を送ってくるだけで声をかけない者や陰でヒソヒソと噂する者。非常に仕事がやりにくい。というか、居心地が悪い。
(休めばよかった)
小さく息を吐き、棚に並べられた本に手を伸ばした。
「婚約者いるんでしょ?」
「なんでも相手の方がとんでもないクズで、あの子相手にもされてないみたいよ?」
「え!それってヴィクトル様に乗り換えようって魂胆!?」
(聞こえてるって……)
棚を挟んでいるからか、私の姿が見えていないようで言いたい放題言ってくれている。
「大人しい顔してやることは大胆よね」
「相手がクズって言われてるけど、自分はいいのかって話よね」
「ほんとそれ。まあ、クズ同士お似合いじゃない?」
「あははは!」と笑う同僚の声を聞いて、まったくその通りだと思った。恋を知りたいから疑似体験をお願いしているなんて説明したところで、共感を得られるはずがない。傍から見ればオーウェンと同じことを私はしている。
「ヴィクトル様もあんな子に目を付けられて迷惑してるわよ」
「でもさぁ、あんな子でもいけるなら私もいけるんじゃない?」
「あんたは無理よ」
「なんでよ!」と揶揄いながら言い争う声が聞こえる。周りからの反応を身に染みて感じた。
──私に彼は釣り合わない。
最初から分かっていた事だが、こうもはっきりと現実を突きつけらると少し、辛い……
『胸を張って隣にいればいい』
俯きかけた時、ヴィクトルの言葉が脳裏に響いた。その言葉が、弱くて臆病な心に灯を灯してくれた。
ネルはギュッと唇を噛み締め、顔を上げた。背筋を伸ばし、胸を張って真っ直ぐ前だけを見据え、一歩足を踏み出した。
その姿は凛として美しく、何よりも輝いて見えた。
そんなネルの姿を陰から見ていたヴィクトルは、愛おし人を見守るように暖かな眼をして微笑んでいた。
「あれ?ヴィクトル様?いつの間にいらしていたんです?」
ヴィクトルの存在に気が付いたバーノンが声を掛けたが、聞こえているのかいないのか、ヴィクトルは前を向いたまま返事がない。その視線の先にネルがいることに気付き、眉間に皺を寄せた。
「ん?あぁ、バーノンか。どうした?」
ようやく自分の存在に気付いたのかと、呆れながら息を吐いた。
「差し出がましい事を言うようですが、ネルは純粋で穢れを知らない娘です。今まで貴方が側に置いていたご令嬢達とは違う。遊び半分で側に置いているようなら今すぐ解放してあげてください」
大人しいバーノンが珍しく喧嘩腰の態度を示してきた事に驚いた。
自分の部下を守る為か、単に俺の事が気に入らないという理由か、それとも……
「彼女の婚約者の話は耳にしているでしょう?あの方は異常にプライドが高いお方だ。そういう者は自分の婚約者を他に取られるのを嫌う。貴方との噂が彼の耳に入れば、彼女は更に酷い仕打ちをされるやも知れません」
(前者だったか……)
「聞いてますか!?」
「聞いてるさ」
気だるそうに返事を返すヴィクトルは、睨みつけるバーノンを見ながら考えた。
遊び半分で彼女を側に置いていると思われていることは癪だが、今までの行いを考えれば仕方ない事だと諦めがつく。だが、婚約者の話は別だ。
単なる感情の捌け口に使い、要らなくなったら捨てようと思っていた女が、俺のような者に目をつけられと知れば、急に捨てるのを惜しがり自分の手の届く所に置きたくなる。
そこには恋愛感情はなく、あるのは単なる見栄と優越感だ。力で屈服させ、言葉で追い詰め支配する。
──本当、反吐が出る。
「お前さ、俺が誰だか分かって言ってるのか?」
頭をガシガシ掻きながら問いかけた。
「は?当たり前じゃないですか。ヴィクトル騎士団長様でしょう?」
「そう、団長様だ。その団長様が一人の女護れないんじゃ示しがつかんだろ?」
「え?は?本気で──!?」
熱い眼差しでネルの姿を見つめながら呟くヴィクトルに、バーノンは驚きで目を見開いている。
ヴィクトルは「どうだかな」と言葉を濁しながら悪戯な笑みを浮かべると、その場を後にした。
「やあ、お嬢さん方」
「ヴィ、ヴィクトル様!?」
その途中、陰口を言っていた2人の元へ顔を出した。間近でヴィクトルの姿を見れた彼女達は歓喜の表情で顔を赤らめている。
「無駄口を叩くのはいいけど、ネルを口説いたのは俺だからね。ネルを侮辱するのは許せないな」
「!!」
まさか聞かれていたとは思いもしなかったと、2人の顔は徐々に青ざめていく。
「そ、そう言う意味で言ったんじゃ……」
「ではどう言う意味で言ったのかな?」
「……」
否定の言葉を口にするが、続く言葉が見つからない。
笑顔で問い詰めるヴィクトルの圧に絶えられず、今にも泣き出しそうな彼女らを目にして、バーノンがやれやれと言った感じに声を掛けた。
「そこまでにしてやって下さい。彼女達も貴方に憧れていたので、ネルが羨ましいんですよ」
「ほう?それは嬉しいが、陰で嘲笑うのは喜ばしくない。……大切にしている人なんかを的にされると特に、ね?」
ギロッと睨みつけると、肩を震わせて逃げるように去って行った。
その姿を見たバーノンは「大人気ない」と呟いたが、ヴィクトルは黙って笑顔を向けるだけだった。