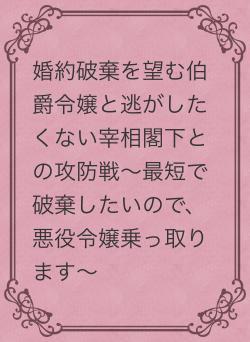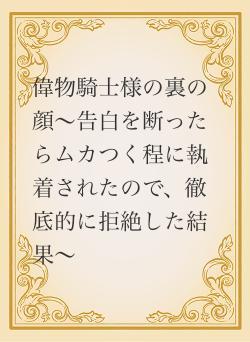ヴィクトルは屋敷に着くなり私室への人払いを使用人らに言い渡すと、ネルを抱きかかえて私室へと入っていった。
入るなりネルの唇を奪い、そのまま流れ込むようにベッドへと移動した。
「すまん。俺も余裕がないらしい。出来るだけ優しくするが、無理だと思ったらなら殴ってくれていい」
荒々しくシャツを脱ぎ捨て、自分に覆いかぶさってくるヴィクトルが視界に入るが、オーウェンと違って恐怖心は全くない。むしろドキドキと心臓が喜んでいる。
「……この状況で言うのは卑怯かもしれないが……どうしても先に言っておきたい」
真っ直ぐに真剣な瞳で見つめてくる。
「ネル、俺は君を愛してる」
「え」
「君が俺のことをどう思っていてもいい。だが、俺は今から好きな女を抱く。それだけは覚えておいてくれ」
獣のような鋭い目で見つめてくるのに、触れる手は壊れ物を扱うように優しい。ヴィクトルの気持ちを知り、驚きよりも真っ先に嬉しさが込み上げてきて、気づいたらヴィクトルの首に腕を回しキスをしていた。
「私も……私も、愛してます……」
今まで我慢していた気持ちが溢れてきて、目に涙を一杯に溜めながら伝えた。
「君という人は……」
困ったように呟いくヴィクトルを見て、ネルは顔を曇らせた。
「男を煽ったらどうなるか教えてやろう」
ヴィクトルは舌なめずりをしながら見下ろした。
***
その後、フォークナー男爵は──……
「私は何も知らん!すべて愚息のやった事だ!」
「僕は悪くない!人の女に手を出したあの男が悪いだろ!それでも騎士か!」
親子揃って自分たちの罪を認めず、自分らの保身ばかり。対応していたランドルフも頭を痛めてるほどだった。
まあ、二人のそんな言い訳が通用するはずもなく、言い渡されたのは爵位の返上と事業の撤退。事実上の経営破綻勧告となった。男爵と息子であるオーウェンは、国境付近の小さな小屋に送られそこで生活することになるだろう。今まで贅の限りを尽くしてきた二人が、どの程度まで耐えられるのかは分からない。もっとも、知る由もないが。
一方でネルの方は……
「最近のネルは随分と調子がいいみたいだね」
「はい」
相変わらず司書官として働いている。
ヴィクトルに抱かれたあの日、本当に夢のような一時だった。起きたら夢が覚めてしまうのではないかと眠るのが怖かったが、いつの間にか眠ってしまっていた。起きた時に横にヴィクトルがいた時の安心感と幸福感は今まで感じた事のないものだった。
「ネル、帰るぞ」
「あ、もうそんな時間」
ヴィクトルが迎えに来て、帰り支度をするのも見慣れた光景になってきた。オーウェンもいなくなったし、一人で帰れると言っているが「駄目だ」と毎回一蹴されてしまう。
「過保護もほどほどにした方がいいですよ?」
「自分の婚約者を迎えきて何が悪い?」
「貴方のそういうところですよ……」
バーノンとのやり取りも毎度の事。
「お待たせしました」
「じゃあ行こう」
ネルの肩を抱き、執務室を後にしようとした所でバーノンに呼び止められた。
「ネルを頼みますよ」
「言われなくても」
「もし、泣かすようなことがあれば私が貰いますからね」
「……お前、ネルの事――」
「ほら、ネルが待ってます。早く行ってあげてください」
背を押され、追い出されるようにして執務室を出たヴィクトルは、その場で盛大な溜息を吐いた。
(薄々そんな気はしていたが……)
バーノンが特定人間を気にすることは珍しいとは思っていた。それが恋慕の想いが込められているのだと気付くのに時間はかからなかった。
「まったく……不器用な奴だ」
「ヴィクトル様?どうしました?」
ネルが心配そうに顔を覗きこんできた。
「なんでもないよ」
バーノンの気持ちを知ったところでネルを渡すつもりはない。ネルには俺だけがいればいい。自分がこんなにも欲深い人間だとは知らなかった。
「ネル、俺を選んでくれてありがとう」
ヴィクトルの言葉に、ネルは優しく微笑んだ。
「それはこちらの台詞です」
暗闇の中に光をもたらしてくれた人。本当ならこの人の横にいるのすら烏滸がましい私だけど、それでもいいと自信を持たせてくれた。一生尽くしても尽くしきれない……
(この人を好きになってよかった)
二人は見つめ合い、どちらともなく唇を合わせた……
入るなりネルの唇を奪い、そのまま流れ込むようにベッドへと移動した。
「すまん。俺も余裕がないらしい。出来るだけ優しくするが、無理だと思ったらなら殴ってくれていい」
荒々しくシャツを脱ぎ捨て、自分に覆いかぶさってくるヴィクトルが視界に入るが、オーウェンと違って恐怖心は全くない。むしろドキドキと心臓が喜んでいる。
「……この状況で言うのは卑怯かもしれないが……どうしても先に言っておきたい」
真っ直ぐに真剣な瞳で見つめてくる。
「ネル、俺は君を愛してる」
「え」
「君が俺のことをどう思っていてもいい。だが、俺は今から好きな女を抱く。それだけは覚えておいてくれ」
獣のような鋭い目で見つめてくるのに、触れる手は壊れ物を扱うように優しい。ヴィクトルの気持ちを知り、驚きよりも真っ先に嬉しさが込み上げてきて、気づいたらヴィクトルの首に腕を回しキスをしていた。
「私も……私も、愛してます……」
今まで我慢していた気持ちが溢れてきて、目に涙を一杯に溜めながら伝えた。
「君という人は……」
困ったように呟いくヴィクトルを見て、ネルは顔を曇らせた。
「男を煽ったらどうなるか教えてやろう」
ヴィクトルは舌なめずりをしながら見下ろした。
***
その後、フォークナー男爵は──……
「私は何も知らん!すべて愚息のやった事だ!」
「僕は悪くない!人の女に手を出したあの男が悪いだろ!それでも騎士か!」
親子揃って自分たちの罪を認めず、自分らの保身ばかり。対応していたランドルフも頭を痛めてるほどだった。
まあ、二人のそんな言い訳が通用するはずもなく、言い渡されたのは爵位の返上と事業の撤退。事実上の経営破綻勧告となった。男爵と息子であるオーウェンは、国境付近の小さな小屋に送られそこで生活することになるだろう。今まで贅の限りを尽くしてきた二人が、どの程度まで耐えられるのかは分からない。もっとも、知る由もないが。
一方でネルの方は……
「最近のネルは随分と調子がいいみたいだね」
「はい」
相変わらず司書官として働いている。
ヴィクトルに抱かれたあの日、本当に夢のような一時だった。起きたら夢が覚めてしまうのではないかと眠るのが怖かったが、いつの間にか眠ってしまっていた。起きた時に横にヴィクトルがいた時の安心感と幸福感は今まで感じた事のないものだった。
「ネル、帰るぞ」
「あ、もうそんな時間」
ヴィクトルが迎えに来て、帰り支度をするのも見慣れた光景になってきた。オーウェンもいなくなったし、一人で帰れると言っているが「駄目だ」と毎回一蹴されてしまう。
「過保護もほどほどにした方がいいですよ?」
「自分の婚約者を迎えきて何が悪い?」
「貴方のそういうところですよ……」
バーノンとのやり取りも毎度の事。
「お待たせしました」
「じゃあ行こう」
ネルの肩を抱き、執務室を後にしようとした所でバーノンに呼び止められた。
「ネルを頼みますよ」
「言われなくても」
「もし、泣かすようなことがあれば私が貰いますからね」
「……お前、ネルの事――」
「ほら、ネルが待ってます。早く行ってあげてください」
背を押され、追い出されるようにして執務室を出たヴィクトルは、その場で盛大な溜息を吐いた。
(薄々そんな気はしていたが……)
バーノンが特定人間を気にすることは珍しいとは思っていた。それが恋慕の想いが込められているのだと気付くのに時間はかからなかった。
「まったく……不器用な奴だ」
「ヴィクトル様?どうしました?」
ネルが心配そうに顔を覗きこんできた。
「なんでもないよ」
バーノンの気持ちを知ったところでネルを渡すつもりはない。ネルには俺だけがいればいい。自分がこんなにも欲深い人間だとは知らなかった。
「ネル、俺を選んでくれてありがとう」
ヴィクトルの言葉に、ネルは優しく微笑んだ。
「それはこちらの台詞です」
暗闇の中に光をもたらしてくれた人。本当ならこの人の横にいるのすら烏滸がましい私だけど、それでもいいと自信を持たせてくれた。一生尽くしても尽くしきれない……
(この人を好きになってよかった)
二人は見つめ合い、どちらともなく唇を合わせた……