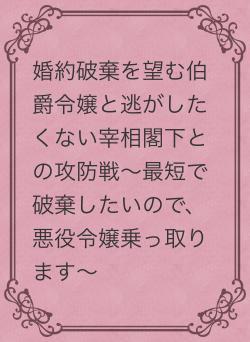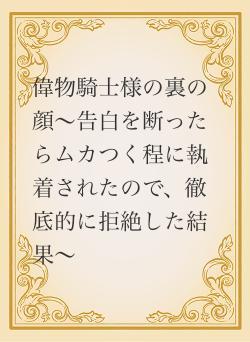パーンッ!
その日、肌を打つ乾いた音が城の中庭に響き渡った。
「女の癖に生意気なんだよ!お前は男を引き立てる事すら知らないのか!?」
打たれた頬を赤く腫らせ、顔を俯かせているのはネル・オルドリッジ。そのネルに怒号を浴びせているのは婚約者であるオーウェン・フォークナー。その傍らには、嘲笑いながらこちらを見下ろす令嬢の姿がある。
「チッ、なんでこんな奴が俺の婚約者なんだよ」
苛立ちながら髪を搔き上げるオーウェンを見て、ネルはキュッと唇を噛み締めた。
「なんだその目は!」
睨みつけた訳ではないが、相手にとっては生意気に見えたのだろう。オーウェンは大きく手を振りかぶり、風を切るように勢い良く振り下ろした。
──が、その手はネルにぶつけられる事なく、パシッと大きな手によって止められた。
「随分と威勢のいい奴がいるなぁ」
「!!」
オーウェンを笑顔で睨みつけるのは、この国の騎士団長ヴィクトル・ギルフォートだった。恰幅のいい体格で自分よりも高い目線で見下ろされて、オーウェンの顔色が悪くなるのが分かった。
「……で?この手をどうするつもりかな?」
「──ッ!」
ギリッと掴んでいる手に力を込めると、オーウェンの顔が痛みで歪んだ。
流石に団長相手では分が悪いと思ったのだろう。振り払うようにしてヴィクトルの手を解くと、悔しそうにネルを睨みつけてから逃げるようにしてその場から去って行った。
ヴィクトルは「さて」と息を吐き、ネルの前に手を差し出した。
「大丈夫かい?」
「ええ、お見苦しい所をお見せいたしました」
「君は確か、司書室の……」
「はい。司書官を務めるネル・オルドリッチと申します」
深々と頭を下げて名を告げた。
物心がついた頃から本が好きで、司書官という職は私の幼い頃からの夢だった。元々真面目な性格で勉強熱心なところがあり、集中すると周りに目が届かなくなったりもした。学園時代もそのせいで苦労した。気がつけば友達と呼べる者は誰もおらず、いつも一人だった。その在学中にオーウェンとの婚約が決まった。
オーウェンは私とは違って社交的で交友関係も多くあった。言葉を並べれば聞こえはいいが、要は遊び人だという事。婚約が決まってもそれは変わる事はなく、注意すれば怒鳴られ殴りつけてくる始末。
「俺が口を出すのもおかしいとは思うが、彼が婚約者で大丈夫かい?」
「……」
腫れた頬を優しく撫でられた。こんな優しくされたら、困ったように笑うのが精一杯。
この婚約は親同士が決めたもの。伯爵家であるオルドリッチ家と男爵家でありながら商家として成功を収めているフォークナー家。この二つの家の繋がりが私達の婚約。オーウェンはゆくゆくは婿としてオルドリッチ家に入ることが決まっている。
「親に相談したのか?」
「……相談したところでどうしようもありません」
実は、この婚約を解消したくても出来ない理由がある。それが、我が家の財政に関すること。
「我が家の醜態を晒すようであまり口にはしたくないのですが……」
私の母は父と結婚する前は侯爵令嬢で、欲しいと言えば何でも買ってもらっていたお嬢様。何不自由のない生活で悠々自適に過ごしていた。そんな時、伯爵家である父と出会い恋に落ちた。当然、周りからの反発も凄かったらしいが、侯爵家の反対を聞かずに結婚。
伯爵家と侯爵家ではそれなりに価値観も生活も変わってくる。最初こそ不満もなく穏やかに生活出来ていたが、私を妊娠したのを機に感情が一変。
初めての妊娠、出産、育児で母のストレスが限界を迎えた。
そのストレスの捌け口が、ドレスや宝石など豪華な宝飾品を買い集める事だった。湯水のように金を使い込み、気が付いた時には手に負えないとこまで来ていた。母の生家である侯爵家には、父との結婚の際に絶縁状を叩きつけられていて金の無心は出来ない。
そんな時に沸いて出たオーウェンとの婚約。……そう。婚約なんて言われているが、体よく売られただけ。籍を入れたら最後、伯爵家は彼の手に渡り私達一家は路頭に迷うだろう。
「ですが、そこまで分かっていて何もしない馬鹿ではありません」
司書官という職は、いうなれば役人と同義。安定職万歳。幼い頃の夢がこういった形で役に立つと言うのは心苦しい気もするが、嘆いたところで金が入る訳でもない。
オーウェンの家に借りた分は簡単に返せる額ではないが、両親を養えるぐらいは出来る。
「今は金を溜めながら両親と住む場所を探している所です」
「……使い込んだのは母親だろう?その責を君が負う事はない。いっその事、両親共々捨ててしまえばいいじゃないか」
「いいえ。産んで育ててくれたことに変わりはありません。それに、仮に見捨てたとしても血の繋がりは消えません。腐っても肉塊になっても私の両親なんです」
眉を下げて苦笑すると、ヴィクトルは優しく微笑み「強いな」と呟いた。
「君の魅力を分からんような奴だ。ろくな女を連れてないと見える」
「そうだといいです」
「クスッ」と笑うネルを見たヴィクトルは、思わず目を奪われた。
ヴィクトルの知るネルは、常に無表情で淡々と仕事をこなす人物だった。時折、顔や体に痣を付けてくることがあり、気にはしていたが……
(こんなの反則だろ)
人生に楽しみなんか無いように見えて、しっかりとした未来を見据えている彼女の姿は勇ましく、自然に微笑む姿はとても愛らしい……目を奪われるのも仕方ない。
「……本当、勿体ないな」
「え?」
「いやなんでもない」
(俺は何を言おうとしたんだ)
ヴィクトルは誤魔化すように言葉を濁した。
「そうだな。あの男から解放されたら、君に相応しい男を見つければいい。あんな男、すぐに忘れられるよ」
「いや、私は……」
否定するように頭を振るネルに、ヴィクトルは「ずっと独り身でいつもりか」と問いかけたが、ネルは再び首を振った。
「本を読む人間としましては、恋愛というものに関心も興味もあります」
私だって、人並み程度には恋愛というものに憧れはある。恋愛小説の様な恋は求めないにしろ、自分を愛してくれる人と一緒になりたい。
ただ、それがどういった気持ちを言うのか分からない。
「如何せん婚約者があの様な者では、恋愛の定義が分からなくなってしまって……」
「なるほど」
ネルの応えに、ヴィクトルは何かを考えるような素振りを見せていた。
「……これは提案であって強制では無いが」そう前置きした上で言葉を続けた。
「俺が教えてやろうか?」
「え?」
その日、肌を打つ乾いた音が城の中庭に響き渡った。
「女の癖に生意気なんだよ!お前は男を引き立てる事すら知らないのか!?」
打たれた頬を赤く腫らせ、顔を俯かせているのはネル・オルドリッジ。そのネルに怒号を浴びせているのは婚約者であるオーウェン・フォークナー。その傍らには、嘲笑いながらこちらを見下ろす令嬢の姿がある。
「チッ、なんでこんな奴が俺の婚約者なんだよ」
苛立ちながら髪を搔き上げるオーウェンを見て、ネルはキュッと唇を噛み締めた。
「なんだその目は!」
睨みつけた訳ではないが、相手にとっては生意気に見えたのだろう。オーウェンは大きく手を振りかぶり、風を切るように勢い良く振り下ろした。
──が、その手はネルにぶつけられる事なく、パシッと大きな手によって止められた。
「随分と威勢のいい奴がいるなぁ」
「!!」
オーウェンを笑顔で睨みつけるのは、この国の騎士団長ヴィクトル・ギルフォートだった。恰幅のいい体格で自分よりも高い目線で見下ろされて、オーウェンの顔色が悪くなるのが分かった。
「……で?この手をどうするつもりかな?」
「──ッ!」
ギリッと掴んでいる手に力を込めると、オーウェンの顔が痛みで歪んだ。
流石に団長相手では分が悪いと思ったのだろう。振り払うようにしてヴィクトルの手を解くと、悔しそうにネルを睨みつけてから逃げるようにしてその場から去って行った。
ヴィクトルは「さて」と息を吐き、ネルの前に手を差し出した。
「大丈夫かい?」
「ええ、お見苦しい所をお見せいたしました」
「君は確か、司書室の……」
「はい。司書官を務めるネル・オルドリッチと申します」
深々と頭を下げて名を告げた。
物心がついた頃から本が好きで、司書官という職は私の幼い頃からの夢だった。元々真面目な性格で勉強熱心なところがあり、集中すると周りに目が届かなくなったりもした。学園時代もそのせいで苦労した。気がつけば友達と呼べる者は誰もおらず、いつも一人だった。その在学中にオーウェンとの婚約が決まった。
オーウェンは私とは違って社交的で交友関係も多くあった。言葉を並べれば聞こえはいいが、要は遊び人だという事。婚約が決まってもそれは変わる事はなく、注意すれば怒鳴られ殴りつけてくる始末。
「俺が口を出すのもおかしいとは思うが、彼が婚約者で大丈夫かい?」
「……」
腫れた頬を優しく撫でられた。こんな優しくされたら、困ったように笑うのが精一杯。
この婚約は親同士が決めたもの。伯爵家であるオルドリッチ家と男爵家でありながら商家として成功を収めているフォークナー家。この二つの家の繋がりが私達の婚約。オーウェンはゆくゆくは婿としてオルドリッチ家に入ることが決まっている。
「親に相談したのか?」
「……相談したところでどうしようもありません」
実は、この婚約を解消したくても出来ない理由がある。それが、我が家の財政に関すること。
「我が家の醜態を晒すようであまり口にはしたくないのですが……」
私の母は父と結婚する前は侯爵令嬢で、欲しいと言えば何でも買ってもらっていたお嬢様。何不自由のない生活で悠々自適に過ごしていた。そんな時、伯爵家である父と出会い恋に落ちた。当然、周りからの反発も凄かったらしいが、侯爵家の反対を聞かずに結婚。
伯爵家と侯爵家ではそれなりに価値観も生活も変わってくる。最初こそ不満もなく穏やかに生活出来ていたが、私を妊娠したのを機に感情が一変。
初めての妊娠、出産、育児で母のストレスが限界を迎えた。
そのストレスの捌け口が、ドレスや宝石など豪華な宝飾品を買い集める事だった。湯水のように金を使い込み、気が付いた時には手に負えないとこまで来ていた。母の生家である侯爵家には、父との結婚の際に絶縁状を叩きつけられていて金の無心は出来ない。
そんな時に沸いて出たオーウェンとの婚約。……そう。婚約なんて言われているが、体よく売られただけ。籍を入れたら最後、伯爵家は彼の手に渡り私達一家は路頭に迷うだろう。
「ですが、そこまで分かっていて何もしない馬鹿ではありません」
司書官という職は、いうなれば役人と同義。安定職万歳。幼い頃の夢がこういった形で役に立つと言うのは心苦しい気もするが、嘆いたところで金が入る訳でもない。
オーウェンの家に借りた分は簡単に返せる額ではないが、両親を養えるぐらいは出来る。
「今は金を溜めながら両親と住む場所を探している所です」
「……使い込んだのは母親だろう?その責を君が負う事はない。いっその事、両親共々捨ててしまえばいいじゃないか」
「いいえ。産んで育ててくれたことに変わりはありません。それに、仮に見捨てたとしても血の繋がりは消えません。腐っても肉塊になっても私の両親なんです」
眉を下げて苦笑すると、ヴィクトルは優しく微笑み「強いな」と呟いた。
「君の魅力を分からんような奴だ。ろくな女を連れてないと見える」
「そうだといいです」
「クスッ」と笑うネルを見たヴィクトルは、思わず目を奪われた。
ヴィクトルの知るネルは、常に無表情で淡々と仕事をこなす人物だった。時折、顔や体に痣を付けてくることがあり、気にはしていたが……
(こんなの反則だろ)
人生に楽しみなんか無いように見えて、しっかりとした未来を見据えている彼女の姿は勇ましく、自然に微笑む姿はとても愛らしい……目を奪われるのも仕方ない。
「……本当、勿体ないな」
「え?」
「いやなんでもない」
(俺は何を言おうとしたんだ)
ヴィクトルは誤魔化すように言葉を濁した。
「そうだな。あの男から解放されたら、君に相応しい男を見つければいい。あんな男、すぐに忘れられるよ」
「いや、私は……」
否定するように頭を振るネルに、ヴィクトルは「ずっと独り身でいつもりか」と問いかけたが、ネルは再び首を振った。
「本を読む人間としましては、恋愛というものに関心も興味もあります」
私だって、人並み程度には恋愛というものに憧れはある。恋愛小説の様な恋は求めないにしろ、自分を愛してくれる人と一緒になりたい。
ただ、それがどういった気持ちを言うのか分からない。
「如何せん婚約者があの様な者では、恋愛の定義が分からなくなってしまって……」
「なるほど」
ネルの応えに、ヴィクトルは何かを考えるような素振りを見せていた。
「……これは提案であって強制では無いが」そう前置きした上で言葉を続けた。
「俺が教えてやろうか?」
「え?」