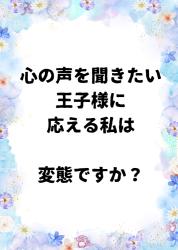「んむっ……モグモグ。んまい」
しかし、これから団子を食べるのになぜ……。
「そう。か、勘違いしないでよね。他の男子に先を越されたくなかっただけなんだから」
「!?!? ラビッツの手作り!?」
寮には生徒用の調理場が開放されていて、予約表へ記入すれば自由に使える。男女は食堂だけが共通で、それ以外は別だ。女子寮の調理場の利用状況は知らない。
まさか、そこを使って!?
「い、一応そうね」
「美味すぎる。最高だ。惚れた。いや、前から惚れてたけど惚れた。全部くれ」
「今からお団子を食べるでしょう。さっきも言ったけど、先を越されたくなかっただけなんだからっ」
「分かった。あとで味わって食べるから全部くれ」
「……仕方ないわね」
小さな紙袋には六枚ほど入っている。
「他の奴にもあげたのか?」
さすがにクッキーを作って六枚にしかならないことはないだろう。女子寮で作ったのなら、ルリアンたちに配ったのだろうか。すごいな。こっちの世界では侯爵令嬢。料理を嗜む機会はなかったはずだ。
「ち、違うわよ! あんたにしかっ……あ、味見しすぎたのよ。それに、場所によって少し硬いところもあって……。あ、硬いって言ってもね、少しだけよ。釘を打てるくらいにはなっていないわよ」
「釘を打てるクッキーはないだろう」
「何言ってるの、思いっきりあるわよ。失敗すると歯が砕けそうなクッキーになるのよ」
「……失敗したのか?」
「あっ」
「それも欲しかったな」
「ちゃんと自分で食べて、もう一回作り直したわ」
俺のために作り直しまで!?
ラビッツの背後に後光でも見えるようだ。もしかしなくても俺は今、前世も合わせた人生の中で初めて女の子の手作りお菓子を食べるの図になっていたのかもしれない。お団子なんて放っておいて、今すぐクッキーを全部食べたい。
ラビッツの手がまだ少し震えている。なぜか涙目にもなっている。
あ! もしかして、お世辞かと思って震えているのか!? そうだよな、一度歯が砕けそうなクッキーを作ったのなら、不安に思うのも当然だ。
女心の分からない自分が歯痒いな。
「ありがとう。まさに奇跡を閉じ込めたような美味しさだよ。口の中に春が訪れたようだ。こんなに美味しいクッキーを食べたら、もう君以外が作ったクッキーなんて食べられない。ラビッツ、君はまさに――、」
バシーン!
扇子が降ってきた。
「おおげさ」
「理不尽だ!」
とりあえず、手の震えは収まったようだ。女心は分からないが、それでよしとしよう。
「ラビッツ、好きだ」
「……し、知ってるわよ」
「女の子に手作りお菓子をもらったのは人生で初めてだ」
「あっそ。よかったわね」
俺を睨む顔も、その全てが愛おしい。次に何を言おうか迷ったその時。
「お待たせしました! 全員、出来上がりました。いよいよ、審査のお時間です!」
進行役の侯爵令息、セヴォルトが声を張り上げた。
しかし、これから団子を食べるのになぜ……。
「そう。か、勘違いしないでよね。他の男子に先を越されたくなかっただけなんだから」
「!?!? ラビッツの手作り!?」
寮には生徒用の調理場が開放されていて、予約表へ記入すれば自由に使える。男女は食堂だけが共通で、それ以外は別だ。女子寮の調理場の利用状況は知らない。
まさか、そこを使って!?
「い、一応そうね」
「美味すぎる。最高だ。惚れた。いや、前から惚れてたけど惚れた。全部くれ」
「今からお団子を食べるでしょう。さっきも言ったけど、先を越されたくなかっただけなんだからっ」
「分かった。あとで味わって食べるから全部くれ」
「……仕方ないわね」
小さな紙袋には六枚ほど入っている。
「他の奴にもあげたのか?」
さすがにクッキーを作って六枚にしかならないことはないだろう。女子寮で作ったのなら、ルリアンたちに配ったのだろうか。すごいな。こっちの世界では侯爵令嬢。料理を嗜む機会はなかったはずだ。
「ち、違うわよ! あんたにしかっ……あ、味見しすぎたのよ。それに、場所によって少し硬いところもあって……。あ、硬いって言ってもね、少しだけよ。釘を打てるくらいにはなっていないわよ」
「釘を打てるクッキーはないだろう」
「何言ってるの、思いっきりあるわよ。失敗すると歯が砕けそうなクッキーになるのよ」
「……失敗したのか?」
「あっ」
「それも欲しかったな」
「ちゃんと自分で食べて、もう一回作り直したわ」
俺のために作り直しまで!?
ラビッツの背後に後光でも見えるようだ。もしかしなくても俺は今、前世も合わせた人生の中で初めて女の子の手作りお菓子を食べるの図になっていたのかもしれない。お団子なんて放っておいて、今すぐクッキーを全部食べたい。
ラビッツの手がまだ少し震えている。なぜか涙目にもなっている。
あ! もしかして、お世辞かと思って震えているのか!? そうだよな、一度歯が砕けそうなクッキーを作ったのなら、不安に思うのも当然だ。
女心の分からない自分が歯痒いな。
「ありがとう。まさに奇跡を閉じ込めたような美味しさだよ。口の中に春が訪れたようだ。こんなに美味しいクッキーを食べたら、もう君以外が作ったクッキーなんて食べられない。ラビッツ、君はまさに――、」
バシーン!
扇子が降ってきた。
「おおげさ」
「理不尽だ!」
とりあえず、手の震えは収まったようだ。女心は分からないが、それでよしとしよう。
「ラビッツ、好きだ」
「……し、知ってるわよ」
「女の子に手作りお菓子をもらったのは人生で初めてだ」
「あっそ。よかったわね」
俺を睨む顔も、その全てが愛おしい。次に何を言おうか迷ったその時。
「お待たせしました! 全員、出来上がりました。いよいよ、審査のお時間です!」
進行役の侯爵令息、セヴォルトが声を張り上げた。