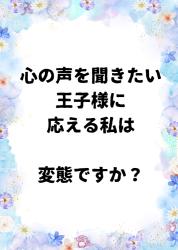「振れてますね」
「どえー!?」
導きのペンデュラムがドワンドワンと激しく揺れている。引きが強い方向へと動かすと、とある場所でピタッと止まった。ややずらせば、また動く。
マジか。
ゲームでは振れていなかった。初日だしと、皆でのんびりパトロールするだけだったのに。
「この場所ですね」
「ドーナツ岩と試しの女神像……」
ベル子が小さく呟いた。
学園の湖畔には、人の五倍以上はあろうかという巨大な岩がそびえ立っている。その中央には穴が穿たれ、女神像がちょこんと鎮座している。ゲームの中で訪れたことのある場所だ。
「では、早速レッツゴーです!」
ルリアンが元気よく言って、ぞろぞろと教室を出るが……俺とラビッツは自然と寄り添って小声でヒソヒソと話す。
「……ニコラ、どう思う?」
「ゲームと違うな」
「ええ。気をつけた方がいいかもしれない」
「そうだな」
ルリアンは「初めてのパトロール、初めての任務ですね〜」と浮かれている。やる気のなさそうなリュークに、何があるのかと疑問符を浮かべるベル子。そんな三人と、のんびり歩く。
……危機感はまるでない。
「どうする、ラビッツ」
「行くしかないでしょ。そのためのパトロール隊なんだから。私の側から離れないでよ、リュークの側からもね」
俺の護衛を兼ねているリュークと、いざとなれば転移魔法を使えるラビッツ。俺を守るのが使命とはいえ……。
「俺だって強いんだぜ?」
「それはそうでしょ。王子なんだから」
「俺だってラビッツを守りたい」
「守られるのがあなたの仕事よ。これでも家からかなり言われてるのよ」
「うう……」
かっこ悪いんだよな。
俺だって、結構やるのに。
「俺の後ろに隠れろ、とか言ってみたい」
「……黒子が出てきそうね」
やはり黒子と呼ぶか。ゲームでも通称・黒子だったからな。黒くないけど。
「命に代えても守るとかやったらさ、ラビッツも俺を見直してくれるだろ?」
「……見直しても死んでるなら意味ないわね。というか、どの面下げて私だけ生き残るのよ。絶対イヤ。家に顔向けできなくなるのよ。全員で転移は無理だけど……」
「俺だって嫌だ。皆を見捨てて自分だけ逃げて、何が王子だ。そんなんで国なんか背負えるかよ」
「…………」
あれ?
なんか黙ったぞ?
「ラビッツ?」
「そ、そう。それなら全員無事に戻るしかないわね」
「ああ。安全第一だな」
「でも、何かあったらすぐに転移できるように掴んどくから」
「え?」
ラビッツが俺の袖をぎゅっと……服の布地だけだけど、ときめくぞ。
「ちゃんと、守る」
家でそうしろと、散々言われてきたのだろう。転移魔法の使い手としての自覚を持てと。何を犠牲にしてでも、国の王子だけは生かさなくてはならない、と。
だからこそ、ゲーム内でリュークと両想いになった場合、二人が結ばれるためには俺から婚約破棄するしかなかった。リュークとラビッツの両親にはしっかりと根回しをし、「二人で仲よく俺を守ってくれよ」とヘラヘラ笑って祝うニコラ・スタッドボルトは、まさにリュークの親友だった。
転生したラビッツも、同じように何度も言われてきたに違いない。俺の婚約者の自覚を持て、と……。
彼女の手が少し震えている。魔法の存在する世界での、思わぬ展開。俺を守ると言いながらも、本当に怖いのはラビッツの方だったのかもしれない。お化け屋敷でツレの袖を掴むタイプなのかもな。
ゲームとは違う。魔法が原因での死亡事故も、この世界にはありふれているという知識もある。
「かっこよく俺が守るさ」
そう言わせてくれよ。
かっこつけたい。
好きな子の前でさえかっこつけられなかったら、男として終わりだろ?
「どえー!?」
導きのペンデュラムがドワンドワンと激しく揺れている。引きが強い方向へと動かすと、とある場所でピタッと止まった。ややずらせば、また動く。
マジか。
ゲームでは振れていなかった。初日だしと、皆でのんびりパトロールするだけだったのに。
「この場所ですね」
「ドーナツ岩と試しの女神像……」
ベル子が小さく呟いた。
学園の湖畔には、人の五倍以上はあろうかという巨大な岩がそびえ立っている。その中央には穴が穿たれ、女神像がちょこんと鎮座している。ゲームの中で訪れたことのある場所だ。
「では、早速レッツゴーです!」
ルリアンが元気よく言って、ぞろぞろと教室を出るが……俺とラビッツは自然と寄り添って小声でヒソヒソと話す。
「……ニコラ、どう思う?」
「ゲームと違うな」
「ええ。気をつけた方がいいかもしれない」
「そうだな」
ルリアンは「初めてのパトロール、初めての任務ですね〜」と浮かれている。やる気のなさそうなリュークに、何があるのかと疑問符を浮かべるベル子。そんな三人と、のんびり歩く。
……危機感はまるでない。
「どうする、ラビッツ」
「行くしかないでしょ。そのためのパトロール隊なんだから。私の側から離れないでよ、リュークの側からもね」
俺の護衛を兼ねているリュークと、いざとなれば転移魔法を使えるラビッツ。俺を守るのが使命とはいえ……。
「俺だって強いんだぜ?」
「それはそうでしょ。王子なんだから」
「俺だってラビッツを守りたい」
「守られるのがあなたの仕事よ。これでも家からかなり言われてるのよ」
「うう……」
かっこ悪いんだよな。
俺だって、結構やるのに。
「俺の後ろに隠れろ、とか言ってみたい」
「……黒子が出てきそうね」
やはり黒子と呼ぶか。ゲームでも通称・黒子だったからな。黒くないけど。
「命に代えても守るとかやったらさ、ラビッツも俺を見直してくれるだろ?」
「……見直しても死んでるなら意味ないわね。というか、どの面下げて私だけ生き残るのよ。絶対イヤ。家に顔向けできなくなるのよ。全員で転移は無理だけど……」
「俺だって嫌だ。皆を見捨てて自分だけ逃げて、何が王子だ。そんなんで国なんか背負えるかよ」
「…………」
あれ?
なんか黙ったぞ?
「ラビッツ?」
「そ、そう。それなら全員無事に戻るしかないわね」
「ああ。安全第一だな」
「でも、何かあったらすぐに転移できるように掴んどくから」
「え?」
ラビッツが俺の袖をぎゅっと……服の布地だけだけど、ときめくぞ。
「ちゃんと、守る」
家でそうしろと、散々言われてきたのだろう。転移魔法の使い手としての自覚を持てと。何を犠牲にしてでも、国の王子だけは生かさなくてはならない、と。
だからこそ、ゲーム内でリュークと両想いになった場合、二人が結ばれるためには俺から婚約破棄するしかなかった。リュークとラビッツの両親にはしっかりと根回しをし、「二人で仲よく俺を守ってくれよ」とヘラヘラ笑って祝うニコラ・スタッドボルトは、まさにリュークの親友だった。
転生したラビッツも、同じように何度も言われてきたに違いない。俺の婚約者の自覚を持て、と……。
彼女の手が少し震えている。魔法の存在する世界での、思わぬ展開。俺を守ると言いながらも、本当に怖いのはラビッツの方だったのかもしれない。お化け屋敷でツレの袖を掴むタイプなのかもな。
ゲームとは違う。魔法が原因での死亡事故も、この世界にはありふれているという知識もある。
「かっこよく俺が守るさ」
そう言わせてくれよ。
かっこつけたい。
好きな子の前でさえかっこつけられなかったら、男として終わりだろ?