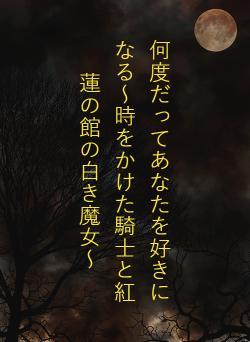仕込みのあいだに作って振舞うクレープは思った以上に好評で、
「手で持って食べられるクレープですか! なんて斬新なことを」
と、まず驚かれた。
キャロルお気に入りのキャラメルナッツはもちろん、軽食として作った野菜や油漬けの魚を巻いたクレープには絶句からの絶賛といった具合で、「クレープに不可能はないのか」と大真面目に言われた時は、笑うのをこらえるのが大変だったくらいだ。
持ち帰りできたらいいのにという呟きを耳にし、具を包んだクレープを用意すると、護衛後の土産の定番になってしまう。
カフェでも通常メニューにしてはと言われたが、正直にまだ難しいと話すと、「今のままでも特別感はありますね!」と微笑まれ、その笑顔の美しさにしばしぼーっとなってしまったのは言うまでもない。
貴族の女性が通える学校というものがない世界だ。社交界デビューしていないグレースにとって、お客様相手とはまた違う、同世代の女性と関わるのは楽しい日々だった。
そんなある日。
「今日はモリーさんを連れて外で食事をしますね」
護衛の女性たちからそう言われ、自分は? と一瞬寂しく思った日。閉店間際にオズワルドが訪れた。
「外は男性が警護してますのでご心配なく」
と女性護衛の一人が片目をつむって、皆でぞろぞろ出ていく。
何が起こったのかわからないまま、二人きりになった店内で、グレースは急に恥ずかしくなってもじもじし始めた。
こんなに長く会えなかったことは初めてで、会ったら言おうと思っていたことが全部頭から消えてしまう。
それでも平静を装いながら普段通りコーヒーを淹れていると、今日のオズワルドは雰囲気が違うことに気づいた。何が違うのだろうと、カップを置きつつさりげなく彼を一瞥し、その髪の生え際が白っぽい金色になっていることに気づく。
(あ、逆プリンになってる。地毛はあんな色だったのね)
濃い色に染めることもあるのかと特に疑問も持たず、むしろ、地の髪の色がヒヨコみたいで可愛いなどと思いきゅんとする。
コーヒーには女の子たち用に焼いていた絞り出しクッキーを添えた。
「食事はどうされますか?」
あくまで客として扱うと、オズワルドは座ってくれないかとグレースに目の前の椅子をすすめた。
最初に礼が先だったと気づき、頬を染めて口を開こうとすると、彼が複数の書類をテーブルに広げた。
「これは、君の実家の借金が完済されたという証明書です」
「えっ?」
「手で持って食べられるクレープですか! なんて斬新なことを」
と、まず驚かれた。
キャロルお気に入りのキャラメルナッツはもちろん、軽食として作った野菜や油漬けの魚を巻いたクレープには絶句からの絶賛といった具合で、「クレープに不可能はないのか」と大真面目に言われた時は、笑うのをこらえるのが大変だったくらいだ。
持ち帰りできたらいいのにという呟きを耳にし、具を包んだクレープを用意すると、護衛後の土産の定番になってしまう。
カフェでも通常メニューにしてはと言われたが、正直にまだ難しいと話すと、「今のままでも特別感はありますね!」と微笑まれ、その笑顔の美しさにしばしぼーっとなってしまったのは言うまでもない。
貴族の女性が通える学校というものがない世界だ。社交界デビューしていないグレースにとって、お客様相手とはまた違う、同世代の女性と関わるのは楽しい日々だった。
そんなある日。
「今日はモリーさんを連れて外で食事をしますね」
護衛の女性たちからそう言われ、自分は? と一瞬寂しく思った日。閉店間際にオズワルドが訪れた。
「外は男性が警護してますのでご心配なく」
と女性護衛の一人が片目をつむって、皆でぞろぞろ出ていく。
何が起こったのかわからないまま、二人きりになった店内で、グレースは急に恥ずかしくなってもじもじし始めた。
こんなに長く会えなかったことは初めてで、会ったら言おうと思っていたことが全部頭から消えてしまう。
それでも平静を装いながら普段通りコーヒーを淹れていると、今日のオズワルドは雰囲気が違うことに気づいた。何が違うのだろうと、カップを置きつつさりげなく彼を一瞥し、その髪の生え際が白っぽい金色になっていることに気づく。
(あ、逆プリンになってる。地毛はあんな色だったのね)
濃い色に染めることもあるのかと特に疑問も持たず、むしろ、地の髪の色がヒヨコみたいで可愛いなどと思いきゅんとする。
コーヒーには女の子たち用に焼いていた絞り出しクッキーを添えた。
「食事はどうされますか?」
あくまで客として扱うと、オズワルドは座ってくれないかとグレースに目の前の椅子をすすめた。
最初に礼が先だったと気づき、頬を染めて口を開こうとすると、彼が複数の書類をテーブルに広げた。
「これは、君の実家の借金が完済されたという証明書です」
「えっ?」