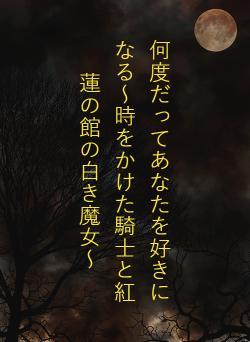一口二口と夢中で食べるピアツェに、グレースはクスっと笑った。作り方は教えているので、彼女は家でも食べてるはずなのだ。
「いやいや、笑い事じゃないよ、グレース。同じ材料を使って、教えてもらった通りに作っても、あんたほどおいしく作れる人はいないんだ。―――ああ、本当においしい。帰ってきてよかったねぇ」
「ほんとね。お義母さん、何度作ってもこれじゃない、これじゃないって言ってたものね」
満足そうなピアツェのもとに、少し呆れたような、それでいて楽しそうな表情のマロンがやってきた。小柄なマロンは大きな荷物を空いている椅子に置くと、ピアツェの手元を見て小さく喉を鳴らした。
「ああ、やっぱりおいしそう。レディ・グレース。私にもフレンチトーストを……え、もうないの?」
わくわくした声のマロンに、グレースは頭を下げた。
「すみません。それが最後だったんです」
見るからにしょんぼりしてしまったマロンに、ピアツェは「グズグズしてるからだよ」とすげない。とはいえ、そう言いながらも視線でグレースに皿とフォークを出すよう訴える。
(ピアツェさんてばツンデレさん)
笑いをこらえつつ、グレースはそれらをマロンの前に置いた。
「いやいや、笑い事じゃないよ、グレース。同じ材料を使って、教えてもらった通りに作っても、あんたほどおいしく作れる人はいないんだ。―――ああ、本当においしい。帰ってきてよかったねぇ」
「ほんとね。お義母さん、何度作ってもこれじゃない、これじゃないって言ってたものね」
満足そうなピアツェのもとに、少し呆れたような、それでいて楽しそうな表情のマロンがやってきた。小柄なマロンは大きな荷物を空いている椅子に置くと、ピアツェの手元を見て小さく喉を鳴らした。
「ああ、やっぱりおいしそう。レディ・グレース。私にもフレンチトーストを……え、もうないの?」
わくわくした声のマロンに、グレースは頭を下げた。
「すみません。それが最後だったんです」
見るからにしょんぼりしてしまったマロンに、ピアツェは「グズグズしてるからだよ」とすげない。とはいえ、そう言いながらも視線でグレースに皿とフォークを出すよう訴える。
(ピアツェさんてばツンデレさん)
笑いをこらえつつ、グレースはそれらをマロンの前に置いた。