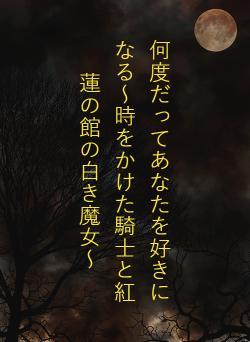矢継ぎ早に尋ねるグレースをピアツェはむぎゅっと抱きしめ、面白そうに軽やかな笑い声をあげた。
「そんなに一度に聞かれても答えられないよ、お嬢ちゃん。どれどれ、顔を見せなさい。――うんうん、今日もべっぴんさんだね。ただちょいと瘦せすぎだ。もう少し肉をつけないとね。せっかく可愛いんだからさ」
ピアツェの言葉に何人かの客が賛同するように小さく頷くが、グレースはそれに気づかず、クスクス笑いながら彼女をいつもの席に案内した。ピアツェの指定席はカウンターの右端だ。
「すまないね、グレース。本当はもう少し早く着く予定だったんだけど、マロンがグズグズしてるもんだから遅くなっちまった」
マロンは彼女の息子の嫁で、いつも製品を届けてくれる青年ミルトの母親だ。
「気にしないで。ピアツェさんならいつでも歓迎よ。あら、そういえばマロンさんは?」
「一緒に来てるよ。まだ手が離せないから、あたしだけ先にこっちに来たんだ。あとで迎えに来るよ」
「そうなのね」
足が少し不自由なピアツェは、春先に風邪をこじらせた後、療養を兼ねて南部にいる息子のもとに行っていると聞いていた。とはいえミルトいわく、「療養と言っったって、どうせ叔父さんがしっかりやってるか監視しに行ったんじゃないかな」だそうだが。
「じゃあピアツェさん。今日は朝食をとりに来られたってことでいいのかしら。それとも甘いコーヒーだけにする?」
「ふふん、なんのために急いできたと思ってるんだい。もちろんミルクたーっぷりのカフェオレとフレンチトースト! ――まだ、あるよね?」
勢いよく注文した後心配になったらしいピアツェに、グレースは大丈夫だと請け合い可愛くウィンクして見せた。
「フレンチトーストはあと一人前で終わりだったのよ。さすが、間がいいわ」