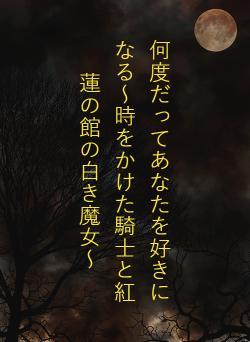借金はまだ大分残っている。頑張っても頑張っても利子が膨らむばかりで、このまま順調に返せても足りないほどに。
少し前に帰省した際、せめてあと一・二年伸ばしてくれないかと頼んだのだが、逆に「むしろ早めてもいいな」と呟かれゾッとした。いやらしい目線は以前より強くなり、十七歳になったリチャードからは「しばらく戻らないほうがいい」と言われたくらいだ。
穏やかな声のオズワルドと話していると、心のおもりが軽くなる気がする。
夜に彼を思い出すと、胸の奥がぎゅうっと痛くて泣きたくなるが、彼の姿を見たりそばにいられる時は幸福だ。
これは内緒の恋だ。辛いときを耐えられるのは、心の中にこの気持ちがあるからだとグレースは思っている。
(私の癒し。勝手に片思いをしててごめんなさい)
絶対に気付かれないよう、今日も最大限気を付ける。
少なくともあと二年、私は自由なのだから。
「美味しかったです。もう一杯コーヒーを貰えますか。今度は甘いのがいいな」
ゆっくり食事を楽しみ、気のせいか名残惜しげに注文するオズワルドに、グレースは少し考えて一杯のコーヒーを持ってきた。スプーンの上には最近流行りの角砂糖。そこに菓子用に置いているブランデーを浸した。
「少しお待ちくださいね」
店内を薄暗くすると砂糖に火をつける。青い炎が揺らめいて幻想的な雰囲気を作り出した。砂糖があらかた溶けた頃スプーンをコーヒーに入れ、くるりとかき混ぜてからオズワルドに渡す。
「特別メニューですよ。少しアルコールが残ってますけど、大丈夫ですよね?」
それは前世で父が時折出していた、カフェロワイヤルというコーヒーだ。青い炎が綺麗で、注文されるのが楽しみだった一品。
いたずらっぽく笑うグレースに、オズワルドは夢から覚めたような顔をして礼を言った。一口コーヒーを飲むと気に入ったらしく、満足そうな笑みが広がる。
「今夜は寒いから、とてもピッタリだ」
少し前に帰省した際、せめてあと一・二年伸ばしてくれないかと頼んだのだが、逆に「むしろ早めてもいいな」と呟かれゾッとした。いやらしい目線は以前より強くなり、十七歳になったリチャードからは「しばらく戻らないほうがいい」と言われたくらいだ。
穏やかな声のオズワルドと話していると、心のおもりが軽くなる気がする。
夜に彼を思い出すと、胸の奥がぎゅうっと痛くて泣きたくなるが、彼の姿を見たりそばにいられる時は幸福だ。
これは内緒の恋だ。辛いときを耐えられるのは、心の中にこの気持ちがあるからだとグレースは思っている。
(私の癒し。勝手に片思いをしててごめんなさい)
絶対に気付かれないよう、今日も最大限気を付ける。
少なくともあと二年、私は自由なのだから。
「美味しかったです。もう一杯コーヒーを貰えますか。今度は甘いのがいいな」
ゆっくり食事を楽しみ、気のせいか名残惜しげに注文するオズワルドに、グレースは少し考えて一杯のコーヒーを持ってきた。スプーンの上には最近流行りの角砂糖。そこに菓子用に置いているブランデーを浸した。
「少しお待ちくださいね」
店内を薄暗くすると砂糖に火をつける。青い炎が揺らめいて幻想的な雰囲気を作り出した。砂糖があらかた溶けた頃スプーンをコーヒーに入れ、くるりとかき混ぜてからオズワルドに渡す。
「特別メニューですよ。少しアルコールが残ってますけど、大丈夫ですよね?」
それは前世で父が時折出していた、カフェロワイヤルというコーヒーだ。青い炎が綺麗で、注文されるのが楽しみだった一品。
いたずらっぽく笑うグレースに、オズワルドは夢から覚めたような顔をして礼を言った。一口コーヒーを飲むと気に入ったらしく、満足そうな笑みが広がる。
「今夜は寒いから、とてもピッタリだ」