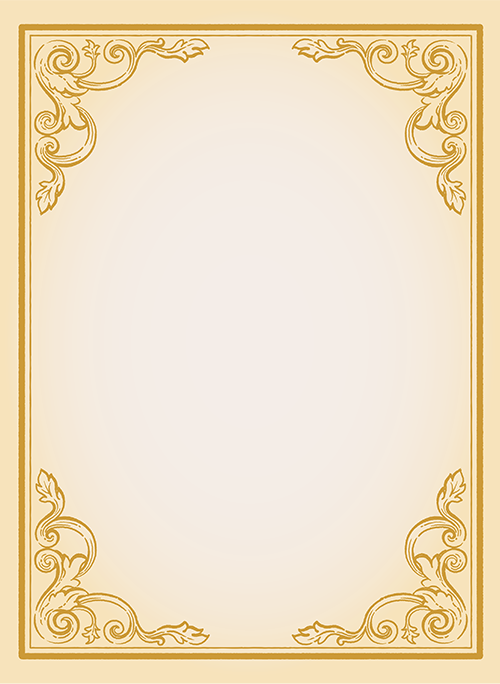必死で走り続けた。
どこをどう通って、ここに辿りついたのかわからない。気づいたら会社近くの小さな公園にいた。
目の前に一本の藤の木があって、紫色の花びらを風に揺らせているのが見えた。
はあ、はあ、と乱れた呼気が耳に響く。
呼吸がままならなくて、胸が痛い。
ヤツの言葉が耳にこだましている。
ずっとヤツに抱いていた気持ちは〝愛〟だと思っていた。
私は半分血の繋がった人を好きになってしまったって思ってた。
許されないことなのに。
目の前が滲む。紫色が霞んでくる。
おばあちゃん、どうしよう。私、どうしたらいいの?
藤の近くにあるベンチに歩み寄って腰を下ろした。
ぼんやりと眺める。
――うわぁ、すご~い!
突然、脳裏に子どもの声が響いた。
――ホント、綺麗だねぇ。
これは……おばあちゃんの声だ。
ああ、懐かしい。
ここはどこ?
満開の藤の大樹。世界を紫色に染めている。
――おばーちゃん、お空がむらさき色してるねー!
――そうだねぇ。
おばあちゃんが優しく微笑みながら私の手を引く。
あの時のこと……
――キラキラしてるー。
――紗英ちゃんのお顔もキラキラしてるわよ。
――ほんと? お花といっしょ?
――ほんとよ。お花と一緒。だからずっと紗英ちゃん、キラキラしててね。
――うん!
――天国のママも願ってるから。紗英ちゃんがいつまでもお花のようにキラキラ笑っていること。ずっと、ずっと思ってるから。
――ママも?
――ママも。
――ずっと?
――ずっと
――おばーちゃんも?
――おばーちゃんも。
キラキラと、いつまでも笑っていて。
花のように。
この藤の花のようにキラキラと。
ふと、意識のピントが合って、目を瞬く。
藤の花が風に揺れている。
揺れている。
――紗英ちゃんがいつまでもお花のようにキラキラ笑っていること。ずっと、ずっと思ってるから。
ああ、泣きそう。
泣きそう。
私はこの言葉に支えられてきた。
この言葉に自分を賭けてきた。
求めているのは、これだ。
視界が滲むと、別の顔が浮かんできた。
――俺が忘れさせてやる。
これは、榛原君?
――俺が忘れさせてやる。
あの夜、熱かった。
なにもかもが。
榛原君、ホントに忘れさせてくれるの?
この苦しさから救ってくれるの?
誰にも頼らないって決めて、強情ばっかりだったこんな私から、なにもかも忘れさせてくれる?
新しい世界を上塗りしてくれる?
頼っていいの?
そう思ったら居ても立っても居られなくなって、榛原君の携帯番号をタップしていた。
どこをどう通って、ここに辿りついたのかわからない。気づいたら会社近くの小さな公園にいた。
目の前に一本の藤の木があって、紫色の花びらを風に揺らせているのが見えた。
はあ、はあ、と乱れた呼気が耳に響く。
呼吸がままならなくて、胸が痛い。
ヤツの言葉が耳にこだましている。
ずっとヤツに抱いていた気持ちは〝愛〟だと思っていた。
私は半分血の繋がった人を好きになってしまったって思ってた。
許されないことなのに。
目の前が滲む。紫色が霞んでくる。
おばあちゃん、どうしよう。私、どうしたらいいの?
藤の近くにあるベンチに歩み寄って腰を下ろした。
ぼんやりと眺める。
――うわぁ、すご~い!
突然、脳裏に子どもの声が響いた。
――ホント、綺麗だねぇ。
これは……おばあちゃんの声だ。
ああ、懐かしい。
ここはどこ?
満開の藤の大樹。世界を紫色に染めている。
――おばーちゃん、お空がむらさき色してるねー!
――そうだねぇ。
おばあちゃんが優しく微笑みながら私の手を引く。
あの時のこと……
――キラキラしてるー。
――紗英ちゃんのお顔もキラキラしてるわよ。
――ほんと? お花といっしょ?
――ほんとよ。お花と一緒。だからずっと紗英ちゃん、キラキラしててね。
――うん!
――天国のママも願ってるから。紗英ちゃんがいつまでもお花のようにキラキラ笑っていること。ずっと、ずっと思ってるから。
――ママも?
――ママも。
――ずっと?
――ずっと
――おばーちゃんも?
――おばーちゃんも。
キラキラと、いつまでも笑っていて。
花のように。
この藤の花のようにキラキラと。
ふと、意識のピントが合って、目を瞬く。
藤の花が風に揺れている。
揺れている。
――紗英ちゃんがいつまでもお花のようにキラキラ笑っていること。ずっと、ずっと思ってるから。
ああ、泣きそう。
泣きそう。
私はこの言葉に支えられてきた。
この言葉に自分を賭けてきた。
求めているのは、これだ。
視界が滲むと、別の顔が浮かんできた。
――俺が忘れさせてやる。
これは、榛原君?
――俺が忘れさせてやる。
あの夜、熱かった。
なにもかもが。
榛原君、ホントに忘れさせてくれるの?
この苦しさから救ってくれるの?
誰にも頼らないって決めて、強情ばっかりだったこんな私から、なにもかも忘れさせてくれる?
新しい世界を上塗りしてくれる?
頼っていいの?
そう思ったら居ても立っても居られなくなって、榛原君の携帯番号をタップしていた。