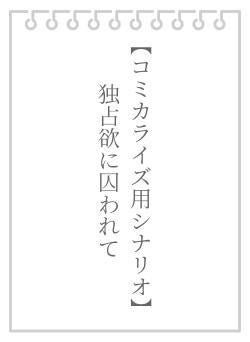仕事が終わるころには、日付が変わっていた。
「お疲れさまです、スミさん」
スタッフに軽く会釈して店を出る。
夜風が頬に触れて、ひんやりと心地よかった。
表通りのネオンはまだ明るいけれど、一歩裏に入ると、街の音が急に遠ざかる。
ヒールの音が、コツコツと静かな路地に響いた。
いつも通っている帰り道。
けれど、今日は空気が違っていた。
風が止み、耳の奥が妙に静かになる。
そのとき――
カツン。
小さな足音が、背後から聞こえた。
一度だけ。
でも、確かに。
立ち止まって振り返る。
街灯がひとつ、オレンジ色に瞬いた。
けれどそこには、誰の姿もない。
背中を冷たい汗が伝う。
イヤホンを外すと、遠くの車の音さえ聞こえない。
世界に、自分ひとりしかいないみたいだった。
「お疲れさまです、スミさん」
スタッフに軽く会釈して店を出る。
夜風が頬に触れて、ひんやりと心地よかった。
表通りのネオンはまだ明るいけれど、一歩裏に入ると、街の音が急に遠ざかる。
ヒールの音が、コツコツと静かな路地に響いた。
いつも通っている帰り道。
けれど、今日は空気が違っていた。
風が止み、耳の奥が妙に静かになる。
そのとき――
カツン。
小さな足音が、背後から聞こえた。
一度だけ。
でも、確かに。
立ち止まって振り返る。
街灯がひとつ、オレンジ色に瞬いた。
けれどそこには、誰の姿もない。
背中を冷たい汗が伝う。
イヤホンを外すと、遠くの車の音さえ聞こえない。
世界に、自分ひとりしかいないみたいだった。