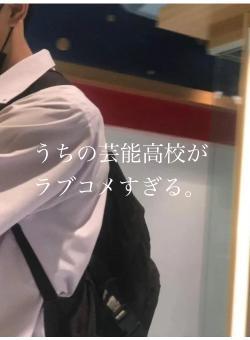「…깜짝이야(驚いた)」
機材を片付ける彼の手が徐に止まり、沈黙が流れる。
こちらをじっと見つめる彼の瞳には引き込まれるものがあって、やっぱり持って生まれた何かがあるなと思わされた。
3秒ほどの沈黙の後に、彼は口を開いた。
「そういえば日本人だったね、ミヤムラユナ。」
卒業式ぶりだ、懐かしい。と笑って言う。
在学中の3年間特別関わりがなかったとは言え元クラスメイト。さすがに覚えられていたようで一安心した。
「忘れられてたらどうしようかと思った。」
「忘れないよ。」
彼曰く記憶力には自信がある、らしい。そう言って微笑む顔が、なんだか懐かしいと思った。
「歌手になったんだね。」
ただそのままの意味で放った言葉が、彼にとって嫌味になるのではないかと思ってハッとした。
当然芸術高校に通う者の中には、その道で成功する者もいれば夢半ばに諦める者もいる。
私は、後者だった。
15歳の時、アーティストとしてデビューすることを夢見て単身で韓国に渡った。でも、夢を追うにはタイムリミットが必ずある。
高校在学中の3年の間に芽が出なければその道を諦めること。それが親から提示された条件だった。
最大手とは言わないけれど、業界ではそこそこ名の知れた事務所と練習生契約をして、名門と呼ばれる芸術高校の実用音楽科にも無事入学して、そこまでは順調だった。簡単にいかないのは、そこからだ。
デビューというのは本当に狭き門で、いくら実力がある人でも、いくら努力してる人でも、絶対にデビューできるなんてことは有り得なかった。
「結局人生運だよなー。」
日本に帰る日。
私物を全て片してすっからかんになった宿舎を見渡してそう呟いたあの日のことを思い出す。
韓国で過ごした3年間。現実を知って、この業界の理不尽さを知って、日本に帰る頃にはもう、この道に対する未練もすっかりなくなっていた。まぁ、人生そんなもんだし。
残ったのは、なんとも言えない空虚な感覚だけだった。
機材を片付ける彼の手が徐に止まり、沈黙が流れる。
こちらをじっと見つめる彼の瞳には引き込まれるものがあって、やっぱり持って生まれた何かがあるなと思わされた。
3秒ほどの沈黙の後に、彼は口を開いた。
「そういえば日本人だったね、ミヤムラユナ。」
卒業式ぶりだ、懐かしい。と笑って言う。
在学中の3年間特別関わりがなかったとは言え元クラスメイト。さすがに覚えられていたようで一安心した。
「忘れられてたらどうしようかと思った。」
「忘れないよ。」
彼曰く記憶力には自信がある、らしい。そう言って微笑む顔が、なんだか懐かしいと思った。
「歌手になったんだね。」
ただそのままの意味で放った言葉が、彼にとって嫌味になるのではないかと思ってハッとした。
当然芸術高校に通う者の中には、その道で成功する者もいれば夢半ばに諦める者もいる。
私は、後者だった。
15歳の時、アーティストとしてデビューすることを夢見て単身で韓国に渡った。でも、夢を追うにはタイムリミットが必ずある。
高校在学中の3年の間に芽が出なければその道を諦めること。それが親から提示された条件だった。
最大手とは言わないけれど、業界ではそこそこ名の知れた事務所と練習生契約をして、名門と呼ばれる芸術高校の実用音楽科にも無事入学して、そこまでは順調だった。簡単にいかないのは、そこからだ。
デビューというのは本当に狭き門で、いくら実力がある人でも、いくら努力してる人でも、絶対にデビューできるなんてことは有り得なかった。
「結局人生運だよなー。」
日本に帰る日。
私物を全て片してすっからかんになった宿舎を見渡してそう呟いたあの日のことを思い出す。
韓国で過ごした3年間。現実を知って、この業界の理不尽さを知って、日本に帰る頃にはもう、この道に対する未練もすっかりなくなっていた。まぁ、人生そんなもんだし。
残ったのは、なんとも言えない空虚な感覚だけだった。