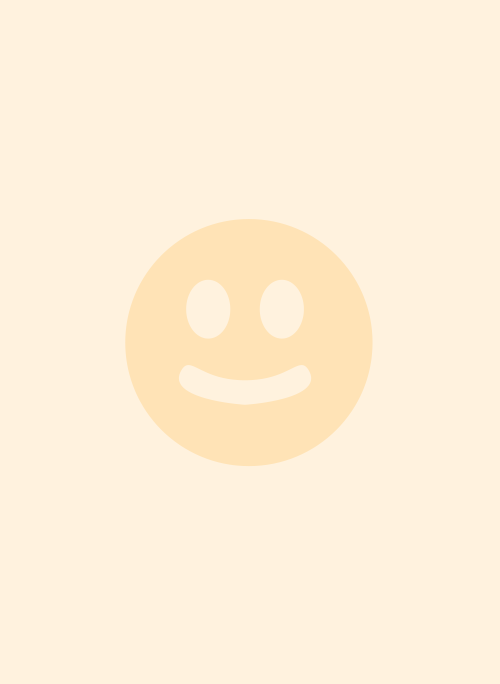答えを待ちわびる彼女。
ゆっくり腕を伸ばして、小さな身体をぐいっと引き寄せる。
「た、たたた、太一さんっ!?」
ぴっとりとくっついてしまった彼女を俺の腕の中に閉じ込めた。
ただそれだけで耳まで真っ赤になる姿は、いつみても飽きない。
俺としても恥ずかしいんだけど、それよりも彼女が愛しい気持ちが勝る。
心地好い体温と、次第に強まっていく心音。
全部…俺だけのものにしてしまいたい。
そんな汚いコトばかり考えているなんて、目の前の彼女は塵ほども気付いてないだろう。
気付かれないように振舞うのが、とにかく必死だ。
彼女の羽織っているダッフルコートと俺のコートの衣擦れの音が、また更に俺の緊張感を快感へと変えていく。
「…そうだなぁ」
例え、これから辛いことがおきても。
……俺と離れてしまっても。
きっと、君の笑顔は変わらない。
口にはできないけど、いつも思ってる。
「笑ってるとこ」
顔を見られないように腕に力を込めた。
すると、苦しそうに見上げた彼女の顔がすぐそこにある。
不思議そうに、彼女は笑ってきた。
ゆっくり腕を伸ばして、小さな身体をぐいっと引き寄せる。
「た、たたた、太一さんっ!?」
ぴっとりとくっついてしまった彼女を俺の腕の中に閉じ込めた。
ただそれだけで耳まで真っ赤になる姿は、いつみても飽きない。
俺としても恥ずかしいんだけど、それよりも彼女が愛しい気持ちが勝る。
心地好い体温と、次第に強まっていく心音。
全部…俺だけのものにしてしまいたい。
そんな汚いコトばかり考えているなんて、目の前の彼女は塵ほども気付いてないだろう。
気付かれないように振舞うのが、とにかく必死だ。
彼女の羽織っているダッフルコートと俺のコートの衣擦れの音が、また更に俺の緊張感を快感へと変えていく。
「…そうだなぁ」
例え、これから辛いことがおきても。
……俺と離れてしまっても。
きっと、君の笑顔は変わらない。
口にはできないけど、いつも思ってる。
「笑ってるとこ」
顔を見られないように腕に力を込めた。
すると、苦しそうに見上げた彼女の顔がすぐそこにある。
不思議そうに、彼女は笑ってきた。