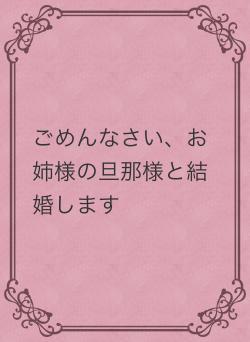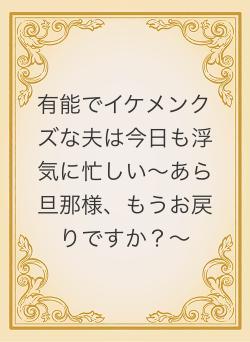街の中心部でエヴェリーナ達は馬車から降りた。
目の前には近隣の店より真新しくお洒落な外装の建物があり、リュミエールと書かれた看板が下がっている。
セドリックは迷う事なくその店の扉を開けた。
店内へ入ると外装と違わずお洒落な雰囲気で、テーブルやイスを始めとした調度品は白を基調とされデザインなども含め気品さを感じる。
ただ店内は閑散としており、来客の姿はなかった。
「いらっしゃいませ。殿下、お待ちしておりました。私はリュミエールのオーナーのイーヴォでございます。この度は、当店をお選び頂き誠に光悦でございます。準備は整っておりますので、ご案内させて頂きます」
店内を観察していると、程なくして店の奥から中年の男性が現れた。
こちらへ近付いてくると挨拶をして深々と頭を下げると、奥の個室へと案内をしてくれた。
「アルバートから貴族令嬢の間で流行っていると聞いたんだ」
席に座ると次々にお茶やスイーツが運ばれてきた。
その間、セドリックからこのカフェに来た経緯の説明を受ける。
「そうなんですね、それはまた……」
意外ですねと思わず口にしそうになり口を噤んだ。
幾ら彼が剣をこよなく愛している変わり者でも、主人の友人に対して失礼だ。
「だから今日は店を貸し切ったんだ」
何がどうして「だから」なのかは不明だが、店内に一人も客がいなかった理由は分かった。
貴族令嬢達が大勢いる中で来店するなど、彼にとっては火中に飛び込むようなものだ。
ただ店を貸し切ってまで、このカフェに来たかった理由が分からない。
(それにしても、少し多い気がします……)
お茶の準備が整うと数人の店員を部屋に残しイーヴォは下がっていった。
六人掛けのテーブルの上には、所狭しとスイーツが並べられていた。
その数はざっと数十種類。
どう考えても二人では食べきれないだろう。
お茶会や食事会などでは、見栄えなどの理由から人数分以上の量を出すのは一般的だが流石に多過ぎる。
「気に入った物があったら教えて。後で屋敷に届けさせるから」
「いえ、そこまでして頂く訳にはまいりません」
予想外の言葉に、セドリックの意図が見えず内心戸惑った。
「日頃頑張ってくれているから、特別手当みたいなものだよ」
「尚更私だけ頂く訳には」
「リズのお陰で屋敷も快適になったし、皆君に感謝している。勿論、僕もね。その為に、今日は君をここへ連れてきた」
特別手当などと言われて少し気が引ける。
ただ真っ直ぐに向けられる彼の目を見てこれが純粋な好意だという事が伝わってきた。
(私の為……)
そんな風に言われて歯痒さを覚える。
「では、有り難く頂戴させて頂きます」
小さく切り分けると取り皿に乗せる。
まるで試食をしているようだが、これだけの種類があるのだから仕方がない。
それに折角用意して貰ったのに、手を付けない皿があったら彼が落胆するかも知れないとエヴェリーナは黙々と食べる。
「リズ、チョコレートはどう? このジャムは好き? こっちのナッツやフルーツの乗ったクッキーは? スコーンはーー」
矢継ぎ早に質問をされ、思わず笑ってしまった。
「セドリック様、落ち着いて下さい。どれもとても美味しいですよ」
どれも甘過ぎず口当たりもよく食べやすい物ばかりだ。それに見た目が華やかで美しく眺めているだけでも幸福感が得られる。
令嬢達に人気がある事が頷けた。
「ごめん。でもリズが何が好きなのか知りたくて……」
「セドリック様は、どちらがお好みですか?」
「僕もどれも美味しいと思う。正直、選べない。でも、そうだな……」
真剣に悩む姿に少し眉を上げた。
「このシナモンの香りのチョコレートが好みかな。それでリズはどれが好き?」
「私は……」
無数に並んでいるスイーツを順番に眺めていく。
どれも本当に美味しい事は間違いない。ただこの中で、自分の好きな物がなにか分からない。
「そちらのオレンジピールのケーキが、いえ、イチゴのクッキー、ではなく、レモンタルト……でもなくて……ミントのチョコレートーー」
兎に角選ばなくてはと思い必死に選ぼうとするが、適当に答えるのはセドリックに失礼だと次々にスイーツの名前を口にする。だがーー
(選べない)
ただ単に好きな物を選ぶだけの事が出来ない自分に幻滅をする。きっと幼子にすら出来る筈だ。
これまでドレスや装飾品を身に付ける時は、皇子妃として他者からどう見られるかを基準に選んできた。
私物は全て必要か否かで、食事や嗜好品は出された物を又は他者に合わせた物を当たり前のように食べていた。
自分以外の事ならば、なんだって簡単に答えが出せるのにーー
ちらりとセドリックを盗み見た。
以前彼もまた分からないと答えていたが、今はちゃんと答えを出している。
(それなのに、私は……)
「そこの君、ここにある物全て毎日一種類ずつ屋敷に届けるようにイーヴォに伝えて」
「セドリック様?」
不意に控えていた店員に声を掛けてると、更に人払いをした。個室には二人だけとなる。
「ねぇ、リズ。僕が女性嫌いだって言ったからこの半月、避けていたんだろう?」
「せめて屋敷にいる時は、心穏やかに過ごして頂きたと思ったんです」
セドリックの脈略のない言動に困惑しながらも、エヴェリーナはそう答えた。
「なるほどね、君の言い分は理解した。それにしても、リズには驚かされてばかりだよ。あの夜の翌日から、僕の視界から君が消えた。確かに同じ屋敷いる筈なのに、どこにも君はいないんだ」
頭をしぼるが、彼の言わんとしている事が全く分からない。
「僕は女性嫌いだけど、平気な女性はいる。それはミラと妹だ。ミラは僕の乳母で母代わりだし、妹は腹違いではあるが血の繋がりがある。まあ妹は別の意味で苦手ではあるんだけどね」
そこまで話して一度口を噤んだ。
そして真っ直ぐにエヴェリーナの目を見つめまた口を開いた。
「そしてあと一人、君だ」
エヴェリーナは目を見張る。
「どうしてだろう。初めて会った時から、リズの事は嫌じゃない。これまで一度も嫌悪感を抱いた事はないし、寧ろ君の姿が見えなくてこの半月……寂しく思ったんだ」
セドリックの声色がとても優しく響いて、いつも気を張っている心が解れていく気がした。
「気遣ってくれるのは嬉しいよ。でも、僕は前みたいにリズが淹れてくれたお茶が飲みたいし、なんならこうやって一緒にお茶をしながら話をしたい」
「セドリック様……」
「僕はリズの事、何も知らないから知りたいんだ。好きな物が分からないなら、一緒に見つけていけばいい。だからさ、このお菓子を毎日一種類ずつ僕と一緒に食べよう」
呆然とする。
こんな風に言われたのは初めてで、こんな時どんな顔をしてなんて答えれば良いのか分からない。
「……甘い物の過剰摂取は、身体に良くありません」
「大した量じゃないから大丈夫だよ」
セドリックは、頬杖をつき至極嬉しそうに笑った。
それを見たエヴェリーナは小さく頷いた。