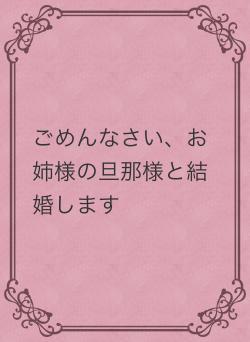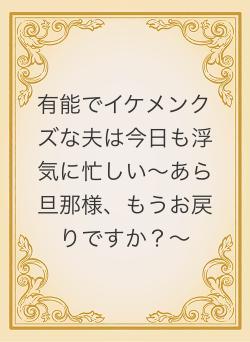ローエンシュタイン帝国ーー
「何故、報告をしなかった」
「ジュリアス殿下に確認致しましたが、必要ないとの事でしたので」
セレーナ宮殿の侍女長グレッタに問いただすと、彼女は当然のようにそう答えた。
「もういい。後は本人に直接確認をする」
彼女以外数名の使用人達に同じ質問をしたが、言い回しこそ違うが返答は同じだった。
ローエンシュタイン帝国、皇太子であるオースティン・ローエンシュタインは、この半年程西大陸の帝国に連なる国々を訪問する為に城を空けていた。戻って来たのは昨晩遅くだ。そして今朝、末の弟夫妻の様子を見に来たのだが、いつも真っ先に出迎えてくれる彼女の姿がなかった。
予定では領地視察の時期ではない筈だと、訝しげな表情を浮かべ、使用人達に問うと先程のような返答をされた。
オースティンは、廊下を靴音を鳴らし歩きながら頭を押さえる。
頭痛がしてきた。
これまでこんなに長く城を留守にした事はなかったが、高々半年だ。だがその間に、末の弟はとんでもない事をしでかしていた。
快気した弟の希望で学院に通う事は報告に上がっていたが、まさかそこで浮気をした挙句、妻であるエヴェリーナに離縁を要求し浮気相手と再婚すると宣言するとは……。更に頭が痛いのが、当然のように離縁後もエヴェリーナが宮殿に留まると弟は思っていたらしい。
幼い頃から病弱故に宮殿に引き篭もりきりで多少世間知らずだと分かっていたが、流石にここまでとは思わなかった。
『……心が、折れてしまったのだと思います』
グリエッタから事の経緯を聞かされ、弟がエヴェリーナに離縁を要求した時の様子を知った。
オースティンは、大国であるローエンシュタイン帝国の皇太子であり、それ相応の教育を受けてきた。多少の事では心乱される事はないと自負出来る。だがそれでも、グリエッタからその話を聞かされ情けなくなり、怒りに震えた。
十年、エヴェリーナは弟の為に身を削り努力してきた。弟が快気出来たのは、ひとえに彼女の努力の賜物だと感謝している。かく言うオースティン自身も彼女には随分と助けられてきた。それなのにーー
「ジュリアス‼︎」
ノックもせず扉を勢いよく開け放つと、部屋の主人である弟のジュリアスは、振り返り目を丸くする。だが、オースティンの姿を見ると直ぐに笑顔になった。
「兄上! 戻ってきたんだ! お帰り」
無邪気に笑い兄の訪問を喜ぶ姿に一瞬毒気を抜かれ、そう言えば土産があったのだと頭を過ぎるが直ぐに我に返る。
「ああ、ただいま……ではなく、それよりリナの事で」
「そうだ! 兄上、リナが帰って来ないんだ!」
オースティンの言葉を遮り、今度は泣きそうな顔でそう訴えてきた。
「帰って来ないか……。君が、そうさせたのだろう」
まるでエヴェリーナが自ら進んで出て行ったような口ぶりにため息が出る。
「僕、リナに出ていけなんて言ってないよ」
粗方話は聞いているが、一応本人からも確認の為にも弟の言い分を聞く事にした。
「ーーなるほど。君が浮気をしたからリナは出て行ったという事だね」
簡単に纏めたが、実際はそんな単純な話ではない。
だが弟は悪びれる事もなく、先程使用人達から聞いた話と同じ説明をした。
悪いと思っていないので、取り繕う事すらしないのが更に呆れる。
「浮気?」
「そうだよ。ジュリアスはリナと夫婦なんだ。本来、他の女性に気を向けてはいけないんだ。リナと離縁して、メリンダ嬢と結婚したいということは、リナのことは好きじゃなくなったのかい?」
「違うよ。確かにメリンダの事は好きだけど、一番はリナに決まってる」
「なら何故……」
「メリンダが、どうしても僕と結婚したいって言うんだ。結婚出来ないなら、もう友達もやめるって。メリンダは生まれて初めて出来た友達だし、それは嫌だなって。でも僕はリナと結婚してるから、どうしたらいいか困ってたら、メリンダがリナなら離縁しても僕のそばにいてくれる筈だって言って。その時にそう言えば昔、リナがずっとそばにいてくれるって言っていたことを思い出したんだ。だからそれなら三人で仲良く暮らせるし、いいかなって」
「いい訳ないだろう!」
「っ⁉︎」
「す、すまない、驚かせてしまったね」
意味の分からない言い分に思わず声を荒げてしまった。
ジュリアスは余程驚いたのか目を見開き固まっている。これまで怒った事など一度もなかったので、当然だろう。
「……ねぇ、兄上。リナ、帰って来るよね?」
肩を落とし、オースティンの様子を窺うように上目遣いでみてくる。
「そんなに心配なら、何故直ぐに探さなかったんだ」
「いつもみたいに直ぐに帰ってくるって思ったんだ。だって、リナが僕を置いてどこかに行っちゃうなんてあり得ないから」
恐らく領地視察に行っている時の話をしているのだろう。彼女は半年に一度、領地へと赴き一ヶ月程宮殿を空けていた。だがその時とは全く状況が違う事をジュリアスは理解していなかったみたいだ。
それにしても一体どこからその自信が湧いてくるのか、呆れるしかない。
「彼女の事は探し出す」
「本当に? 良かった!」
「だがそれは君の元に連れ戻す訳ではない」
「え……」
「ジュリアス、世の中には取り返しのつかない事がある。君は自らリナを手放した。彼女が君の元に戻る事はもうない」
「それって、もうリナと一緒に暮らせないって事?」
「……ああ、そうだ」
「い、嫌だ‼︎ リナがいなくなるなんて、そんなの嫌だ‼︎」
「ジュリアス、なにを……」
喚くジュリアスは思い出したように棚に駆け寄った。そして引き出しから離縁書を取り出すと、それを勢いよく破り捨てた。
「嫌だ! リナが帰って来ないなら、僕、離縁なんてしない! メリンダとも結婚しないし、友達もやめる‼︎ だから兄上、お願い、リナを僕に返して‼︎ 僕、リナがいないと生きていけないっ」
床に座り込み幼子のように泣き喚く弟を見たオースティンは、どこで間違えたのかと呆然と立ち尽くした。