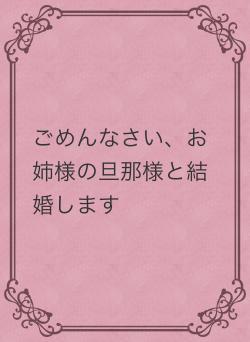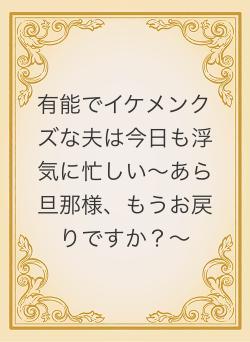正式に雇用が決まり、半月が過ぎた。
住み込みで三食付きなので、何不自由することもなく安心して暮らせている。
セドリックが何者かは分からないが、これだけの屋敷を所有出来る財力がある貴族という事は、上級貴族なのかも知れない。
それなのにも拘らず、得体の知らないエヴェリーナを簡単に雇い入れてくれた。寛大なのかはたまたマイラの影響力なのかは分からない。
気になるが、聞いていいものか悩む。
使用人達は皆彼を名前に敬称を付けて呼んでおり爵位は不明だ。まあ知った所でリズは一介の使用人に過ぎないので、特別何かある訳でもないのだが。
エヴェリーナは休憩時間に、外の空気を吸おうと庭に出た。暫く歩いていると、後ろから声を掛けられる。
「ーーこの辺りに新しく花を植えてみようと思うんですが、どんな花がいいものかと悩んでいまして」
長い髭が特徴的の初老の男性は庭師のフランだ。こうやって度々雑談をする事がある。
「ガザニアとかはどうですか? 日当たりも良いですし、光沢のある花弁は日の光に照らされるとキラキラとして綺麗ですよ」
「それは良い。次の仕入れの時に探してみます」
始めは掃除全般を任せられていたが、エントランスが殺風景だったので世間話程度にソロモンに少しだけ提案をしてみた。
厚かましいとは思ったが、エントランスは屋敷の顔と言っても過言ではない。気になってしまった。
来訪があった際に、一番初めに目にする場所である故に、エントランスで印象が大分変わってしまう。
貴族の来訪者は様々で、友人知人以外にも取引相手や仕立て屋や宝石商などといった業者も少なくない。言い方は悪いが、侮られない為にも少し華美くらいでいいと思っている。
そんなエヴェリーナの考えを知ってか知らずか、ソロモンやミラは「なら、いっその事模様替えしちゃいましょう」と言い出した。
それからは、いつの間にか屋敷中模様替えする話になっていて、その全てをエヴェリーナにと頼まれてしまった。
更にたまたま庭師と話す機会があり、いつの間にか相談をされるようになり、お茶の話をすれば執事達に淹れ方を教えたりもするようになった。
流石に出しゃばり過ぎかも知れないと不安になるが、ソロモンやミラにお礼を言われると期待に応えなくてはとつい余計な世話を焼いてしまう。
「リズさん、今ちょっと手が離せなくて、セドリック様にお茶持って行って貰ってもいいですか?」
そんなある日、屋敷に来訪があった。
どうやらセドリックの友人らしい。
ジルやソロモンなど皆それぞれ作業をしており、丁度手の空いたエヴェリーナがお茶出しを頼まれた。
「はい、承知致しました」
実はセドリックにお茶を淹れるのはこれで何度目かになる。
初めて淹れる時にセドリックの好みが分からないので、家令であるジルにセドリックの好みを聞いてみたのだが「セドリック様は拘りのない方なので、リズさんの好きな物を淹れてあげて下さい」と言われてしまった。
もしかして何かの試験なのかと思ったが、毎回違うお茶を淹れても彼はただ普通にお礼を言ってくれるだけだ。
「今日は、これにしましょう」
お茶に乾燥したベルガモットを入れて、香りをつけたら取り出して少量の蜂蜜をいれる。
客人の好みは分からないが、何となくセドリックは香り高い方が好きなように思えたのでこれにした。
「ああ、そうだ! 今磨いている彼女は、クリスティーヌっていうんだ」
セドリックの友人のアルバートは気さくで良い人そうだが、とても変わった人だった。
普通に自己紹介を終えたと思った矢先、手元の剣を彼女と表しクリスティーヌだと紹介した。
エヴェリーナは衝撃を受ける。
これまで様々な経験をしてきたが、剣を紹介されたのは初めてだ。どう反応すればいいのか困惑する。
彼は主人であるセドリックの友人だ。絶対に無礼があってはならないと、頭をしぼった。
「リズ、お茶が一人分多いよ」
お茶を出し終わり退室しようとするが、セドリックから声を掛けられる。
「そちら、クリスティーヌ様のものです」
考えに考えた結果、主人の友人の大切な方(?)故、同様にもてなす事にした。
だがエヴェリーナの返答にセドリックは呆気に取られた様子に見える。間違えてしまったかも知れないと不安になるが、次の瞬間アルバートが歓喜の声を上げた。
「リズ嬢、君はなんて素晴らしい人だ! こんな気遣いを受けたのは生まれて初めてだ!」
「だろうね……」
呆れ顔のセドリックを尻目に余りに喜ぶアルバートを見て、笑いそうになりつつエヴェリーナは部屋を後にした。