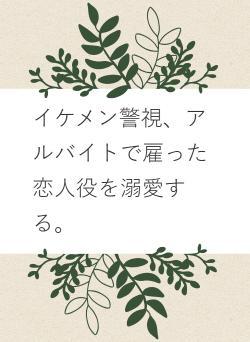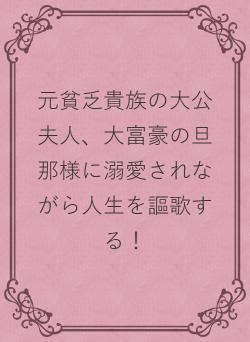心臓が止まるかと思った。
目の前に、グーグー間抜け面でガチ寝している朝陽の顔があった。視線を動かすと、見覚えのある壁と天井が視界に入る。自分の部屋だ。
服は、乱れてない、大丈夫。……いやいやいや、大丈夫じゃないって。何で二人でベッドに入ってるのよ。おかしいでしょ。
とりあえず出よう、と思い身をよじったけれど……抱きしめられていたらしい。全然抜けず、むしろ強くなってきた。
「寒……」
「……おい、起きてんならさっさとどけ」
「ガチで寒いからそのままでいて」
「知るかっ! 私は湯たんぽか!」
自分を湯たんぽ扱いされた事を怒っているわけじゃない。抱きしめられて速く脈打つ心臓の音が聞こえてしまうのではと焦っている。こんなに近かったら、聞かれているかもしれない。
「お前今日仕事だろ」
「……今何時?」
指差した先にある時計を見た朝陽は……飛び起きた。そりゃそうだ、さっさと帰って仕事の準備しないといけないんだから。ざまぁみろ。
洗面台貸して。その言葉に生返事をしつつもタオルを貸したけれど、内心ホッとしていた。けれど、大きな心臓の音が中々収まらない。
一緒に一つの布団で寝るなんて、昔は何回もあったはずだ。だから、別におかしなことではない。そう、おかしなことでは、ない。今更何をそんなに驚いているんだ、自分は。
ふと見ると、ローテーブルの上が綺麗になっていた。確か昨日は、朝陽が作ってくれた夕飯と一緒にお酒を楽しんだはずだ。それからは……寝た?
そんなに飲んでいたわけじゃない、気がするんだけど……と、昨日の記憶を呼び起こしていると洗面所に行っていた朝陽が戻ってきた。