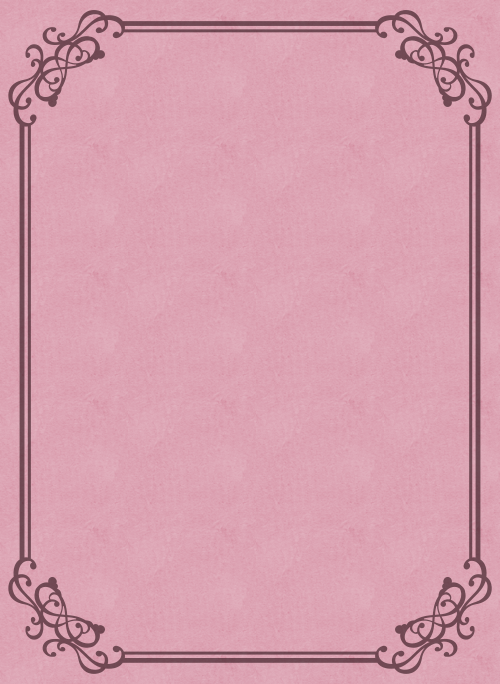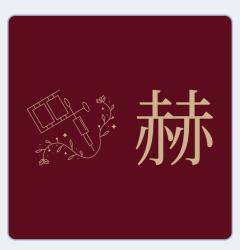静かな町の片隅に、古びた診療所があった。白い壁に蔦が絡まり、窓辺には色とりどりの花が咲くその場所は、まるで童話の中から抜け出したようだった。そこに住むのは、医師免許を目指して日夜勉強に励むルクルーゼ、20歳の快活な女の子だ。彼女は赤い髪をポニーテールに結び、いつも白衣のポケットに聴診器を忍ばせていた。ルクルーゼのモットーは「どんな困難も力でねじ伏せる!」――その逞しい性格は、どんな患者にも希望を与えた。
ある日、診療所のドアをそっと叩く音がした。ルクルーゼがドアを開けると、そこには青白い顔をした少女が立っていた。彼女の名前はルル。ふわふわの白いドレスに身を包み、手にはピンクのわたあめを握りしめていた。だが、その目は怯えで揺れ、まるで嵐の前の海のようだった。
「ルル! 久しぶり! どうしたの? また風邪?」 ルクルーゼは笑顔で迎え入れたが、ルルの震える声がそれを遮った。 「違うの…ルクルーゼ、私…恋愛が怖いんだ」
ルクルーゼは目を丸くした。恋愛恐怖症――それはルルが抱える、誰にも言えない秘密だった。ルルは恋愛の話を聞くだけで心臓がバクバクし、手汗をかき、時には気を失いそうになるほどだった。彼女は言った。 「好きな人ができても、近づくのが怖い…。告白なんて考えただけで、頭が真っ白になるの。わたあめを食べても、怖さが消えない……」
ルクルーゼは腕を組んで考え込んだ。彼女の頭脳は、医学書と同じくらい鋭く回転し始めた。 「ふむふむ、これは心の病気だね! ルル、安心して。私、ルクルーゼが絶対に治してあげるよ!」 彼女は力強く拳を握り、ルルの肩をポンと叩いた。その勢いに、ルルは少しよろめいたが、なぜか少し安心した。
ある日、診療所のドアをそっと叩く音がした。ルクルーゼがドアを開けると、そこには青白い顔をした少女が立っていた。彼女の名前はルル。ふわふわの白いドレスに身を包み、手にはピンクのわたあめを握りしめていた。だが、その目は怯えで揺れ、まるで嵐の前の海のようだった。
「ルル! 久しぶり! どうしたの? また風邪?」 ルクルーゼは笑顔で迎え入れたが、ルルの震える声がそれを遮った。 「違うの…ルクルーゼ、私…恋愛が怖いんだ」
ルクルーゼは目を丸くした。恋愛恐怖症――それはルルが抱える、誰にも言えない秘密だった。ルルは恋愛の話を聞くだけで心臓がバクバクし、手汗をかき、時には気を失いそうになるほどだった。彼女は言った。 「好きな人ができても、近づくのが怖い…。告白なんて考えただけで、頭が真っ白になるの。わたあめを食べても、怖さが消えない……」
ルクルーゼは腕を組んで考え込んだ。彼女の頭脳は、医学書と同じくらい鋭く回転し始めた。 「ふむふむ、これは心の病気だね! ルル、安心して。私、ルクルーゼが絶対に治してあげるよ!」 彼女は力強く拳を握り、ルルの肩をポンと叩いた。その勢いに、ルルは少しよろめいたが、なぜか少し安心した。