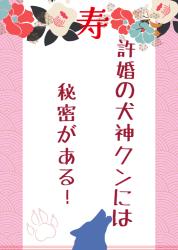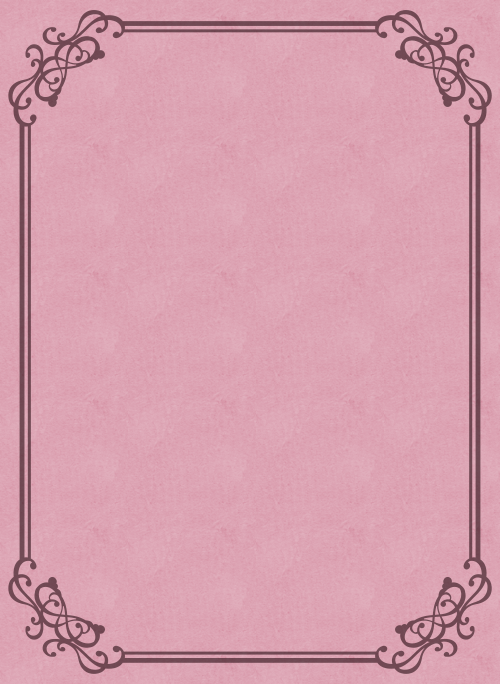「異動になるから、心細いみたいで。私が色々面倒見てきたから」
「それ理由になってない」
「怒ってるんですか?」
「怒ってる・・・って言ったらあきれる?」
「質問を質問で返すなんて一ノ瀬さんらしくはないですよ。それに湊君は彼女いるから、あのハグに恋愛的要素はないです」
「それでも見てて嫌なんだよ。如月さんは俺の彼女なのに」
俺の彼女――いや、喜んでいる場合ではない。この状況は不味い。誰かに見られ黒川部長の耳に入ったりでもしたら。
「ようやく触れられる関係になったけど、如月さんは隙だらけだから心配。・・・こんなに独占欲強いって自分でも知らなかった」
そう頭では理解していたはずなのに、一ノ瀬さんの哀愁漂う声と吐息が耳元に触れたせいで、身体がビクッと震えた。
「わ、私が好きなのは一ノ瀬さんだけです」
「無自覚って怖いな。こっち向いて、莉子」
名前を呼ばれ不意を突かれると、一ノ瀬さんの腕の中で身体の向きが変わった。その時、資料庫の前を他の社員が通りかかった。息を殺すように密着する身体を小さくした。腰に手が回り、空いた手で顎を固定された。ゆっくりとなぞられていく唇に、思わず一ノ瀬さんのシャツを握りしめていた。
「キスしていい?」
「ここ、職場ですよ?」
「知ってるよ。そんなこと・・・。でも、もう我慢の限界」
一ノ瀬さんの唇が私の唇と重なった。一度だけ軽く触れた。私の様子を伺うと、少しだけ口角を上げてまたキスを繰り返した。深くなっていくキスに抗えない。
惚れた弱みとか、好きになった方の負けとかよく言うけれど、私の場は合完璧なる敗者だ。一ノ瀬さんに溺れていく。
「いっいちのせ・・・さん。これ以上は――」
「あ、ごめん。つい夢中で」
こつん、と一ノ瀬さんのお凸が額に触れた。その至近距離に、整った顔を改めて思い知らされる。本当に慣れてるな、この人は。
「ねぇ今度の土曜日どこか行かない?」
「土曜日・・・?あっその日は予定が」
「予定って?」
「高坂さんとポップアップへ行くんです」
「・・・あのさぁ」
しまった・・・さすがに、このタイミングでは不味かった。腰を強く引き寄せられ、隙間がないほどに身体が密着した。のぼせていく中で、一ノ瀬さんを落ち着かせる言葉を探した。そうだ!閃いたと同時に顔を向けた。
「一ノ瀬さん!私とデートをしましょう!」
□□□
初デートは映画か、テーマパークか、日帰り旅行かと相場は決まっている。好きな人と時間を共有するのだから、素敵な場所をチョイスしたい。だから私は猛反している。こんな所に、一ノ瀬さんを連れて来て良かったのかと。
「あの、本当にここで良かったんでしょうか?」
「莉子が来たかったんだから構わないよ」
「でもこれでは、あまりにも私の趣味に偏り過ぎて・・・」
二人でやって来たのは『行け!おもち大魔神!最後の戦い~』のポップアップショップ。デートに誘ったら、逆に行きたい場所を聞かれて即答してしまった。一ノ瀬さんの優しい。
「わぁ!かわいい!一ノ瀬さん見て下さい!これがおもち大魔神です」
「本当だ。感触すご、手が埋もれてく」
大きくモチモチのおもち大魔神のクッションに一ノ瀬さんの手が埋もれていく。あれ、なんだろう一ノ瀬さんが言うと卑猥に聞こえるな。手つきとか・・・って何考えてるんだ私!こんな神聖な場所でそんなこと、そんなことをっ!!
「ねぇこっちはパンダの被り物してるよ」
「それは多分このショップの限定で」
「へぇ、このサイズならつけやすそうだな。一緒に買ってく?」
「お揃いってこと?」
「うん。車の鍵に付けるの探してたんだよね」
「じゃ、じゃ私も家の鍵に付ける」
「ふ~ん。それなら俺も家の鍵にするか。どっちの色がいい?」
一ノ瀬さんが両手に持ったおもち大魔神を私に見せた。一瞬、時間が止まった錯覚に陥る。隣にいた、子供の笑い声が耳の奥で木霊していた。
「一ノ瀬さんがかっこよすぎてフリーズしてました」
「えっ今!?どこで?嬉しいけど・・・よくわかんないな」
「好きな人が自分の好きな物を持ってるのって尊い」
「そういうもんなのかな・・・とりあえずこれ買ってくるよ」
色を決めて一ノ瀬さんがレジに並ぼうとした時だった。
「あれ?一ノ瀬君?」
店の周りには、大勢の人が列を作っていて、賑やかなオープニング曲も流れている。そんな中で一ノ瀬さんを呼び止める声がはっきりと聞こえた。
「やっぱり!驚いた。どうしたのこんな所で?」
「福田さんこそどうしたんですか」
外の通路に福田さんの姿があった。一ノ瀬さんは福田さんの姿に、商品を持ったまま出て行こうとする。
「あの、一ノ瀬さん。私会計行って来ます」
「あっごめん。そうだった」
「何この店?すごい込み具合だけど」
「彼女がハマってるらしくて」
「彼女?」
一ノ瀬さんから商品を受け取ると、刺すような視線が福田さんから向けらえた。会釈だけをして私はレジへと向かった。後ろから聞こえてくる一ノ瀬さんと福田さんの会話。彼女って言って大丈夫だろうか。一抹の不安が、あっという間に広がり黒い靄になっていく。自分がそうなっていたことに戸惑いを隠せなかった。さっきまであんなに楽しかったのに・・・。
しばらくして戻って来た一ノ瀬さんに、明るく作った声がわざとらしくなってしまった。それでも、続けて必要以上に笑っていたのは、一ノ瀬さんに気づかれるのが恐かった。
お揃いにしようと言って買った、おもち大魔神のキーホルダーも結局、私が二つとも持ち帰った。
□□□
数週間前までは春の風がまだ冷たく感じたのに、すぐそこまで夏が迫ってきている。外回りを終えてオフィスに戻って来ると、冷房が身体を冷やしてくれた。立ち寄ったコンビニで飲料水を買い、エレベーターに乗り込んだタイミングで乾いた喉を潤した。
「あら?お疲れ様」
声をかけてきたのは福田さんだった。こんな時思う。例えば電車を一本早めたら、取引先のご厚意のタクシーを使わずに歩いていたら、コンビニに寄らなければ、ここで会うことはなかったのにと。
「お疲れ様です」と軽く頭を下げると、ハイヒールで高くなった視界から私を見下ろした。無言の中で早く七階に着けと叫んだ。じんわりと汗ばんだ背中に汗が流れていく。さっき潤したばかりの喉がまた乾き出しそうだ。
「如月さんだっけ?一ノ瀬君と付き合ってるんだって?」
「・・・えっと、」
返答に迷ってしまった。社内恋愛禁止は今もグレーゾーン。黒川部長に知られれば面倒なことになる。でも一ノ瀬さんは、福田さんに彼女だって紹介してくれていた・・・。
「はい。まぁ、そうですね」
「ふっ意外ね。一ノ瀬君がこういう感じタイプだったなんて。たまには変わった人とお付き合いしてみたかったのかしら」
「・・・まぁ、そうですね」
つい同じ返答をしてしまった。嫌味を嫌味とわかってて言ってくる人に対して、大人になって対処法を心得ていたはずだったのに。一ノ瀬さんの話をされると、感情が大きく揺さぶられる。いつもは高野豆腐のように硬く頑丈な心が、あっという間におぼろ豆腐みたいになる。
「一ノ瀬さんモテるから不安でしょう」
「別に不安じゃありません」
「あらそう。意外とタフなのね。でも・・・」
悔しくて言い返したはいいが・・・。なんと、弱い反撃だろう。エレベーターが六階に着きドアが開く。廊下で話している社員の雑談や人の気配が伝わって来た。福田さんが降りる間際に私に釘を刺した。
「あまり本気にならない方がいいわよ。・・・一ノ瀬君とは私も昔色々あったから。部署が一緒だと出張とかもよく被るの」
厚く塗られたファンデーションがひび割れそうなほど、ニッコリと作った笑顔を見せてきた。出て行く際に、香った煙草の香りに咽そうになった。こんなわかりやすい揺さぶりをする人が、今の時代にもいるのか。しかもこんな身近に・・・。
「福田さん」
「何?」
「本気になるのは仕方ないです。私が好きなんだから。・・・失礼します」
一ノ瀬さんがモテるのは、今に始まったことじゃない。そんなの最初から知っていた。知っていて付き合った。はずなのに――私は閉のボタンを押し続けた。
「ちょっと、待って!!」
ガタンッと鈍い鉄の音がしたと思ったら、閉まりかけたドアに一ノ瀬さんが肩をねじ込ませていた。緊急を察知しドアが開く。余りの衝撃に驚いて声が出ない。一ノ瀬さんは乗り込んでくると、屋上のボタンを押した。ドアが閉まると両肩に強い力が加わった。
「大丈夫?なんか言われてなかった!?」
「・・・えっ?」
「福田さんと話してたでしょ?嫌なこと言われたかと・・・暗い顔してるし」
必死になって追いかけてきてくれた一ノ瀬さんの姿に言葉がつまった。
「はぁ・・・あの人、女性社員にライバル意識強くて。だから、如月さんも嫌味を言われてんじゃないかって心配で・・・」
心細くなって寂しくて不安で、そういった感情が一気に打ち寄せてくる。今までそういった感情を一人にの人物に対して、同時に抱いたことなんてない。こんなことくらいで、動揺して。
――抱きしめて欲しいなんて言ったら、面倒がられてしまうだろうか。
「・・・大丈夫です。何も言われてませんから」
「本当?こないだも福田さんとショップで会った時、様子がおかしくなかった?俺の気のせいならいいけど」
「一ノ瀬さんは人気だから。一々気にしてたらキリがないと心得ています」
「あのさ・・・俺、前にも話したけど好きな子にしか、莉子以外には興味ないって。告白されても振ってる。俺がこんなに好きなのがまだわからない?」
わからないのは私が変わり者だからだろうか。
お願いだから、今すぐ抱きしめて好きだと言って欲しい。そう思っているのに、平然を装うために出た言葉は全く違うものだった。
「す、すごい。それはモテ王の武勇伝」
「・・・何、その言い方」
あっ、しまった・・・。私今、変な言い方した?
スッと肩から手を離した一ノ瀬さんが私に背を向けた。・・・きっと気に障ることを言ってしまったんだ。訂正しないと。でも、どこが?どこからが変だった?
「やっと付き合えたと思ったのに、俺ばかり好きみたいで。嫌になる」
冷たさを含んだ声に、心が震えてた。
「どうして・・・嫌になるの?」
私だって、こんなに好きなのに。・・・けれど一ノ瀬さんからの返事はなかった。手を伸ばせば届く距離にいるのに、その背中が遠く感じる。
さっきまで出ていた太陽も分厚い雲に隠れ、どんよりとした空模様に変わっている。エレベータ―に滞留する空気が重すぎて息苦しかった。
□□□
翌日、電車で一ノ瀬さんに会えるかと淡い期待をしたけど、そんなに都合よくはいかなかった。朝はミーティングや会議が入るから会えない方が普通だ。酸欠状態の満員電車に、押し詰められため息が零れた。
「如月さん。コンペの企画書まだだけど、今回は見送る?」
「すみません・・・今考えてて。来週中には必ず提出します」
「それ以上は待てないからね」
一つのことが上手くいかないと、芋づる式のようにあれもこれもと、手が付けられなくなっていく。パソコンを開け仕事に向かうけど、調子が上がらない。
「どうしたの莉子。疲れてない?クマやばいよ」
「慣れないことをしてるせいかな」
「一ノ瀬君のこと?」
「・・・ううん。多分、私のせい」
昨日から続いている曇り空は、雨を溜め込んだまま、濃さを増していた。今日は雨降る予報だったから折り畳み傘をカバンに入れてきたけど、夢乃の言う通り疲れているから早めに帰ろう。
「それ理由になってない」
「怒ってるんですか?」
「怒ってる・・・って言ったらあきれる?」
「質問を質問で返すなんて一ノ瀬さんらしくはないですよ。それに湊君は彼女いるから、あのハグに恋愛的要素はないです」
「それでも見てて嫌なんだよ。如月さんは俺の彼女なのに」
俺の彼女――いや、喜んでいる場合ではない。この状況は不味い。誰かに見られ黒川部長の耳に入ったりでもしたら。
「ようやく触れられる関係になったけど、如月さんは隙だらけだから心配。・・・こんなに独占欲強いって自分でも知らなかった」
そう頭では理解していたはずなのに、一ノ瀬さんの哀愁漂う声と吐息が耳元に触れたせいで、身体がビクッと震えた。
「わ、私が好きなのは一ノ瀬さんだけです」
「無自覚って怖いな。こっち向いて、莉子」
名前を呼ばれ不意を突かれると、一ノ瀬さんの腕の中で身体の向きが変わった。その時、資料庫の前を他の社員が通りかかった。息を殺すように密着する身体を小さくした。腰に手が回り、空いた手で顎を固定された。ゆっくりとなぞられていく唇に、思わず一ノ瀬さんのシャツを握りしめていた。
「キスしていい?」
「ここ、職場ですよ?」
「知ってるよ。そんなこと・・・。でも、もう我慢の限界」
一ノ瀬さんの唇が私の唇と重なった。一度だけ軽く触れた。私の様子を伺うと、少しだけ口角を上げてまたキスを繰り返した。深くなっていくキスに抗えない。
惚れた弱みとか、好きになった方の負けとかよく言うけれど、私の場は合完璧なる敗者だ。一ノ瀬さんに溺れていく。
「いっいちのせ・・・さん。これ以上は――」
「あ、ごめん。つい夢中で」
こつん、と一ノ瀬さんのお凸が額に触れた。その至近距離に、整った顔を改めて思い知らされる。本当に慣れてるな、この人は。
「ねぇ今度の土曜日どこか行かない?」
「土曜日・・・?あっその日は予定が」
「予定って?」
「高坂さんとポップアップへ行くんです」
「・・・あのさぁ」
しまった・・・さすがに、このタイミングでは不味かった。腰を強く引き寄せられ、隙間がないほどに身体が密着した。のぼせていく中で、一ノ瀬さんを落ち着かせる言葉を探した。そうだ!閃いたと同時に顔を向けた。
「一ノ瀬さん!私とデートをしましょう!」
□□□
初デートは映画か、テーマパークか、日帰り旅行かと相場は決まっている。好きな人と時間を共有するのだから、素敵な場所をチョイスしたい。だから私は猛反している。こんな所に、一ノ瀬さんを連れて来て良かったのかと。
「あの、本当にここで良かったんでしょうか?」
「莉子が来たかったんだから構わないよ」
「でもこれでは、あまりにも私の趣味に偏り過ぎて・・・」
二人でやって来たのは『行け!おもち大魔神!最後の戦い~』のポップアップショップ。デートに誘ったら、逆に行きたい場所を聞かれて即答してしまった。一ノ瀬さんの優しい。
「わぁ!かわいい!一ノ瀬さん見て下さい!これがおもち大魔神です」
「本当だ。感触すご、手が埋もれてく」
大きくモチモチのおもち大魔神のクッションに一ノ瀬さんの手が埋もれていく。あれ、なんだろう一ノ瀬さんが言うと卑猥に聞こえるな。手つきとか・・・って何考えてるんだ私!こんな神聖な場所でそんなこと、そんなことをっ!!
「ねぇこっちはパンダの被り物してるよ」
「それは多分このショップの限定で」
「へぇ、このサイズならつけやすそうだな。一緒に買ってく?」
「お揃いってこと?」
「うん。車の鍵に付けるの探してたんだよね」
「じゃ、じゃ私も家の鍵に付ける」
「ふ~ん。それなら俺も家の鍵にするか。どっちの色がいい?」
一ノ瀬さんが両手に持ったおもち大魔神を私に見せた。一瞬、時間が止まった錯覚に陥る。隣にいた、子供の笑い声が耳の奥で木霊していた。
「一ノ瀬さんがかっこよすぎてフリーズしてました」
「えっ今!?どこで?嬉しいけど・・・よくわかんないな」
「好きな人が自分の好きな物を持ってるのって尊い」
「そういうもんなのかな・・・とりあえずこれ買ってくるよ」
色を決めて一ノ瀬さんがレジに並ぼうとした時だった。
「あれ?一ノ瀬君?」
店の周りには、大勢の人が列を作っていて、賑やかなオープニング曲も流れている。そんな中で一ノ瀬さんを呼び止める声がはっきりと聞こえた。
「やっぱり!驚いた。どうしたのこんな所で?」
「福田さんこそどうしたんですか」
外の通路に福田さんの姿があった。一ノ瀬さんは福田さんの姿に、商品を持ったまま出て行こうとする。
「あの、一ノ瀬さん。私会計行って来ます」
「あっごめん。そうだった」
「何この店?すごい込み具合だけど」
「彼女がハマってるらしくて」
「彼女?」
一ノ瀬さんから商品を受け取ると、刺すような視線が福田さんから向けらえた。会釈だけをして私はレジへと向かった。後ろから聞こえてくる一ノ瀬さんと福田さんの会話。彼女って言って大丈夫だろうか。一抹の不安が、あっという間に広がり黒い靄になっていく。自分がそうなっていたことに戸惑いを隠せなかった。さっきまであんなに楽しかったのに・・・。
しばらくして戻って来た一ノ瀬さんに、明るく作った声がわざとらしくなってしまった。それでも、続けて必要以上に笑っていたのは、一ノ瀬さんに気づかれるのが恐かった。
お揃いにしようと言って買った、おもち大魔神のキーホルダーも結局、私が二つとも持ち帰った。
□□□
数週間前までは春の風がまだ冷たく感じたのに、すぐそこまで夏が迫ってきている。外回りを終えてオフィスに戻って来ると、冷房が身体を冷やしてくれた。立ち寄ったコンビニで飲料水を買い、エレベーターに乗り込んだタイミングで乾いた喉を潤した。
「あら?お疲れ様」
声をかけてきたのは福田さんだった。こんな時思う。例えば電車を一本早めたら、取引先のご厚意のタクシーを使わずに歩いていたら、コンビニに寄らなければ、ここで会うことはなかったのにと。
「お疲れ様です」と軽く頭を下げると、ハイヒールで高くなった視界から私を見下ろした。無言の中で早く七階に着けと叫んだ。じんわりと汗ばんだ背中に汗が流れていく。さっき潤したばかりの喉がまた乾き出しそうだ。
「如月さんだっけ?一ノ瀬君と付き合ってるんだって?」
「・・・えっと、」
返答に迷ってしまった。社内恋愛禁止は今もグレーゾーン。黒川部長に知られれば面倒なことになる。でも一ノ瀬さんは、福田さんに彼女だって紹介してくれていた・・・。
「はい。まぁ、そうですね」
「ふっ意外ね。一ノ瀬君がこういう感じタイプだったなんて。たまには変わった人とお付き合いしてみたかったのかしら」
「・・・まぁ、そうですね」
つい同じ返答をしてしまった。嫌味を嫌味とわかってて言ってくる人に対して、大人になって対処法を心得ていたはずだったのに。一ノ瀬さんの話をされると、感情が大きく揺さぶられる。いつもは高野豆腐のように硬く頑丈な心が、あっという間におぼろ豆腐みたいになる。
「一ノ瀬さんモテるから不安でしょう」
「別に不安じゃありません」
「あらそう。意外とタフなのね。でも・・・」
悔しくて言い返したはいいが・・・。なんと、弱い反撃だろう。エレベーターが六階に着きドアが開く。廊下で話している社員の雑談や人の気配が伝わって来た。福田さんが降りる間際に私に釘を刺した。
「あまり本気にならない方がいいわよ。・・・一ノ瀬君とは私も昔色々あったから。部署が一緒だと出張とかもよく被るの」
厚く塗られたファンデーションがひび割れそうなほど、ニッコリと作った笑顔を見せてきた。出て行く際に、香った煙草の香りに咽そうになった。こんなわかりやすい揺さぶりをする人が、今の時代にもいるのか。しかもこんな身近に・・・。
「福田さん」
「何?」
「本気になるのは仕方ないです。私が好きなんだから。・・・失礼します」
一ノ瀬さんがモテるのは、今に始まったことじゃない。そんなの最初から知っていた。知っていて付き合った。はずなのに――私は閉のボタンを押し続けた。
「ちょっと、待って!!」
ガタンッと鈍い鉄の音がしたと思ったら、閉まりかけたドアに一ノ瀬さんが肩をねじ込ませていた。緊急を察知しドアが開く。余りの衝撃に驚いて声が出ない。一ノ瀬さんは乗り込んでくると、屋上のボタンを押した。ドアが閉まると両肩に強い力が加わった。
「大丈夫?なんか言われてなかった!?」
「・・・えっ?」
「福田さんと話してたでしょ?嫌なこと言われたかと・・・暗い顔してるし」
必死になって追いかけてきてくれた一ノ瀬さんの姿に言葉がつまった。
「はぁ・・・あの人、女性社員にライバル意識強くて。だから、如月さんも嫌味を言われてんじゃないかって心配で・・・」
心細くなって寂しくて不安で、そういった感情が一気に打ち寄せてくる。今までそういった感情を一人にの人物に対して、同時に抱いたことなんてない。こんなことくらいで、動揺して。
――抱きしめて欲しいなんて言ったら、面倒がられてしまうだろうか。
「・・・大丈夫です。何も言われてませんから」
「本当?こないだも福田さんとショップで会った時、様子がおかしくなかった?俺の気のせいならいいけど」
「一ノ瀬さんは人気だから。一々気にしてたらキリがないと心得ています」
「あのさ・・・俺、前にも話したけど好きな子にしか、莉子以外には興味ないって。告白されても振ってる。俺がこんなに好きなのがまだわからない?」
わからないのは私が変わり者だからだろうか。
お願いだから、今すぐ抱きしめて好きだと言って欲しい。そう思っているのに、平然を装うために出た言葉は全く違うものだった。
「す、すごい。それはモテ王の武勇伝」
「・・・何、その言い方」
あっ、しまった・・・。私今、変な言い方した?
スッと肩から手を離した一ノ瀬さんが私に背を向けた。・・・きっと気に障ることを言ってしまったんだ。訂正しないと。でも、どこが?どこからが変だった?
「やっと付き合えたと思ったのに、俺ばかり好きみたいで。嫌になる」
冷たさを含んだ声に、心が震えてた。
「どうして・・・嫌になるの?」
私だって、こんなに好きなのに。・・・けれど一ノ瀬さんからの返事はなかった。手を伸ばせば届く距離にいるのに、その背中が遠く感じる。
さっきまで出ていた太陽も分厚い雲に隠れ、どんよりとした空模様に変わっている。エレベータ―に滞留する空気が重すぎて息苦しかった。
□□□
翌日、電車で一ノ瀬さんに会えるかと淡い期待をしたけど、そんなに都合よくはいかなかった。朝はミーティングや会議が入るから会えない方が普通だ。酸欠状態の満員電車に、押し詰められため息が零れた。
「如月さん。コンペの企画書まだだけど、今回は見送る?」
「すみません・・・今考えてて。来週中には必ず提出します」
「それ以上は待てないからね」
一つのことが上手くいかないと、芋づる式のようにあれもこれもと、手が付けられなくなっていく。パソコンを開け仕事に向かうけど、調子が上がらない。
「どうしたの莉子。疲れてない?クマやばいよ」
「慣れないことをしてるせいかな」
「一ノ瀬君のこと?」
「・・・ううん。多分、私のせい」
昨日から続いている曇り空は、雨を溜め込んだまま、濃さを増していた。今日は雨降る予報だったから折り畳み傘をカバンに入れてきたけど、夢乃の言う通り疲れているから早めに帰ろう。