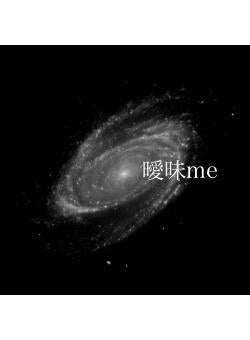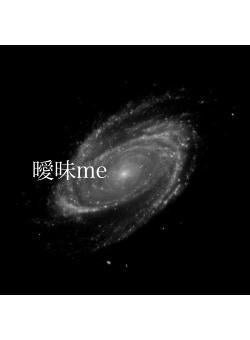*
次の日の夜。
今日もまたいつもと同じような日。
でも、二日連続で彼に会えるのは、やっぱり嬉しかった。
もう行き慣れた道を、スタスタと歩いていく。
横断歩道までくると、なぜか彼がわざわざ向かい側まできていた。
理由はすぐに分かった。
スマホの充電が切れたから、少しズレた家の時計を頼りにしていたせいで遅れてしまったんだ。
私は申し訳ないという気持ちを込めながらも、彼に手を振った。
信号が青に変わり、小走りをしていくところだった。
「やっほ、もう遅いからきちゃ……」
彼はそう言いかけていた。
「え、ちょっ――」
キィィィガッシャーン!!
もう、言いかけた頃には遅かった。
私は反射的に耳を塞ぎ、目を必死に閉じていた。
小説のワンシーンでよくある、目の前で起こった事故。
少しずつ目を開けると、力なく横たわっている彼の姿が見えた。
現実って、思ってたよりも残酷だ。
なんなの、これ……。
足が勝手に、彼の方に近づいていく。
本当はずっとずっと怖くて、見たくもないくせに。
彼の目の前までくると、するすると膝の力が抜けていくのが分かった。
「……澄真、ねえ、まって、澄真」
あぁ、そっか。
彼の名前を呼ぶのも、これが初めてだ。
馬鹿みたい。
名前を呼ぶだけなのに、これが最初で最後になるなんて。
哀れなことに、私はただ、待ってという言葉しか出てこなかった。
おかしいほどに同じ言葉を繰り返して、頭がパニック状態になっていく。
冷静でなんかいられるわけがなかった。
真夜中だから、人もいない。
私だけ、取り残されてしまったような感覚が身に染みる。
あぁ、どうしよう。
とりあえず、救急車。
こんな状態で救急車を呼べたことですら、自分を褒め称えたいぐらいだった。
電話をしたその後はどうしたのか、もう自分でも覚えていない。
次の日の夜。
今日もまたいつもと同じような日。
でも、二日連続で彼に会えるのは、やっぱり嬉しかった。
もう行き慣れた道を、スタスタと歩いていく。
横断歩道までくると、なぜか彼がわざわざ向かい側まできていた。
理由はすぐに分かった。
スマホの充電が切れたから、少しズレた家の時計を頼りにしていたせいで遅れてしまったんだ。
私は申し訳ないという気持ちを込めながらも、彼に手を振った。
信号が青に変わり、小走りをしていくところだった。
「やっほ、もう遅いからきちゃ……」
彼はそう言いかけていた。
「え、ちょっ――」
キィィィガッシャーン!!
もう、言いかけた頃には遅かった。
私は反射的に耳を塞ぎ、目を必死に閉じていた。
小説のワンシーンでよくある、目の前で起こった事故。
少しずつ目を開けると、力なく横たわっている彼の姿が見えた。
現実って、思ってたよりも残酷だ。
なんなの、これ……。
足が勝手に、彼の方に近づいていく。
本当はずっとずっと怖くて、見たくもないくせに。
彼の目の前までくると、するすると膝の力が抜けていくのが分かった。
「……澄真、ねえ、まって、澄真」
あぁ、そっか。
彼の名前を呼ぶのも、これが初めてだ。
馬鹿みたい。
名前を呼ぶだけなのに、これが最初で最後になるなんて。
哀れなことに、私はただ、待ってという言葉しか出てこなかった。
おかしいほどに同じ言葉を繰り返して、頭がパニック状態になっていく。
冷静でなんかいられるわけがなかった。
真夜中だから、人もいない。
私だけ、取り残されてしまったような感覚が身に染みる。
あぁ、どうしよう。
とりあえず、救急車。
こんな状態で救急車を呼べたことですら、自分を褒め称えたいぐらいだった。
電話をしたその後はどうしたのか、もう自分でも覚えていない。