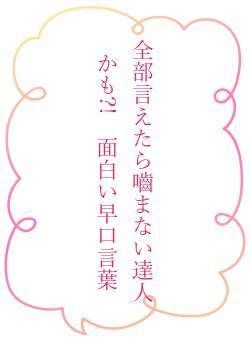合宿から帰った数日後。夏の終わりの風が吹き始めた放課後、結月は校舎の裏のベンチにひとり座っていた。
「……なんでもないよ」
隣に腰かけた陽翔に、そう言った自分の声が、遠くの風にかき消される。
ほんとは「会えなくなるのが怖い」って言いたかった。
「そばにいたい」って言いたかった。
けど、言えば何かが壊れてしまいそうで――飲み込んだ。
陽翔は、そんな結月の横顔をじっと見つめていた。
小さくて、か弱くて、でもすごく強くて、ずっとそばで見守ってくれたその背中に――「好き」って伝えたい気持ちが、喉の奥でつかえていた。
(言いたいのに、言えない――)
「……ねぇ、陽翔」
結月がぽつりと口を開いた。
「私、ほんとはね、怖いの。陽翔がいなくなったら、って考えるだけで、足がすくむ。」
陽翔の胸がぎゅっと締めつけられる。
結月は続ける。
「強くなりたいって思ってるのに、陽翔の前だと、私、どうしても弱くなっちゃうの。お兄ちゃんの時みたいに、後悔したくなくて……でも、また同じになるのが怖いの。」
陽翔はそっと、結月の肩に手を置いた。
何も言わずに、ただ静かに――その震えを受け止めるように。
「……僕も、同じだよ。怖いよ。毎日、夢を見て、次の日が来るたびに、終わりが近づいてるって思って……でも」
陽翔は、結月の方へゆっくり顔を向けた。
「君がそばにいてくれるから、僕は今、ちゃんと生きていられる。」
結月の瞳に、ぽろりと涙がこぼれる。
「……ありがとう」
その声に、陽翔は優しく微笑んだ。
夜風が、二人の間をやわらかく吹き抜けていく。
想いはまだ言葉にできないまま――でも、心と心はたしかにつながっていた。
「……なんでもないよ」
隣に腰かけた陽翔に、そう言った自分の声が、遠くの風にかき消される。
ほんとは「会えなくなるのが怖い」って言いたかった。
「そばにいたい」って言いたかった。
けど、言えば何かが壊れてしまいそうで――飲み込んだ。
陽翔は、そんな結月の横顔をじっと見つめていた。
小さくて、か弱くて、でもすごく強くて、ずっとそばで見守ってくれたその背中に――「好き」って伝えたい気持ちが、喉の奥でつかえていた。
(言いたいのに、言えない――)
「……ねぇ、陽翔」
結月がぽつりと口を開いた。
「私、ほんとはね、怖いの。陽翔がいなくなったら、って考えるだけで、足がすくむ。」
陽翔の胸がぎゅっと締めつけられる。
結月は続ける。
「強くなりたいって思ってるのに、陽翔の前だと、私、どうしても弱くなっちゃうの。お兄ちゃんの時みたいに、後悔したくなくて……でも、また同じになるのが怖いの。」
陽翔はそっと、結月の肩に手を置いた。
何も言わずに、ただ静かに――その震えを受け止めるように。
「……僕も、同じだよ。怖いよ。毎日、夢を見て、次の日が来るたびに、終わりが近づいてるって思って……でも」
陽翔は、結月の方へゆっくり顔を向けた。
「君がそばにいてくれるから、僕は今、ちゃんと生きていられる。」
結月の瞳に、ぽろりと涙がこぼれる。
「……ありがとう」
その声に、陽翔は優しく微笑んだ。
夜風が、二人の間をやわらかく吹き抜けていく。
想いはまだ言葉にできないまま――でも、心と心はたしかにつながっていた。