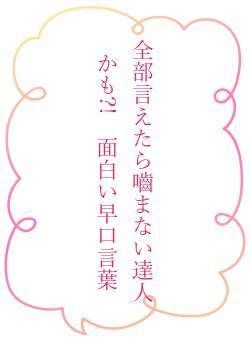夕暮れ時。図書室の窓から差し込む光が、柔らかく本棚を照らしていた。
撮影の準備が終わったあと、陽翔と結月は静かな空間に残っていた。
陽翔がノートを閉じると、結月がぽつりと呟いた。
「ねえ、陽翔……私、ほんとはずっと怖かったんだ。」
陽翔が顔を上げる。結月はまっすぐ彼を見つめていた。
「――私、お兄ちゃんを病気で亡くしたの。2年前。突然、告げられて、何もできなかった。」
沈黙が流れた。陽翔の胸が締めつけられる。
「毎日、後悔してた。あの時、もっと話していれば、もっと気づけていれば、って……」
結月の手が震えていた。けれど、その瞳は決して揺らがなかった。
「だからね、陽翔。君のことも、ちゃんと見ていたいの。」
陽翔は目を伏せたまま、拳をぎゅっと握る。
「……結月、ごめん。僕は……言えないことがある。でも、それは……言わなきゃいけないことじゃないと思ってる。」
「ううん。言えないなら、無理に言わなくていい。私が勝手に知ろうとするんじゃなくて……支えるの。陽翔が話したくなるまで、私は隣にいるから。」
陽翔の目に、涙がにじむ。
心の奥にしまっていた孤独が、少しずつ溶けていくのを感じた。
「ありがとう……結月。君にそう言ってもらえて、嬉しい。」
二人の間に、言葉にならない優しさが流れる。
沈黙が、温かな信頼に包まれていた。
結月は微笑んで言った。
「約束だよ。私は、もう大切な人を失いたくない。君の夢も、命も、ちゃんと守る。」
陽翔はその言葉を胸に刻み、静かに頷いた。
放課後の図書室。
そこには、そっと芽生えた信頼と、寄り添う想いが確かに存在していた。
撮影の準備が終わったあと、陽翔と結月は静かな空間に残っていた。
陽翔がノートを閉じると、結月がぽつりと呟いた。
「ねえ、陽翔……私、ほんとはずっと怖かったんだ。」
陽翔が顔を上げる。結月はまっすぐ彼を見つめていた。
「――私、お兄ちゃんを病気で亡くしたの。2年前。突然、告げられて、何もできなかった。」
沈黙が流れた。陽翔の胸が締めつけられる。
「毎日、後悔してた。あの時、もっと話していれば、もっと気づけていれば、って……」
結月の手が震えていた。けれど、その瞳は決して揺らがなかった。
「だからね、陽翔。君のことも、ちゃんと見ていたいの。」
陽翔は目を伏せたまま、拳をぎゅっと握る。
「……結月、ごめん。僕は……言えないことがある。でも、それは……言わなきゃいけないことじゃないと思ってる。」
「ううん。言えないなら、無理に言わなくていい。私が勝手に知ろうとするんじゃなくて……支えるの。陽翔が話したくなるまで、私は隣にいるから。」
陽翔の目に、涙がにじむ。
心の奥にしまっていた孤独が、少しずつ溶けていくのを感じた。
「ありがとう……結月。君にそう言ってもらえて、嬉しい。」
二人の間に、言葉にならない優しさが流れる。
沈黙が、温かな信頼に包まれていた。
結月は微笑んで言った。
「約束だよ。私は、もう大切な人を失いたくない。君の夢も、命も、ちゃんと守る。」
陽翔はその言葉を胸に刻み、静かに頷いた。
放課後の図書室。
そこには、そっと芽生えた信頼と、寄り添う想いが確かに存在していた。