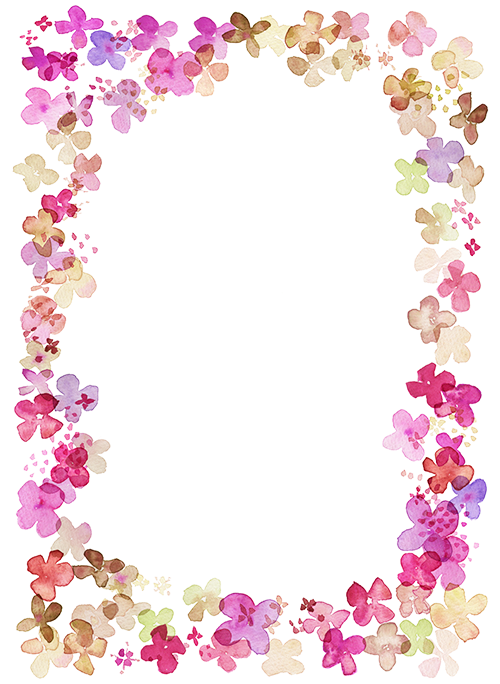初出社の朝。
受付でもらった社員証を握りしめながら、遥は胸の鼓動をなんとか落ち着けようとしていた。
──今日から、私は編集部の一員。
まだ信じられないけど、これは「選ばれた」のではなく、自分で選んだ道だ。
エレベーターを降りてオフィスに入った瞬間、ふいに聞こえた声に、遥は足を止めた。
「……おつかれさまです。アプリ側のチェック、午後イチまでに上げときます」
聞き覚えのある低めの声。振り返ると、ガラス越しの会議室に、見慣れた後ろ姿があった。
──え?
遥が立ち尽くしていると、その人物がふとこちらを向いて、軽く手を振る。
「やっと来たね、『編集部の星』さん」
「え……なんで悠真がここに!?」
彼は笑って会議室を出てきて、名札を見せる。
「高橋悠真、システム部所属。ここの漫画事業部に常駐中です」
「なにそれ、どういうこと……?」
「言ってなかったっけ? 俺、もともと漫画系アプリの開発に関わってて。この会社の配信アプリ、俺のチームが一部つくってるんだよね」
「え……初耳なんですけど……」
「だって、転職決まって舞い上がってる遥が可愛くて、邪魔したくなかったんだ」
さらりと、そう言われて──遥の心臓がどくんと脈打った。
「なっ……そんな、可愛いとか……」
「可愛いよ。ずっと、可愛い」
そう言った悠真の眼差しは、冗談じゃなかった。
「それに、ちゃんと読んでたし。遥が書いた『レボルの記憶回の考察記事』」
「え……! っていうか、悠真、レボルの漫画、もう追ってなかったんじゃないの?」
「ごめん、嘘ついた。遥と話すきっかけが欲しくて」
悠真はからからと笑って、続けた。
「8年くらい前だったかな? 遥、『記憶の伏線は第2話から始まっていた』って書いてたよね。俺、あれ読んで震えたよ」
遥は、言葉が出なかった。
まさか──こんなに近くで、こんなに長く、自分の文章を覚えてくれていた人がいたなんて。
「実はさ、最初にこの会社と仕事することになったのも、遥の記事がきっかけだった」
「……え?」
「『今、この編集部の漫画、面白い』って思わせてくれたの、遥だったから」
彼の言葉は、遥の胸にまっすぐ届いた。
自己肯定感なんてなかったあの頃の自分を、誰かが肯定してくれていた。それが、悠真だった。
「じゃあ……私たちがまた会えたのって……」
「偶然だけど、偶然じゃない。遥が『自分の足でここに来た』から、こうなったんだよ」
「悠真……」
名前を呼んだその瞬間、悠真が一歩、近づく。
悠真の熱のある視線が、遥を捉えた。
「これからは、ちゃんと言うようにする」
「なにを?」
「遥が可愛いってこと。ずっと、好きだったってこと」
「……ばか」
そう言いながらも、遥は笑っていた。
ずっと、こうして隣にいてほしかった人が、いま隣にいる。
その日、ふたりは帰り道の地下鉄の中で、自然に手をつないでいた。
「悠真、私たちって、今どんな関係なんだろう」
「『また恋をはじめたふたり』って感じ?」
「なにそれ、ドラマのタイトルみたい」
遥は、目を細めて笑った。それから、こう呟いた。
「悠真。君をひとりにさせない、よ」
言い終えてから、少しの沈黙が落ちる。
悠真はやさしく微笑んで、遥の手をぎゅっと握り直した。
「俺も。これからはずっと、一緒にいよう」
顔が熱くなるのを感じながら、遥は小さく頷いた。
受付でもらった社員証を握りしめながら、遥は胸の鼓動をなんとか落ち着けようとしていた。
──今日から、私は編集部の一員。
まだ信じられないけど、これは「選ばれた」のではなく、自分で選んだ道だ。
エレベーターを降りてオフィスに入った瞬間、ふいに聞こえた声に、遥は足を止めた。
「……おつかれさまです。アプリ側のチェック、午後イチまでに上げときます」
聞き覚えのある低めの声。振り返ると、ガラス越しの会議室に、見慣れた後ろ姿があった。
──え?
遥が立ち尽くしていると、その人物がふとこちらを向いて、軽く手を振る。
「やっと来たね、『編集部の星』さん」
「え……なんで悠真がここに!?」
彼は笑って会議室を出てきて、名札を見せる。
「高橋悠真、システム部所属。ここの漫画事業部に常駐中です」
「なにそれ、どういうこと……?」
「言ってなかったっけ? 俺、もともと漫画系アプリの開発に関わってて。この会社の配信アプリ、俺のチームが一部つくってるんだよね」
「え……初耳なんですけど……」
「だって、転職決まって舞い上がってる遥が可愛くて、邪魔したくなかったんだ」
さらりと、そう言われて──遥の心臓がどくんと脈打った。
「なっ……そんな、可愛いとか……」
「可愛いよ。ずっと、可愛い」
そう言った悠真の眼差しは、冗談じゃなかった。
「それに、ちゃんと読んでたし。遥が書いた『レボルの記憶回の考察記事』」
「え……! っていうか、悠真、レボルの漫画、もう追ってなかったんじゃないの?」
「ごめん、嘘ついた。遥と話すきっかけが欲しくて」
悠真はからからと笑って、続けた。
「8年くらい前だったかな? 遥、『記憶の伏線は第2話から始まっていた』って書いてたよね。俺、あれ読んで震えたよ」
遥は、言葉が出なかった。
まさか──こんなに近くで、こんなに長く、自分の文章を覚えてくれていた人がいたなんて。
「実はさ、最初にこの会社と仕事することになったのも、遥の記事がきっかけだった」
「……え?」
「『今、この編集部の漫画、面白い』って思わせてくれたの、遥だったから」
彼の言葉は、遥の胸にまっすぐ届いた。
自己肯定感なんてなかったあの頃の自分を、誰かが肯定してくれていた。それが、悠真だった。
「じゃあ……私たちがまた会えたのって……」
「偶然だけど、偶然じゃない。遥が『自分の足でここに来た』から、こうなったんだよ」
「悠真……」
名前を呼んだその瞬間、悠真が一歩、近づく。
悠真の熱のある視線が、遥を捉えた。
「これからは、ちゃんと言うようにする」
「なにを?」
「遥が可愛いってこと。ずっと、好きだったってこと」
「……ばか」
そう言いながらも、遥は笑っていた。
ずっと、こうして隣にいてほしかった人が、いま隣にいる。
その日、ふたりは帰り道の地下鉄の中で、自然に手をつないでいた。
「悠真、私たちって、今どんな関係なんだろう」
「『また恋をはじめたふたり』って感じ?」
「なにそれ、ドラマのタイトルみたい」
遥は、目を細めて笑った。それから、こう呟いた。
「悠真。君をひとりにさせない、よ」
言い終えてから、少しの沈黙が落ちる。
悠真はやさしく微笑んで、遥の手をぎゅっと握り直した。
「俺も。これからはずっと、一緒にいよう」
顔が熱くなるのを感じながら、遥は小さく頷いた。