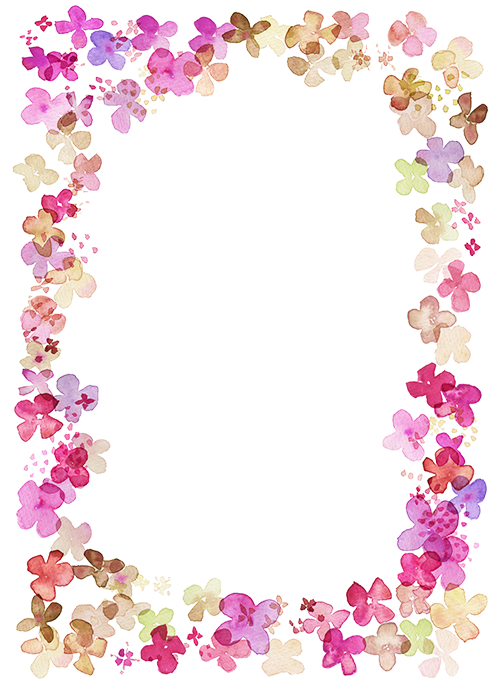履歴書の「職歴」欄を見つめたまま、ボールペンを握る手が止まっていた。
(本当に、私の人生、うまくいかなかったな……)
大学受験に失敗し、浪人も叶わず、フリーター生活。今は出版社の下請けで、Web記事を書く毎日。将来は見えない。貯金もない。
それでも書くことだけは、なぜか手放さなかった。
(──どうしてだろう)
ふと、頭に浮かんだのは、中学三年の卒業式の日だった。
その年の三月。
体育館での式が終わったあと、遅れて満開になった校庭の桜の下で、遥は悠真に声をかけた。
「ねえ、ちょっとだけ時間ある?」
「うん、なに?」
二人で並んで歩いたグラウンドの端。ベンチに座って、遥はいつものように、軽い調子で話し始めた。
「レボル、来週で第二部完結なんだって。『星屑レボルシオン』、またひと区切り」
「マジか。じゃあ……いよいよ『星屑の記憶』回、くるな」
「うん……でね、悠真。ちょっと話あるの」
「……うん」
遥はほんの少しだけ、息を吸ってから言った。
「私、進学校行くから、たぶん部活も辞めて勉強に専念すると思う。漫画も、読む余裕ないかも。だから……」
言いよどんだ言葉の先を、悠真は待ってくれた。
「だから……一度、ちゃんと、別れようと思ってる。私のわがままだって分かってる。でも……このまま中途半端にしたくないから」
悠真は、黙って少しだけうつむいたあと、小さくうなずいた。
「……そっか。遥が、そう思うなら、いいよ」
そう言って、笑った。
「……ちゃんと、応援する。遥なら、どこまでも行けるって思ってるから」
「……ありがとう」
言葉が、にじむように胸に残った。
そして──
「あのさ、最後にちょっとだけ言ってもいい?」
「え?」
「遥って、レボルの感想とか考察書くの、めちゃくちゃうまいし。言葉に力がある。……だからさ、書くことは、これからもやめないでほしい」
そのときの彼の顔を、遥はずっと忘れられなかった。
──書くことをやめなかったのは、あの言葉のせいだった。
ライターになる道は、決して順調ではなかった。
でも、あのとき悠真がそう言ってくれなかったら、たぶん私は、文章にしがみついてこられなかった。
(……あれが、私の「原点」だったんだ)
遥は、空欄だった「自己PR」欄に、ゆっくりとペンを走らせた。
その週、初めて本格的に挑んだ編集プロダクションの面接。
「なぜ書くことを続けてきたのか」と聞かれたとき、遥は少し笑って答えた。
「……中学のときに、友達に『言葉に力がある』って言われたことがあって。それが、ずっと支えで」
「それ、大事ですね。誰かの言葉が、自分の道をつくってくれることってありますよ」
面接を終えて外に出ると、春の光が差していた。
翌日、スマホに届いたメールの件名には「内定通知」の文字があった。
遥はすぐに悠真に電話をかけた。
「──受かった! 受かったよ悠真!」
「ほんと!? やったな遥!」
声が、弾んでいた。昔と同じ、でも少し大人になった声で。
「それでさ、会社名って……どこだった?」
「原田編集プロダクション。なんか漫画案件も多くて」
「……あー、知ってる。もしかしたら、今度驚くことになるかも」
「え、なにそれ」
「言えないけど、初出社、楽しみにしといて」
その言葉に、遥は笑った。
またきっと、あの頃みたいに──いや、あの頃とは違う形で。
(本当に、私の人生、うまくいかなかったな……)
大学受験に失敗し、浪人も叶わず、フリーター生活。今は出版社の下請けで、Web記事を書く毎日。将来は見えない。貯金もない。
それでも書くことだけは、なぜか手放さなかった。
(──どうしてだろう)
ふと、頭に浮かんだのは、中学三年の卒業式の日だった。
その年の三月。
体育館での式が終わったあと、遅れて満開になった校庭の桜の下で、遥は悠真に声をかけた。
「ねえ、ちょっとだけ時間ある?」
「うん、なに?」
二人で並んで歩いたグラウンドの端。ベンチに座って、遥はいつものように、軽い調子で話し始めた。
「レボル、来週で第二部完結なんだって。『星屑レボルシオン』、またひと区切り」
「マジか。じゃあ……いよいよ『星屑の記憶』回、くるな」
「うん……でね、悠真。ちょっと話あるの」
「……うん」
遥はほんの少しだけ、息を吸ってから言った。
「私、進学校行くから、たぶん部活も辞めて勉強に専念すると思う。漫画も、読む余裕ないかも。だから……」
言いよどんだ言葉の先を、悠真は待ってくれた。
「だから……一度、ちゃんと、別れようと思ってる。私のわがままだって分かってる。でも……このまま中途半端にしたくないから」
悠真は、黙って少しだけうつむいたあと、小さくうなずいた。
「……そっか。遥が、そう思うなら、いいよ」
そう言って、笑った。
「……ちゃんと、応援する。遥なら、どこまでも行けるって思ってるから」
「……ありがとう」
言葉が、にじむように胸に残った。
そして──
「あのさ、最後にちょっとだけ言ってもいい?」
「え?」
「遥って、レボルの感想とか考察書くの、めちゃくちゃうまいし。言葉に力がある。……だからさ、書くことは、これからもやめないでほしい」
そのときの彼の顔を、遥はずっと忘れられなかった。
──書くことをやめなかったのは、あの言葉のせいだった。
ライターになる道は、決して順調ではなかった。
でも、あのとき悠真がそう言ってくれなかったら、たぶん私は、文章にしがみついてこられなかった。
(……あれが、私の「原点」だったんだ)
遥は、空欄だった「自己PR」欄に、ゆっくりとペンを走らせた。
その週、初めて本格的に挑んだ編集プロダクションの面接。
「なぜ書くことを続けてきたのか」と聞かれたとき、遥は少し笑って答えた。
「……中学のときに、友達に『言葉に力がある』って言われたことがあって。それが、ずっと支えで」
「それ、大事ですね。誰かの言葉が、自分の道をつくってくれることってありますよ」
面接を終えて外に出ると、春の光が差していた。
翌日、スマホに届いたメールの件名には「内定通知」の文字があった。
遥はすぐに悠真に電話をかけた。
「──受かった! 受かったよ悠真!」
「ほんと!? やったな遥!」
声が、弾んでいた。昔と同じ、でも少し大人になった声で。
「それでさ、会社名って……どこだった?」
「原田編集プロダクション。なんか漫画案件も多くて」
「……あー、知ってる。もしかしたら、今度驚くことになるかも」
「え、なにそれ」
「言えないけど、初出社、楽しみにしといて」
その言葉に、遥は笑った。
またきっと、あの頃みたいに──いや、あの頃とは違う形で。