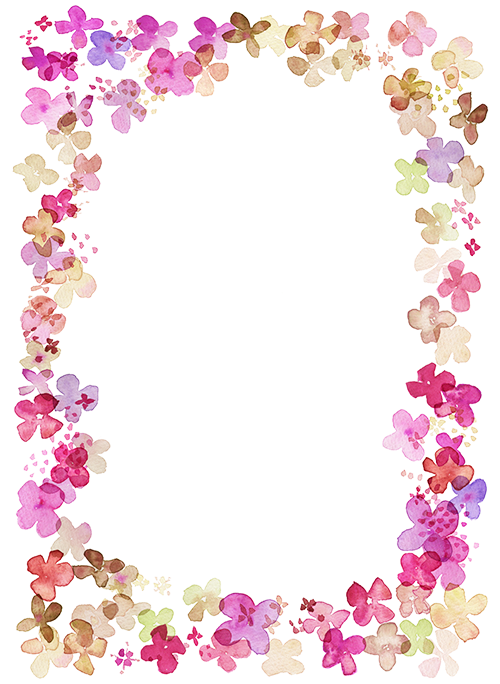映画に行く約束をしたその夜、遥はなんとなく、久しぶりにSNSを開いた。
フォロー欄のなかに、今朝まで「記憶のなかの人」だった名前があるのが、妙にそわそわする。
──高橋悠真。
中学卒業以来、見たこともなかった彼の現在が、指先ひとつで覗けてしまうことが、少し怖くて、でも気になって。
つい、タップしてしまった。
そこには思っていたよりずっと、リアルな彼がいた。
広いオフィスでノートパソコンを前にした写真。
海外カンファレンスらしき会場で、英語でスピーチをしている姿。
部内の懇親会で笑っている姿や、友人らしき数人との登山の記録。
そのどれもが、自信と余裕にあふれていた。
(……なんか、すごいな)
心の底からそう思った。
同じ28歳。自分だって一応「働いている」けれど、並べられたら到底勝てない気がする。
(ていうか、勝ち負けじゃないって分かってるけど……)
小さなため息が漏れた。
部屋のなかは静かで、キーボードの打鍵音も、編集部からの通知も鳴らない夜だった。
明日〆切の記事にはまだタイトルすら決まっていない。
クライアントからは「もう少し読者目線で」「レギュレーションに沿っているだけで、つまらない」と言われてしまった。何度書き直しても結果は同じで、「これが能力の限界ってことか」と勝手に思う自分もいる。
(私……何してるんだろ)
そう呟いた瞬間、スマホの通知が震えた。
悠真からのLINEだった。
「あ、そうだ。映画、来週の金曜とかどう?」
「仕事終わりに池袋集合とかでもいけるよ。懐かしの『レボルの聖地』ってことで」
懐かしの──その言葉に、少しだけ口元が緩む。
あの頃、よく二人で話していた。
「エルゲータって、もし地球にあるならどこだろうね」
「池袋とか? ごちゃごちゃしてて、宇宙感あるよね」
──とりとめのない会話。けれど、唯一、自分が特別だった時間。
メッセージの返信を打とうとする手が、止まった。
(……このまま会って、どうするんだろ。私は、何を期待してるんだろ)
スマホを伏せて、遥は天井を見上げた。
そこに広がっていたのは、何もない「現在」だった。
フォロー欄のなかに、今朝まで「記憶のなかの人」だった名前があるのが、妙にそわそわする。
──高橋悠真。
中学卒業以来、見たこともなかった彼の現在が、指先ひとつで覗けてしまうことが、少し怖くて、でも気になって。
つい、タップしてしまった。
そこには思っていたよりずっと、リアルな彼がいた。
広いオフィスでノートパソコンを前にした写真。
海外カンファレンスらしき会場で、英語でスピーチをしている姿。
部内の懇親会で笑っている姿や、友人らしき数人との登山の記録。
そのどれもが、自信と余裕にあふれていた。
(……なんか、すごいな)
心の底からそう思った。
同じ28歳。自分だって一応「働いている」けれど、並べられたら到底勝てない気がする。
(ていうか、勝ち負けじゃないって分かってるけど……)
小さなため息が漏れた。
部屋のなかは静かで、キーボードの打鍵音も、編集部からの通知も鳴らない夜だった。
明日〆切の記事にはまだタイトルすら決まっていない。
クライアントからは「もう少し読者目線で」「レギュレーションに沿っているだけで、つまらない」と言われてしまった。何度書き直しても結果は同じで、「これが能力の限界ってことか」と勝手に思う自分もいる。
(私……何してるんだろ)
そう呟いた瞬間、スマホの通知が震えた。
悠真からのLINEだった。
「あ、そうだ。映画、来週の金曜とかどう?」
「仕事終わりに池袋集合とかでもいけるよ。懐かしの『レボルの聖地』ってことで」
懐かしの──その言葉に、少しだけ口元が緩む。
あの頃、よく二人で話していた。
「エルゲータって、もし地球にあるならどこだろうね」
「池袋とか? ごちゃごちゃしてて、宇宙感あるよね」
──とりとめのない会話。けれど、唯一、自分が特別だった時間。
メッセージの返信を打とうとする手が、止まった。
(……このまま会って、どうするんだろ。私は、何を期待してるんだろ)
スマホを伏せて、遥は天井を見上げた。
そこに広がっていたのは、何もない「現在」だった。