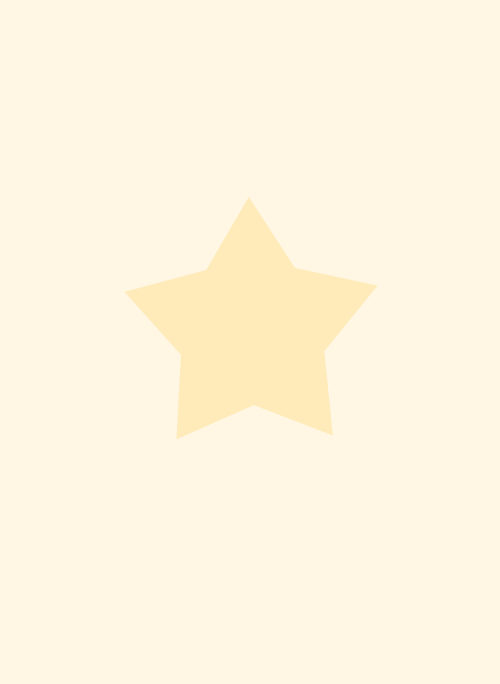「私はね、あなたと一緒に死ぬの。」 「そうだね。」
「でもなんか、あなたを置いて逝きそうな気もする。」 「それはちっと寂しいなあ。」
「寂しいの? 胸を触れないからでしょう?」 「そうだなあ。」
「何だよ 変態親父!」 「いてえ。」
麻理は拳骨をお見舞いすると台所に立った。 その後ろに俺も立ってみる。
「なあに?」 「何でも、、、。」
「スカート捲りしたいでしょう?」 「いやいや、そんなことは、、、。」
「してもいいのよ。 あなたの物だから。」 「物じゃない。 お前は嫁だ。」
「あーーら、嫁だったのね? 妻じゃなかったのか。」 「嫁も妻も同じだろう?」
「全然違うわよ。 嫁ってのは外から借りてきた子猫。 妻ってのは旦那様に愛されてる人のことよ。」 「そうか。」
「じゃあ、あなたはやっぱり私のことを愛してないのね?」 「そんなこと無いよ。 ずっと、、、。」
「だったら私を妻だって言えるはずよねえ?」 「ごめんごめん。 麻理は俺の妻だ。」
「それでほんとにいいの?」 「いいよ。 文句も無い。」
「ありがとう。」 そう言って振り向いた麻理は俺に飛び込んできた。
その頬っぺたを撫でながらキスをする。 「うーーーん、萌えちゃいそう。」
「いいよ。 どんどん萌えて。」 「何か考えてるでしょう? 変なこと。」
「何も考えてないよ。」 「嘘吐け。 この手は何よ?」
「触ってもいいって言うから。」 「あなたもほんとに若いのねえ。 裸になってあげる。」
「ちょい待ち。」 服を脱ぎかけた麻理を制止する。 二階から姉ちゃんが下りてきた。
「ワオ、仲いいなあ。」 「夫婦ですから。」
澄まして答える麻理の頬っぺたをツンツン。 「いいじゃない。 ほんとのことなんだから。」
「姉ちゃんには相手が、、、。」 「居るわよ ここに。」
「えーーーーーー? まだまだ良太さんとやる気なの?」 「だってさあ、もてないんだもん。」
「お姉さん それはあなたが悪いのよ。 良太さんに苦労ばかりさせるから。」 「言うなあ 麻理。」
「は? これくらいは言わせてもらうわよ。 私はあなたの妻なんですから。」 「いいもん。 誰も私なんか可愛がってくれないんだもん。」
「そうやってカリントウでも食べてなさい。」 麻理は言い切ると台所に立った。
「なんか疲れちゃったなあ。 簡単なおかずを作るか。」 そう言って麻理は野菜炒めを作り始めた。
姉ちゃんはというと不貞腐れた顔でカリントウを食べてます。 「お腹いっぱいだから要らないわ。」
そう言って二階へ上がっていきました。 「勝手にやってろ。 ボケナス。」
麻理は野菜炒めを作ると皿を取り出して大盛りを俺の前に置いた。 「大盛りだね。」
「あなたにはまだまだ元気で居てほしいから。」 「お前も食べなよ。」
「うん。 私はちゃんと食べてるから大丈夫。」 隣に座った麻理は太腿をくっ付けてきた。
「食べてもいいからね。」 「ありがとう。 後でゆっくり戴くよ。」
それにしても静かな静かな夜だ。 母ちゃんたちが居た頃は毎晩のように賑やかだったのに。
まあ母ちゃんにはいーーーーーーっつも冷や汗を掻かされてたっけなあ。 いきなり姉ちゃんと結婚しろって言ってくるし、、、。
でも結局はくっ付かないままで30年が経ってしまった。 子供も産ませなくて良かったよ。
あの頃の姉ちゃんはサボり魔だった。 そっと抜け出しては交番に遊びに来てたっけ。
我慢も限界だった店長にしこたまお説教をされて誓約書まで書かされてからやっと真面目に働くようになったんだよなあ。
それでも彼氏はついにくっ付かなかった。 可哀そうになあ。
その頃だよ。 麻理は婚約が破棄されて俺に飛び込んできたのは。
夢かと思ったよ。 こいつが俺に飛び込んでくるなんて、、、。
「今夜もお風呂は一緒に入りましょうねえ。」 「そうだねえ。 洗ってやるよ。」
「またまた狙ってるでしょ?」 「狙わなくてどうするんだよ? そのお胸。」
「分かった。 死ぬ時には胸だけ置いて逝くね。」 「えーーーー? 胸だけかーい?」
「全部置いて逝くの? それもまた面倒だなあ。」 「いいじゃん。 三日くらいは。」
「三日だけなの? それも嫌だなあ。」 「しょうがない。 人形で残すか。」
「変な趣味。」 「いいだろう。 それだけ麻理を愛してるんだ 俺は。」
「そっか。 私って意外と幸せだったのね?」 「何だよ 意外って?」
「まあ、いいからいいから。 お楽しみは後に取っておきましょうね。 お父さん。」 麻理はそう言うとニコッと笑ってキスをした。
ボワーーーーー、、、、。 なんかいきなり宙に浮いた気分だ。
こうやっていつも俺は麻理に抑え込まれてるんだ。 しかしまあ、よくやるわ。
姉ちゃんだったらあれだけ発狂しそうだったのになあ。 そうそう、あのお人形さんはまだまだ交番に置いてあります。
ちょいとボロボロになってきたからあっちこっち修理してるけどね。 でもさ、あの人形 どことなく麻理に似てるんだけど、、、。
もしかして麻理ってあの人形の生まれ変わりか? そんなことは無いよなあ。
あれやこれや考えていると麻理の声が聞こえた。 「お風呂 いいわよ。」
「うーん。」 生返事をしてから動く。
脱衣所のドアを開けてみると麻理が真正面で脱いでいた。 「ワーオ。」
「なあに? 珍しい物を見付けたような顔して。」 「お前のお胸は地球上の一番大事な宝物だから。」
「変な趣味。」 「いいんだ それでも。」
「良太さん 30年前と変わってないわねえ。」 「当り前だ。 男がコロコロ変わってたまるかってんだ。」
「なんか素敵だわ。 惚れ直しちゃう。」 「何回でも惚れ直してくれ。」
「かっこ付けるな ボケ。」 「アグ、、、。」
麻理は脱いでしまうと浴室のほうを向いた。 その背中を抱いてみると、、、、。
なぜか麻理はじっとしている。 「食べていいわよ。」
そう言うものだから思いっ切り食べちゃった。
「激しかったなあ。 お父さん 溜まってたのね?」 「そりゃあ3週間近くやってないんだもん。 溜まるわ。」
「でも良かった。 ガス抜きできたから明日からも頑張ってね。」 「オー!」
それにしてもまあ本当に60歳の夫婦なんだろうか? 無邪気というのか若いというのか、、、。
その頃、姉ちゃんはというとカリントウを腹いっぱい食べたものだからすっかり寝込んでしまっていますねえ。 静かで平和でいいわーー。
姉ちゃんが居るとどっかで誰かが喧嘩してるからなあ。 歩くトラブルメーカーも珍しい。
体を洗って湯に浸かって天井を二人で仰いでおります。 この家も修理しながらここまで使ってきたんだ。
もうすぐ50年くらいになるからねえ。 よく頑張ったもんだ。
「明日さあ、交番に遊びに行ってもいい?」 「何するの?」
「あなたの仕事を見てみたいの。」 「やることはなーーーんにも無いけど。」
「それでもいいのよ。 この世の思い出にしたいから。」 「寂しいこと言うなよ。 死ぬのはまだ先だぜ。」
「いつ死ぬか分からないでしょう? だから見ておきたいのよ。」 「それもそうだな。」
そんなわけで翌日は麻理と二人で交番へ行くことにしたんですわ。 二階にはまだまだ姉ちゃんの荷物が置いてあるのに、、、。
その日も姉ちゃんは俺たちとは口も聞きませんです。 平和ですなあ。
朝、台所には麻理が居ます。 味噌汁を作りながらチラッチラッと外を眺めてますねえ。
「この辺りもずいぶんと変わったわねえ。」 「そりゃそうさ。 30年も経てば変わるよ。」
「あの頃はセルフレジがトレンドだったのに今はチップレジだもんねえ。」 「そうだなあ。 カードすら持ち歩かなくなったもんなあ。」
スマホをかざす必要も無い。 ポケットに入れておくだけで勝手に決済されている。 いいのか悪いのか、、、。
だから万引きしようにも出来なくなったんだよな。 決済できないと店から出れないんだもん。
それどころか警察に自動通報されてしまって捉まるんだもんなあ。 怖いよなあ。
うちには連絡なんて来ないけど、、、。 たまには仕事をさせてくれーーーーーー。
「あれ? 姉ちゃんは?」 「さあねえ。 そのうちに食べに来るでしょうよ。」
「冷たいなあ。」 「あなたが優し過ぎるのよ。 だからもてなかったでしょう?」
「それはそうかもしれんが、、、。」 「あのお姉さんと心中した買ったらしてもいいのよ。 構わないから。」
「それは嫌だよ。」 「何で?」
「麻理が居るから。」 「私が居たってお姉さん何だもん。 関係無いわよ。」
「大いに関係有るよ。」 「そっか。 そこまで私を愛してくれてるのね?」
そこへやっと姉ちゃんが入ってきた。 「そこに有るから。」
「ん。」 なんか朝から微妙な空気が、、、。
「でもなんか、あなたを置いて逝きそうな気もする。」 「それはちっと寂しいなあ。」
「寂しいの? 胸を触れないからでしょう?」 「そうだなあ。」
「何だよ 変態親父!」 「いてえ。」
麻理は拳骨をお見舞いすると台所に立った。 その後ろに俺も立ってみる。
「なあに?」 「何でも、、、。」
「スカート捲りしたいでしょう?」 「いやいや、そんなことは、、、。」
「してもいいのよ。 あなたの物だから。」 「物じゃない。 お前は嫁だ。」
「あーーら、嫁だったのね? 妻じゃなかったのか。」 「嫁も妻も同じだろう?」
「全然違うわよ。 嫁ってのは外から借りてきた子猫。 妻ってのは旦那様に愛されてる人のことよ。」 「そうか。」
「じゃあ、あなたはやっぱり私のことを愛してないのね?」 「そんなこと無いよ。 ずっと、、、。」
「だったら私を妻だって言えるはずよねえ?」 「ごめんごめん。 麻理は俺の妻だ。」
「それでほんとにいいの?」 「いいよ。 文句も無い。」
「ありがとう。」 そう言って振り向いた麻理は俺に飛び込んできた。
その頬っぺたを撫でながらキスをする。 「うーーーん、萌えちゃいそう。」
「いいよ。 どんどん萌えて。」 「何か考えてるでしょう? 変なこと。」
「何も考えてないよ。」 「嘘吐け。 この手は何よ?」
「触ってもいいって言うから。」 「あなたもほんとに若いのねえ。 裸になってあげる。」
「ちょい待ち。」 服を脱ぎかけた麻理を制止する。 二階から姉ちゃんが下りてきた。
「ワオ、仲いいなあ。」 「夫婦ですから。」
澄まして答える麻理の頬っぺたをツンツン。 「いいじゃない。 ほんとのことなんだから。」
「姉ちゃんには相手が、、、。」 「居るわよ ここに。」
「えーーーーーー? まだまだ良太さんとやる気なの?」 「だってさあ、もてないんだもん。」
「お姉さん それはあなたが悪いのよ。 良太さんに苦労ばかりさせるから。」 「言うなあ 麻理。」
「は? これくらいは言わせてもらうわよ。 私はあなたの妻なんですから。」 「いいもん。 誰も私なんか可愛がってくれないんだもん。」
「そうやってカリントウでも食べてなさい。」 麻理は言い切ると台所に立った。
「なんか疲れちゃったなあ。 簡単なおかずを作るか。」 そう言って麻理は野菜炒めを作り始めた。
姉ちゃんはというと不貞腐れた顔でカリントウを食べてます。 「お腹いっぱいだから要らないわ。」
そう言って二階へ上がっていきました。 「勝手にやってろ。 ボケナス。」
麻理は野菜炒めを作ると皿を取り出して大盛りを俺の前に置いた。 「大盛りだね。」
「あなたにはまだまだ元気で居てほしいから。」 「お前も食べなよ。」
「うん。 私はちゃんと食べてるから大丈夫。」 隣に座った麻理は太腿をくっ付けてきた。
「食べてもいいからね。」 「ありがとう。 後でゆっくり戴くよ。」
それにしても静かな静かな夜だ。 母ちゃんたちが居た頃は毎晩のように賑やかだったのに。
まあ母ちゃんにはいーーーーーーっつも冷や汗を掻かされてたっけなあ。 いきなり姉ちゃんと結婚しろって言ってくるし、、、。
でも結局はくっ付かないままで30年が経ってしまった。 子供も産ませなくて良かったよ。
あの頃の姉ちゃんはサボり魔だった。 そっと抜け出しては交番に遊びに来てたっけ。
我慢も限界だった店長にしこたまお説教をされて誓約書まで書かされてからやっと真面目に働くようになったんだよなあ。
それでも彼氏はついにくっ付かなかった。 可哀そうになあ。
その頃だよ。 麻理は婚約が破棄されて俺に飛び込んできたのは。
夢かと思ったよ。 こいつが俺に飛び込んでくるなんて、、、。
「今夜もお風呂は一緒に入りましょうねえ。」 「そうだねえ。 洗ってやるよ。」
「またまた狙ってるでしょ?」 「狙わなくてどうするんだよ? そのお胸。」
「分かった。 死ぬ時には胸だけ置いて逝くね。」 「えーーーー? 胸だけかーい?」
「全部置いて逝くの? それもまた面倒だなあ。」 「いいじゃん。 三日くらいは。」
「三日だけなの? それも嫌だなあ。」 「しょうがない。 人形で残すか。」
「変な趣味。」 「いいだろう。 それだけ麻理を愛してるんだ 俺は。」
「そっか。 私って意外と幸せだったのね?」 「何だよ 意外って?」
「まあ、いいからいいから。 お楽しみは後に取っておきましょうね。 お父さん。」 麻理はそう言うとニコッと笑ってキスをした。
ボワーーーーー、、、、。 なんかいきなり宙に浮いた気分だ。
こうやっていつも俺は麻理に抑え込まれてるんだ。 しかしまあ、よくやるわ。
姉ちゃんだったらあれだけ発狂しそうだったのになあ。 そうそう、あのお人形さんはまだまだ交番に置いてあります。
ちょいとボロボロになってきたからあっちこっち修理してるけどね。 でもさ、あの人形 どことなく麻理に似てるんだけど、、、。
もしかして麻理ってあの人形の生まれ変わりか? そんなことは無いよなあ。
あれやこれや考えていると麻理の声が聞こえた。 「お風呂 いいわよ。」
「うーん。」 生返事をしてから動く。
脱衣所のドアを開けてみると麻理が真正面で脱いでいた。 「ワーオ。」
「なあに? 珍しい物を見付けたような顔して。」 「お前のお胸は地球上の一番大事な宝物だから。」
「変な趣味。」 「いいんだ それでも。」
「良太さん 30年前と変わってないわねえ。」 「当り前だ。 男がコロコロ変わってたまるかってんだ。」
「なんか素敵だわ。 惚れ直しちゃう。」 「何回でも惚れ直してくれ。」
「かっこ付けるな ボケ。」 「アグ、、、。」
麻理は脱いでしまうと浴室のほうを向いた。 その背中を抱いてみると、、、、。
なぜか麻理はじっとしている。 「食べていいわよ。」
そう言うものだから思いっ切り食べちゃった。
「激しかったなあ。 お父さん 溜まってたのね?」 「そりゃあ3週間近くやってないんだもん。 溜まるわ。」
「でも良かった。 ガス抜きできたから明日からも頑張ってね。」 「オー!」
それにしてもまあ本当に60歳の夫婦なんだろうか? 無邪気というのか若いというのか、、、。
その頃、姉ちゃんはというとカリントウを腹いっぱい食べたものだからすっかり寝込んでしまっていますねえ。 静かで平和でいいわーー。
姉ちゃんが居るとどっかで誰かが喧嘩してるからなあ。 歩くトラブルメーカーも珍しい。
体を洗って湯に浸かって天井を二人で仰いでおります。 この家も修理しながらここまで使ってきたんだ。
もうすぐ50年くらいになるからねえ。 よく頑張ったもんだ。
「明日さあ、交番に遊びに行ってもいい?」 「何するの?」
「あなたの仕事を見てみたいの。」 「やることはなーーーんにも無いけど。」
「それでもいいのよ。 この世の思い出にしたいから。」 「寂しいこと言うなよ。 死ぬのはまだ先だぜ。」
「いつ死ぬか分からないでしょう? だから見ておきたいのよ。」 「それもそうだな。」
そんなわけで翌日は麻理と二人で交番へ行くことにしたんですわ。 二階にはまだまだ姉ちゃんの荷物が置いてあるのに、、、。
その日も姉ちゃんは俺たちとは口も聞きませんです。 平和ですなあ。
朝、台所には麻理が居ます。 味噌汁を作りながらチラッチラッと外を眺めてますねえ。
「この辺りもずいぶんと変わったわねえ。」 「そりゃそうさ。 30年も経てば変わるよ。」
「あの頃はセルフレジがトレンドだったのに今はチップレジだもんねえ。」 「そうだなあ。 カードすら持ち歩かなくなったもんなあ。」
スマホをかざす必要も無い。 ポケットに入れておくだけで勝手に決済されている。 いいのか悪いのか、、、。
だから万引きしようにも出来なくなったんだよな。 決済できないと店から出れないんだもん。
それどころか警察に自動通報されてしまって捉まるんだもんなあ。 怖いよなあ。
うちには連絡なんて来ないけど、、、。 たまには仕事をさせてくれーーーーーー。
「あれ? 姉ちゃんは?」 「さあねえ。 そのうちに食べに来るでしょうよ。」
「冷たいなあ。」 「あなたが優し過ぎるのよ。 だからもてなかったでしょう?」
「それはそうかもしれんが、、、。」 「あのお姉さんと心中した買ったらしてもいいのよ。 構わないから。」
「それは嫌だよ。」 「何で?」
「麻理が居るから。」 「私が居たってお姉さん何だもん。 関係無いわよ。」
「大いに関係有るよ。」 「そっか。 そこまで私を愛してくれてるのね?」
そこへやっと姉ちゃんが入ってきた。 「そこに有るから。」
「ん。」 なんか朝から微妙な空気が、、、。