「仲がいいの?」
「小学校に入る前から知ってる。家も近いからわざわざ学校で会うことはないんだけど、たまに顔出すんだ。さっきまでいたんだよ」
「……知らなかった」
北条くんから他の友だちの話は聞いたことがなくて、勝手にわたしだけなんだって思ってた。
家の近い幼馴染みがいたっておかしなことじゃないのに、何となく、むっとしてしまう。
それが顔に出てしまっていたのか、北条くんはからかうように笑う。
「ごめんね、教えていなくて」
「いいよ、何でも教えてくれるわけじゃないって、わかってるし」
「ううん、三瀬さんが聞いてくれるなら何でも教えるよ」
笑っているのに、その目はいつも真っ直ぐだ。
ふたりの時間が始まったあの日から、随分と打ち解けたと思う。
聞いていいよ、って北条くんが言うから、躊躇いながら、迷いながら、聞きたいことをかき集めて渡した。
そうしたら、北条くんは本当に全部を答えてくれて、わたしの中に本があるとしたら、北条くんのページは色鮮やかに染染まっていった。
「高取朱那って、わかる? わたしの友だち。この間、少しだけ北条くんのことを話したの。先に言えなくてごめんね」
「高取……わかるよ、小学校が一緒だった」
「放課後、北条くんに会ってるって話したの」
「そうだったんだ。大丈夫だよ、三瀬さんの友だちなら」
北条くんも、わたしに心を許してくれていると思う。
少し深いところまで触れることを、許してくれている。
何でも教えると言いながら、北条くんも最初は少しだけ緊張していた。
放課後の僅かな時間を重ねて、そんな緊張や遠慮は解れていった。




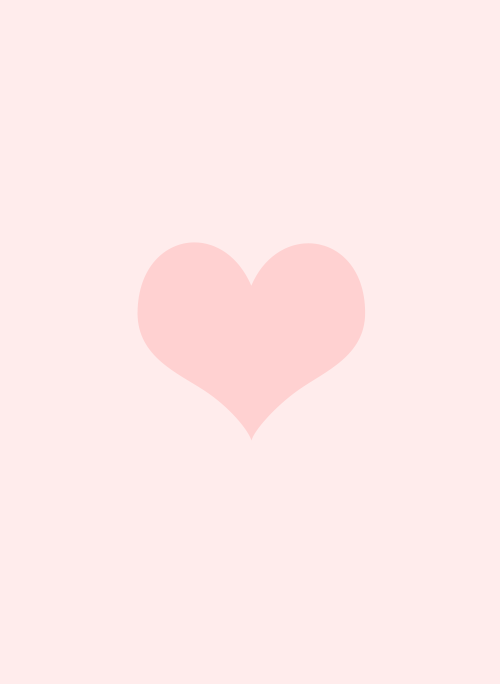
![[短篇集]きみが忘れたむらさきへ。](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.782/img/book/genre99.png)