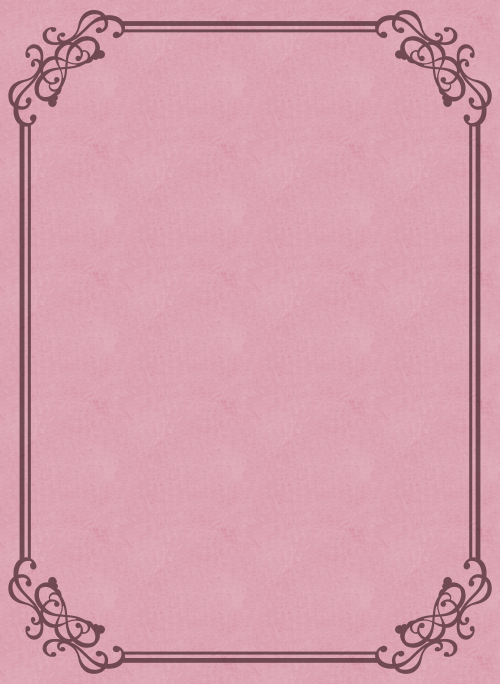半年後。
東京の郊外にある小さなマンション。
飛鳥と遥真は、いま同じ部屋に暮らしていた。
朝の光がレースのカーテンを通して差し込み、部屋の隅々まであたたかく照らしている。
リビングには、観葉植物と脚本の山と、ふたり分のマグカップ。
ソファの上には、昨夜ふたりで選んだクッション。
どれもが、“ふたりの暮らし”を語っていた。
飛鳥は、ダイニングテーブルに広げたノートパソコンの前で、脚本の続きを打ち込んでいた。
リズム良く響くキーボードの音に、生活の気配が溶け込んでいる。
ふと、手が止まる。
「ねえ、恋人がサプライズで料理してくるって、ありだと思う?」
そう言って、後ろを振り向いた飛鳥が見たのは——
キッチンでエプロン姿の遥真が、フライパンをかき混ぜている姿だった。
「それって……僕の話?」
遥真が、少し得意げに微笑む。
エプロンには可愛らしい猫のイラスト。似合っていることが、なんとなく悔しい。
「だって、今日は大事な初回打ち合わせでしょ? せめて、食事くらいは俺がサポートしないと」
「それって、プロデューサー的発言……?」
「専属シェフ兼、応援団です」
ふたりで笑い合う。台本には書かれていない、自然な笑いだった。
「それに……恋人に何かしてあげたいって思うのって、台本関係ないですよね?」
遥真の言葉に、飛鳥は照れくさそうに肩をすくめた。
「そういうの、ちゃんと言える人、ほんとずるい」
「……ちゃんと想った相手には、ちゃんと伝えたいって思うから。飛鳥さんがそういう相手だっただけだよ」
ふたりの間に流れるのは、恋愛ドラマのような劇的な展開ではない。
でも、確かに“物語”があった。
毎日の積み重ねが、ふたりだけのエピソードを育てていく。
“恋の台本”は、もう誰のためでもない。
視聴率のためでも、批評家のためでもない。
ふたりで、笑って、泣いて、恋して、書き直していく未来へ——
飛鳥は再びキーボードに向かい、ふと目を上げて言った。
「ねえ、今夜、先に最終稿読んでもらってもいい?」
「もちろん。読みます。誰よりも先に、読ませてください」
それが、いまの彼の“役目”だった。
いや、“役目”なんかじゃない。
一緒に生きていく人として、当然のこと。
湯気の立つキッチンからは、オムライスのいい香りがしていた。
ふたりの時間は、今日も穏やかに進んでいた。
やがてテーブルに並べられた手作りの食事。
卵の上にはケチャップで描かれた、ぎこちないハートマーク。
「ちょっと曲がってない?」
「それも味です」
ふたりで顔を見合わせて笑った。
それが、日々のなかで積み上がっていく“幸せ”だった。
「ねえ、今度の休み、久しぶりに遠出でもしない?」
食後の紅茶を飲みながら、飛鳥がふと尋ねた。
「いいね。どこ行きたい?」
「海とか。前に、行ってみたいって言ってた場所」
「じゃあ、調べておく。ちゃんと、旅の台本も作っとくよ」
「それ、また本気で作りそうで怖い……」
そんな会話も、どこまでも心地よかった。
誰かのためじゃない。
ふたりのために、ふたりの手で描いていく毎日。
それがいちばんの、物語だった。
東京の郊外にある小さなマンション。
飛鳥と遥真は、いま同じ部屋に暮らしていた。
朝の光がレースのカーテンを通して差し込み、部屋の隅々まであたたかく照らしている。
リビングには、観葉植物と脚本の山と、ふたり分のマグカップ。
ソファの上には、昨夜ふたりで選んだクッション。
どれもが、“ふたりの暮らし”を語っていた。
飛鳥は、ダイニングテーブルに広げたノートパソコンの前で、脚本の続きを打ち込んでいた。
リズム良く響くキーボードの音に、生活の気配が溶け込んでいる。
ふと、手が止まる。
「ねえ、恋人がサプライズで料理してくるって、ありだと思う?」
そう言って、後ろを振り向いた飛鳥が見たのは——
キッチンでエプロン姿の遥真が、フライパンをかき混ぜている姿だった。
「それって……僕の話?」
遥真が、少し得意げに微笑む。
エプロンには可愛らしい猫のイラスト。似合っていることが、なんとなく悔しい。
「だって、今日は大事な初回打ち合わせでしょ? せめて、食事くらいは俺がサポートしないと」
「それって、プロデューサー的発言……?」
「専属シェフ兼、応援団です」
ふたりで笑い合う。台本には書かれていない、自然な笑いだった。
「それに……恋人に何かしてあげたいって思うのって、台本関係ないですよね?」
遥真の言葉に、飛鳥は照れくさそうに肩をすくめた。
「そういうの、ちゃんと言える人、ほんとずるい」
「……ちゃんと想った相手には、ちゃんと伝えたいって思うから。飛鳥さんがそういう相手だっただけだよ」
ふたりの間に流れるのは、恋愛ドラマのような劇的な展開ではない。
でも、確かに“物語”があった。
毎日の積み重ねが、ふたりだけのエピソードを育てていく。
“恋の台本”は、もう誰のためでもない。
視聴率のためでも、批評家のためでもない。
ふたりで、笑って、泣いて、恋して、書き直していく未来へ——
飛鳥は再びキーボードに向かい、ふと目を上げて言った。
「ねえ、今夜、先に最終稿読んでもらってもいい?」
「もちろん。読みます。誰よりも先に、読ませてください」
それが、いまの彼の“役目”だった。
いや、“役目”なんかじゃない。
一緒に生きていく人として、当然のこと。
湯気の立つキッチンからは、オムライスのいい香りがしていた。
ふたりの時間は、今日も穏やかに進んでいた。
やがてテーブルに並べられた手作りの食事。
卵の上にはケチャップで描かれた、ぎこちないハートマーク。
「ちょっと曲がってない?」
「それも味です」
ふたりで顔を見合わせて笑った。
それが、日々のなかで積み上がっていく“幸せ”だった。
「ねえ、今度の休み、久しぶりに遠出でもしない?」
食後の紅茶を飲みながら、飛鳥がふと尋ねた。
「いいね。どこ行きたい?」
「海とか。前に、行ってみたいって言ってた場所」
「じゃあ、調べておく。ちゃんと、旅の台本も作っとくよ」
「それ、また本気で作りそうで怖い……」
そんな会話も、どこまでも心地よかった。
誰かのためじゃない。
ふたりのために、ふたりの手で描いていく毎日。
それがいちばんの、物語だった。