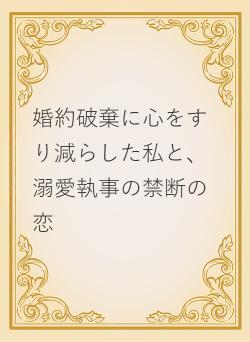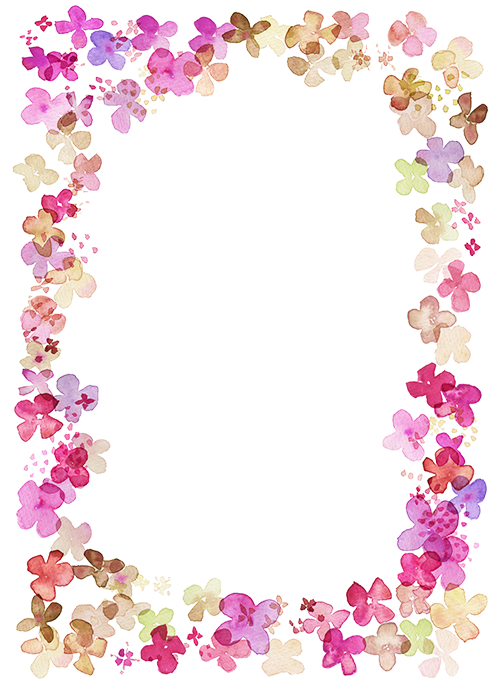すっかり夜になり、宴会場ではたくさんの精霊さんたちが集まっていた。
その中には水神様もいて、精霊さんたちが楽しそうに話している。
人間の姿をしているものの、彼らには頭の上から耳が生えていたり尻尾がはえていた。
すると、桃さんがふすまを開けて宴会場の人々に声をかける。
「さあっ! さあっ! 主役である琴音様のご登場です!」
勢いよく開いたふすまの前に、私は立っていた。
一瞬で注目が私に向く。
(ひえ~! 緊張する……)
精霊さんたちは何も言わずにじっと私を見ている。
(やっぱり変だったんじゃ……)
そう思っていた時、水神様が声をあげた。
「似合ってるじゃないか」
彼と目が合ってしまい、私のほっぺはどんどん熱くなっていく。
「でしょ~!?」
桜さんがえっへんといった様子で誇らしげにしている。
「なんと美しい……」
「ほお~見事じゃ」
そんな言葉が耳に入ってきて、益々私は照れてしまう。
「さ、琴音様のお席は水神様のお隣ですよ~」
桜さんと桃さんに連れられて、彼の隣に座る。
「失礼いたします」
「そんなかたくならなくていい。まずは飲め」
「お酒は……」
「これは水だ。酔いはしない」
「では、いただきます」
私は盃にあった水を一気に飲み干した。
(甘くて、すごく美味しい……)
「これで、お前もこの屋敷の家族だ」
「家族……」
それはなんだか懐かしい響きだった。
(村の皆のことも家族のように思ってたけど、一人じゃないって思えることは嬉しい……)
私は温かい気持ちになっていく。
ご飯も美味しくて、優しい空気が流れている。
(笑顔って、やっぱりいいな……)
宴会が一時間ほど行なわれた後、私は水神様が見当たらないことに気づく。
(どちらに行かれたんだろう……)
私は屋敷の中を探してみる。
すると、縁側で一人座っていらっしゃるのが見えた。
近づいて行ってみると、彼はじっと月を眺めながらお酒を飲んでいた。
「水神様」
少し遠慮がちに彼の斜め後ろに座って声をかけてみた。
お酒がもうないようなので注いで差し上げよう。
そう思った時、水神様に突然腕を引っ張られる。
「わっ!」
「もっと近くにこい」
私は水神様にぴったりくっつく形になる。
心臓がドクンと大きく跳ねた後、顔がどんどん熱くなっていくのを感じた。
宴会場でみんなの前に出た時とは違う、心を鷲掴みにされるようなそんな感覚。
鼓動は速まるばかりで、沈黙に耐えられなかった私は口を開く。
「あ、あのっ! こんな素敵な衣装に、それにお食事や宴会を開いてくださって、ありがとうございました」
「気に入ったか?」
「もちろんです。でも、私なんかがこんな……」
そう口にした時、水神様の細い人差し指が私の唇につけられる。
「『私なんかが』なんていうな。お前はひとを助けられる立派な人間だ。もっと胸を張れ」
「水神様……」
美しい水神様の瞳に吸い込まれそうになる。
彼の整った唇が近づいてきたその時、後ろから声が聞こえた。
「あ~! 水神様が琴音様を口説いてる!」
「あ~! だめ~!!」
桜さんと桃さんが私から水神様を引きはがした。
そうして、ぷんすかという感じで二人は水神様を睨んでいる。
「お前らな……」
呆れる水神様に、やいやいといった様子で桜さんと桃さんが突っかかる。
彼はそんなことも日常茶飯事なのか、うまくあしらっていた。
(なんだか、楽しい……)
私はそう心の中で思っていた。
翌朝になって、私はいつものようにお布団を片付けて、早々に廊下の掃除を始める。
しばらく掃除をしていると、ふと頭上から声を降ってきた。
「何をやっている?」
それはたまたまお通りになった水神様の声だった。
私は急いで頭を下げる。
「あ、申し訳ございません。朝のうちにやっておこうとしたのですが、雑巾をお借りするのに手間取ってしまって……」
「そうじゃない。どうして掃除なんてしている」
「お屋敷でお世話になる以上は何かお役に立たねばと」
私の日常はこうだった。
和泉家で使用人の方と同じお仕事をする。
それが私の生きる立った一つの道。
水神様は私の言葉になんだか納得されたようだった。
そして、私の視線に合わせると一言だけ言う。
「お前を使用人扱いする者はここにはいない。そんなことをしなくていい」
彼はそう言って去って行ってしまう。
「私、やはり水神様に嫌われているのかな……」
「きゅー?」
「いつか、本当に生贄として食べられてしまうのかも」
昨日のことは幻で、一時的な客人扱い。
冥土の土産にいい思いをさせてやろうという最後の計らいかもしれない。
(まさか、ね……)
それから数日が経ち、ようやく私も屋敷の生活に慣れてきた。
桜さんや桃さん、他の使用人さんの方たちとも打ち解けてきて、一緒に料理をしたり、掃除をしたりすることも少なくない。
そんな日々を過ごしていたある日、私は水神様のお部屋の前にいた。
(これでよかったのかしら……?)
呼吸を整え、中に向かって声をかけてみる。
「水神様、琴音です。今、よろしいでしょうか?」
「ああ、入れ」
私が入ってもお忙しいのか、水神様は奥の机に向かって筆をとっている。
そんな彼を邪魔しないように、そっと机の隅にあるものを置いた。
「これは」
「一緒に作りました、桜さんと桃さんと。水神様がお好きと聞いて」
それはいちご大福だった。
(水神様のお好きなものを聞いたら、すごくきらきらした目で教えてくれたのよね。なぜかすごく嬉しそうにしてたけれど……)
「なぜ?」
どうしてこれを自分に、いった様子で水神様は私に尋ねた。
「先日歓迎会を開いていただいたお礼です。私、あんな賑やかで楽しいこと初めてでした。すごく嬉しくて、心が躍って……まるで天国みたいでした」
水神様は私の言葉に静かに耳を傾けている。
(そう、だから……)
私は覚悟をもって言う。
「ですから、どうぞ生贄として食べてください」
その中には水神様もいて、精霊さんたちが楽しそうに話している。
人間の姿をしているものの、彼らには頭の上から耳が生えていたり尻尾がはえていた。
すると、桃さんがふすまを開けて宴会場の人々に声をかける。
「さあっ! さあっ! 主役である琴音様のご登場です!」
勢いよく開いたふすまの前に、私は立っていた。
一瞬で注目が私に向く。
(ひえ~! 緊張する……)
精霊さんたちは何も言わずにじっと私を見ている。
(やっぱり変だったんじゃ……)
そう思っていた時、水神様が声をあげた。
「似合ってるじゃないか」
彼と目が合ってしまい、私のほっぺはどんどん熱くなっていく。
「でしょ~!?」
桜さんがえっへんといった様子で誇らしげにしている。
「なんと美しい……」
「ほお~見事じゃ」
そんな言葉が耳に入ってきて、益々私は照れてしまう。
「さ、琴音様のお席は水神様のお隣ですよ~」
桜さんと桃さんに連れられて、彼の隣に座る。
「失礼いたします」
「そんなかたくならなくていい。まずは飲め」
「お酒は……」
「これは水だ。酔いはしない」
「では、いただきます」
私は盃にあった水を一気に飲み干した。
(甘くて、すごく美味しい……)
「これで、お前もこの屋敷の家族だ」
「家族……」
それはなんだか懐かしい響きだった。
(村の皆のことも家族のように思ってたけど、一人じゃないって思えることは嬉しい……)
私は温かい気持ちになっていく。
ご飯も美味しくて、優しい空気が流れている。
(笑顔って、やっぱりいいな……)
宴会が一時間ほど行なわれた後、私は水神様が見当たらないことに気づく。
(どちらに行かれたんだろう……)
私は屋敷の中を探してみる。
すると、縁側で一人座っていらっしゃるのが見えた。
近づいて行ってみると、彼はじっと月を眺めながらお酒を飲んでいた。
「水神様」
少し遠慮がちに彼の斜め後ろに座って声をかけてみた。
お酒がもうないようなので注いで差し上げよう。
そう思った時、水神様に突然腕を引っ張られる。
「わっ!」
「もっと近くにこい」
私は水神様にぴったりくっつく形になる。
心臓がドクンと大きく跳ねた後、顔がどんどん熱くなっていくのを感じた。
宴会場でみんなの前に出た時とは違う、心を鷲掴みにされるようなそんな感覚。
鼓動は速まるばかりで、沈黙に耐えられなかった私は口を開く。
「あ、あのっ! こんな素敵な衣装に、それにお食事や宴会を開いてくださって、ありがとうございました」
「気に入ったか?」
「もちろんです。でも、私なんかがこんな……」
そう口にした時、水神様の細い人差し指が私の唇につけられる。
「『私なんかが』なんていうな。お前はひとを助けられる立派な人間だ。もっと胸を張れ」
「水神様……」
美しい水神様の瞳に吸い込まれそうになる。
彼の整った唇が近づいてきたその時、後ろから声が聞こえた。
「あ~! 水神様が琴音様を口説いてる!」
「あ~! だめ~!!」
桜さんと桃さんが私から水神様を引きはがした。
そうして、ぷんすかという感じで二人は水神様を睨んでいる。
「お前らな……」
呆れる水神様に、やいやいといった様子で桜さんと桃さんが突っかかる。
彼はそんなことも日常茶飯事なのか、うまくあしらっていた。
(なんだか、楽しい……)
私はそう心の中で思っていた。
翌朝になって、私はいつものようにお布団を片付けて、早々に廊下の掃除を始める。
しばらく掃除をしていると、ふと頭上から声を降ってきた。
「何をやっている?」
それはたまたまお通りになった水神様の声だった。
私は急いで頭を下げる。
「あ、申し訳ございません。朝のうちにやっておこうとしたのですが、雑巾をお借りするのに手間取ってしまって……」
「そうじゃない。どうして掃除なんてしている」
「お屋敷でお世話になる以上は何かお役に立たねばと」
私の日常はこうだった。
和泉家で使用人の方と同じお仕事をする。
それが私の生きる立った一つの道。
水神様は私の言葉になんだか納得されたようだった。
そして、私の視線に合わせると一言だけ言う。
「お前を使用人扱いする者はここにはいない。そんなことをしなくていい」
彼はそう言って去って行ってしまう。
「私、やはり水神様に嫌われているのかな……」
「きゅー?」
「いつか、本当に生贄として食べられてしまうのかも」
昨日のことは幻で、一時的な客人扱い。
冥土の土産にいい思いをさせてやろうという最後の計らいかもしれない。
(まさか、ね……)
それから数日が経ち、ようやく私も屋敷の生活に慣れてきた。
桜さんや桃さん、他の使用人さんの方たちとも打ち解けてきて、一緒に料理をしたり、掃除をしたりすることも少なくない。
そんな日々を過ごしていたある日、私は水神様のお部屋の前にいた。
(これでよかったのかしら……?)
呼吸を整え、中に向かって声をかけてみる。
「水神様、琴音です。今、よろしいでしょうか?」
「ああ、入れ」
私が入ってもお忙しいのか、水神様は奥の机に向かって筆をとっている。
そんな彼を邪魔しないように、そっと机の隅にあるものを置いた。
「これは」
「一緒に作りました、桜さんと桃さんと。水神様がお好きと聞いて」
それはいちご大福だった。
(水神様のお好きなものを聞いたら、すごくきらきらした目で教えてくれたのよね。なぜかすごく嬉しそうにしてたけれど……)
「なぜ?」
どうしてこれを自分に、いった様子で水神様は私に尋ねた。
「先日歓迎会を開いていただいたお礼です。私、あんな賑やかで楽しいこと初めてでした。すごく嬉しくて、心が躍って……まるで天国みたいでした」
水神様は私の言葉に静かに耳を傾けている。
(そう、だから……)
私は覚悟をもって言う。
「ですから、どうぞ生贄として食べてください」