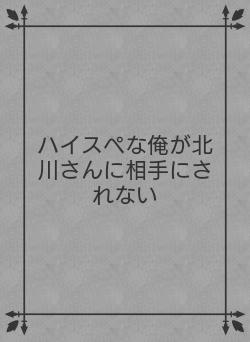「君ら、いつからそんな
連携するようになったの?!」
太陽が驚きながらそう言った。
確かに家政婦にあんなこと
すべきじゃないけど、
雷も朔も厳しすぎるんじゃない?
まぁ、今までこういうことで
他にもいろいろあったんだろうけど…
って、悠長に考えてる場合ではない!
隙をみて私はこっそり抜けなければ。
でも突然消えたらさすがに心配されるし、
スマホにメッセージ入れとこ。
『急用で戻るね』
三つ子たちがいざこざしている反対側のドアからそっと降りると
裸足でコンビニの駐車場を横断する。
夏のアスファルトは火傷しそうなくらい熱かった。
「あっあっ!あっつ!」
と小声で言いながら、
私に気づかない三つ子を
チラチラ確認しつつフェードアウトする。
「だから!
あいつは家政婦っつってんだろ!
セフレ候補じゃねンだよ!」
「そんな風に思ってないから。
こんなのコミュニケーションでしょう?」
「この人の感覚おかしすぎます」
三つ子たちの声は遠ざかり、
私は住宅街へ入った。
車道の横だと皆に見られて恥ずかしいからね。
「あっつ!あっつ!死ぬー!」
足の裏は焼けそうで熱いし、
身体は干からびそう…
でも、早く戻らないと!
履き物はあのサンダル一足しか持ってないから、
盗れたらまずい!