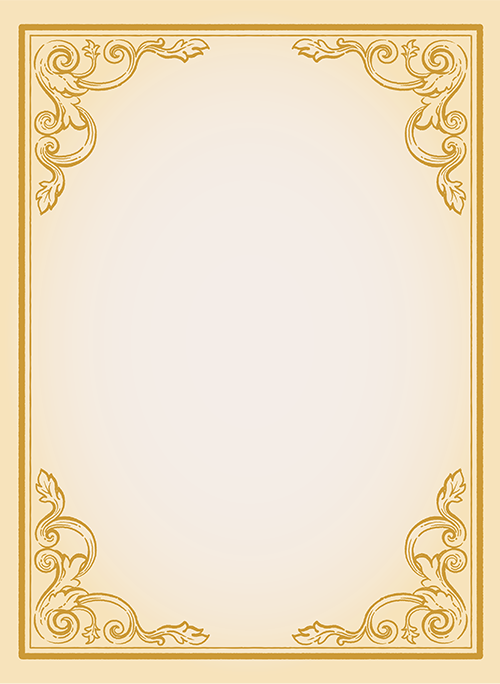セスは約束通り、次の日には、私に車椅子を与え、監禁していた部屋から出ることを許してくれた。
最初こそ、セス同伴の元、屋敷内を散策していた私だったが、いつしかセスは私が1人でも屋敷内を散策することを許すようになり、もう屋敷内だけなら私は自由に動くことができていた。
「綺麗だねぇ。この花はなんていう花なの?珍しい色だけど」
セスに車椅子を押されながら、私は屋敷の庭に咲く花々に感嘆の声をあげる。
レンガの道を囲むように咲き誇る花は見たことのない見た目をしており、色も不思議な色をしていた。
例えばあそこの紫色の花。あの花の紫はただの紫ではない。青みや赤みを帯びる紫がグラデーションのように混じり、何故か薄くキラキラと輝いて見える。
どの花もあの紫の花のように、一概にこの色だと言い切れないような色をしており、キラキラと輝いていた。
「こちらはライトという魔法花なのですが、どの花も輝く魔法薬を使用して育てられており、この屋敷にのみ生息する花なんです」
「へぇ…。魔法薬でキラキラしているんだね」
「はい。ライトという魔法花ですが、魔法薬で改良しているので、厳密にはライトではございません。アナタの為に育てた花なので、ステラ、と名付けるのいかがでしょう?」
「え!?ステラ!?」
突然何でもないようにとんでもない提案をするセスに思わず驚き、後ろを振り向く。
するとセスはお昼時の柔らかい日差しを浴びて、それはもう愛おしそうに私をまっすぐと見つめていた。
とても気恥ずかしくなる慣れることのできない視線だ。そんなにも愛おしげに見られると恥ずかしさで溶けてしまう。