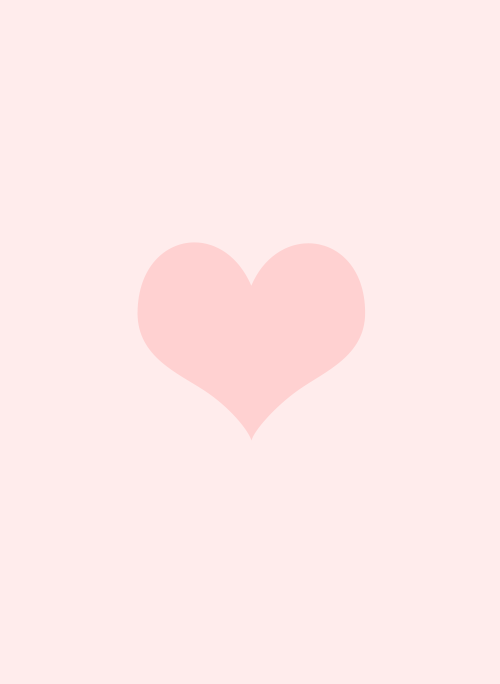が、気を取り直したように尚輝を見た彩は
「そう。まぁ、どうでもいいけど、弓道を甘く見ないで。」
厳しい口調で言う。
「先輩・・・。」
「君、中学時代部活は?」
「硬式テニス部でした。」
「フーン、一応運動部経験者なんだ。」
「はい。」
「でも女子と一緒だから、チャラチャラと出来ると思ったら、大間違いだから。やってみればわかるけど、弓を引くのにだって、結構な力がいるんだから。まぁ弓道はテニスと違って、なかなかやれる場所も少ないし、中学で弓道部がある学校もほとんどないから、みんなほぼ初心者なんで、その点は安心してもらっていいけど、とりあえず、夏休みに入るくらいまでは、筋トレや基礎練習がメインだから。そのつもりで。」
「はい、ありがとうございます。」
「それじゃ、お疲れ。」
そう言って、歩き出そうとする彩に
「あっ先輩、このあと僕とお茶しませんか?」
と誘いをかける尚輝。だが
「無理。」
と言い捨てるように言うと、彩はそのまま歩き去って行った。
翌日、登校した尚輝に、クラスメイトの西川秀が声を掛けて来た。
「で、脈はありそうなのかよ。」
「そんなのまだわかんねぇよ。」
からかい気味の秀の言葉に、尚輝はややぶっきらぼうに答える。
「それにしても、入学してひと月も経たないうちに、いきなり2年生の教室に乗り込んで、コクって玉砕したと思ったら、全くめげないで、すぐに興味の欠片もない部活に、その先輩に近づきたい一心で飛び込み入部するとはな。大した行動力だ。」
と言った秀の口調は感心してるというよりは、呆れがこもっていた。
「『中学の部活は、内申点上げる為に、嫌々やってただけ。高校に入ったら部活なんかに時間取られないで、思いっきり遊びまわる』って言って、部活のオリエンテ-ションの間、ずっと寝てた奴とは、とても思えねぇよ。」
「居ても立ってもいられねぇんだよ。」
「えっ?」
「とにかく、寝ても覚めても、あの人のことが頭に浮かんで来て、胸が苦しくなるんだ。この自分を気持ちを、先輩に伝えられずにはいられない。先輩に好きな奴がいようと、彼氏がいようと、そんなの関係ない。とにかく俺のハートは一瞬で、先輩に撃ち抜かれたんだ。もうこの気持ちは抑えられねぇ。」
周囲の視線も気にせず、そう熱く語る尚輝。
「なるほどねぇ・・・。」
そんな尚輝の熱量に、秀はやや押され気味に答える。
「そう。まぁ、どうでもいいけど、弓道を甘く見ないで。」
厳しい口調で言う。
「先輩・・・。」
「君、中学時代部活は?」
「硬式テニス部でした。」
「フーン、一応運動部経験者なんだ。」
「はい。」
「でも女子と一緒だから、チャラチャラと出来ると思ったら、大間違いだから。やってみればわかるけど、弓を引くのにだって、結構な力がいるんだから。まぁ弓道はテニスと違って、なかなかやれる場所も少ないし、中学で弓道部がある学校もほとんどないから、みんなほぼ初心者なんで、その点は安心してもらっていいけど、とりあえず、夏休みに入るくらいまでは、筋トレや基礎練習がメインだから。そのつもりで。」
「はい、ありがとうございます。」
「それじゃ、お疲れ。」
そう言って、歩き出そうとする彩に
「あっ先輩、このあと僕とお茶しませんか?」
と誘いをかける尚輝。だが
「無理。」
と言い捨てるように言うと、彩はそのまま歩き去って行った。
翌日、登校した尚輝に、クラスメイトの西川秀が声を掛けて来た。
「で、脈はありそうなのかよ。」
「そんなのまだわかんねぇよ。」
からかい気味の秀の言葉に、尚輝はややぶっきらぼうに答える。
「それにしても、入学してひと月も経たないうちに、いきなり2年生の教室に乗り込んで、コクって玉砕したと思ったら、全くめげないで、すぐに興味の欠片もない部活に、その先輩に近づきたい一心で飛び込み入部するとはな。大した行動力だ。」
と言った秀の口調は感心してるというよりは、呆れがこもっていた。
「『中学の部活は、内申点上げる為に、嫌々やってただけ。高校に入ったら部活なんかに時間取られないで、思いっきり遊びまわる』って言って、部活のオリエンテ-ションの間、ずっと寝てた奴とは、とても思えねぇよ。」
「居ても立ってもいられねぇんだよ。」
「えっ?」
「とにかく、寝ても覚めても、あの人のことが頭に浮かんで来て、胸が苦しくなるんだ。この自分を気持ちを、先輩に伝えられずにはいられない。先輩に好きな奴がいようと、彼氏がいようと、そんなの関係ない。とにかく俺のハートは一瞬で、先輩に撃ち抜かれたんだ。もうこの気持ちは抑えられねぇ。」
周囲の視線も気にせず、そう熱く語る尚輝。
「なるほどねぇ・・・。」
そんな尚輝の熱量に、秀はやや押され気味に答える。