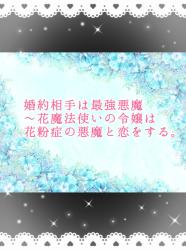柊と剛は窓の外の雪景色を眺めながら、静かに会話を交わす。
「剛さん、僕たちがこのカフェで逢いたいと思っている景色って、どんな景色なんでしょう」
剛は考え込み、遠くを見るような目をした。
「俺の場合は、妹の若菜ともう一度会って……ただきちんと向き合いたい、かな。自分勝手に生きてきたくせに、いなくなってから向き合いたいとか、そう思うのも、自分勝手すぎるけど。まぁ、もういない人と過ごすのは無理だけどな」
剛は静かにため息をついた。
柊は窓の外の雪を見つめながら、母の声が聞こえてくる幻を想像した。『柊、大好きだよ』と。
――あの温かい言葉が、今も耳の奥に残っている。もしも母がここにいて、剛さんと一緒に今、笑顔で食事ができたなら……。
「僕ももう一度、母に逢いたいです。生きていた時みたいに、母と一緒にただご飯を食べながら、笑い合いたい――」
しばらくすると、優里がオムライスをトレイに乗せ、テーブルに近づいてきた。トレイの中には鶏出汁のキャベツスープとアップルパイ、コーヒーも一緒に乗せてある。それらがテーブルに並んだ。
香ばしいケチャップの香りやスープの温かい湯気が店内に広がっていく。完璧に仕上げられた料理を眺めると、柊と剛の顔に自然と笑みが浮かんだ。
「見た目、剛さんが作ったのと似ていて……美味しそう。いただきます!」
「剛さん、僕たちがこのカフェで逢いたいと思っている景色って、どんな景色なんでしょう」
剛は考え込み、遠くを見るような目をした。
「俺の場合は、妹の若菜ともう一度会って……ただきちんと向き合いたい、かな。自分勝手に生きてきたくせに、いなくなってから向き合いたいとか、そう思うのも、自分勝手すぎるけど。まぁ、もういない人と過ごすのは無理だけどな」
剛は静かにため息をついた。
柊は窓の外の雪を見つめながら、母の声が聞こえてくる幻を想像した。『柊、大好きだよ』と。
――あの温かい言葉が、今も耳の奥に残っている。もしも母がここにいて、剛さんと一緒に今、笑顔で食事ができたなら……。
「僕ももう一度、母に逢いたいです。生きていた時みたいに、母と一緒にただご飯を食べながら、笑い合いたい――」
しばらくすると、優里がオムライスをトレイに乗せ、テーブルに近づいてきた。トレイの中には鶏出汁のキャベツスープとアップルパイ、コーヒーも一緒に乗せてある。それらがテーブルに並んだ。
香ばしいケチャップの香りやスープの温かい湯気が店内に広がっていく。完璧に仕上げられた料理を眺めると、柊と剛の顔に自然と笑みが浮かんだ。
「見た目、剛さんが作ったのと似ていて……美味しそう。いただきます!」