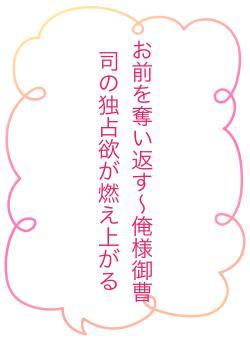「そう言う訳にはいきません、社長に奢って頂く理由がありません」
「それなら、今日は俺がつぐみをデートに誘ったことにすればいい」
急につぐみと呼ばれて、ドクンと胸が高鳴った。
さっきまで、振られて涙していたのに、自分が情けなくなってきた。
「俺が勝手にオーダーするよ、食べられないものとかある?」
「あっ、いえありません」
光高は慣れた感じで、次々とオーダーをした。
「ごめん、どうしても気になって、聞いてもいいかな」
つぐみは何を聞かれるのだろうと不安になった。
「なんでしょうか」
「さっき、泣いてた理由が知りたい、でもどうしても話したくないなら、いいんだ」
「大丈夫です」
つぐみは話始めた。
「五年付き合った彼に振られちゃったんです」
「そうだったんだ」
「二年も二股掛けられて、気づかない私も私ですけど、好きな女の子が出来たとかで、もう笑っちゃいますよね」
「それなら、今日は俺がつぐみをデートに誘ったことにすればいい」
急につぐみと呼ばれて、ドクンと胸が高鳴った。
さっきまで、振られて涙していたのに、自分が情けなくなってきた。
「俺が勝手にオーダーするよ、食べられないものとかある?」
「あっ、いえありません」
光高は慣れた感じで、次々とオーダーをした。
「ごめん、どうしても気になって、聞いてもいいかな」
つぐみは何を聞かれるのだろうと不安になった。
「なんでしょうか」
「さっき、泣いてた理由が知りたい、でもどうしても話したくないなら、いいんだ」
「大丈夫です」
つぐみは話始めた。
「五年付き合った彼に振られちゃったんです」
「そうだったんだ」
「二年も二股掛けられて、気づかない私も私ですけど、好きな女の子が出来たとかで、もう笑っちゃいますよね」