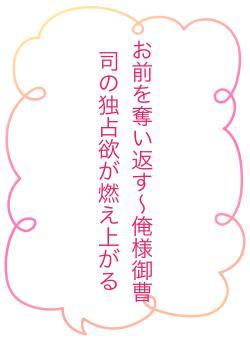ホームと反対側のドアのところにいたつぐみは押しつぶされそうになった。
柿崎は手すりに捕まり、つぐみを囲う態勢を取ってくれた。
「つぐみ、大丈夫か」
「うん、大丈夫」
柿崎の腕の中にすっぽり入って、ぎゅっと抱きしめられた形になった。
つぐみは不思議だった。
柿崎から別れを告げられて、あんなに落ち込んだのに、今はぎゅっと抱きしめられているのに何も感じない。
(私、光高さんが好き)
光高はそんなつぐみの気持ちを知らずに、柿崎に嫉妬していた。
不安が押し寄せてきて、居ても立っても居られない。
(俺はなんて情けないんだ)
電車は三時間後、最寄りの駅に到着した。
(光高さん、心配してるかな)
柿崎はつぐみに声をかけようとすると、つぐみはスマホを取り出して光高に電話しようとしていた。
その手を掴んで引き寄せた。
「えっ、正臣」
柿崎は手すりに捕まり、つぐみを囲う態勢を取ってくれた。
「つぐみ、大丈夫か」
「うん、大丈夫」
柿崎の腕の中にすっぽり入って、ぎゅっと抱きしめられた形になった。
つぐみは不思議だった。
柿崎から別れを告げられて、あんなに落ち込んだのに、今はぎゅっと抱きしめられているのに何も感じない。
(私、光高さんが好き)
光高はそんなつぐみの気持ちを知らずに、柿崎に嫉妬していた。
不安が押し寄せてきて、居ても立っても居られない。
(俺はなんて情けないんだ)
電車は三時間後、最寄りの駅に到着した。
(光高さん、心配してるかな)
柿崎はつぐみに声をかけようとすると、つぐみはスマホを取り出して光高に電話しようとしていた。
その手を掴んで引き寄せた。
「えっ、正臣」