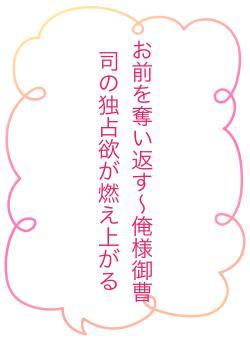「私がソファで寝ます」
つぐみが透かさず言葉を発した。
「何言ってるんだ、俺がソファ使うから、つぐみは俺の寝室のベッドを使え」
「そんなこと出来ません」
「それならベッドで一緒に寝るか」
つぐみは顔を真っ赤に染めて俯いた。
「決まりな、一緒に寝よう」
(無理だよ、でも私少し期待してるかも、さっきのキスであんなにドキドキしちゃって
その先ってどうなっちゃうんだろう)
ベッドに入ると、中々寝付けない。
ベッドはキングサイズもあるから、二人の距離は遠い。
つぐみは元恋人と二年もの間何もない状態だった。
二十七歳にもなって、全く潤う事もなく、キスだけであんなにもドキドキしてしまった。
光高は憧れの存在だ。
かっこよくて、頼りがいがあって、食事を一緒に出来るだけでも嬉しいのに、キスしちゃうなんて……
だから、光高が自分に五年も片思いしていたなんて、考えられないことだった。
「もう寝たか」
つぐみが透かさず言葉を発した。
「何言ってるんだ、俺がソファ使うから、つぐみは俺の寝室のベッドを使え」
「そんなこと出来ません」
「それならベッドで一緒に寝るか」
つぐみは顔を真っ赤に染めて俯いた。
「決まりな、一緒に寝よう」
(無理だよ、でも私少し期待してるかも、さっきのキスであんなにドキドキしちゃって
その先ってどうなっちゃうんだろう)
ベッドに入ると、中々寝付けない。
ベッドはキングサイズもあるから、二人の距離は遠い。
つぐみは元恋人と二年もの間何もない状態だった。
二十七歳にもなって、全く潤う事もなく、キスだけであんなにもドキドキしてしまった。
光高は憧れの存在だ。
かっこよくて、頼りがいがあって、食事を一緒に出来るだけでも嬉しいのに、キスしちゃうなんて……
だから、光高が自分に五年も片思いしていたなんて、考えられないことだった。
「もう寝たか」