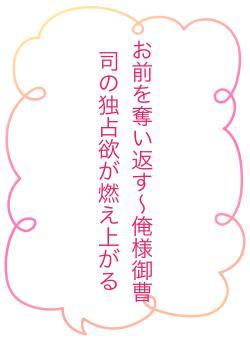「光高さん、泊まる必要ありますか」
「つぐみはお前を振った元恋人のうちに泊まらなかったのか」
「泊まりました、と言うより、一緒に暮らしていました」
つぐみの言葉に光高の表情がパッと輝いた。
「そうだ、ここに引っ越してこい」
「はあ?」
「もしかして、母親が突然やってくるかもしれない」
(いやいや、ありえないでしょ)
ところが、次の瞬間、インターホンが鳴った。
光高とつぐみは顔を見合わせた。
光高はインターホンに対応した。
「光高さん、開けてちょうだい」
光高の予想通り、母親だった。
母親は遠慮せず、ずかずかと部屋に入ってきた。
「あら、居たのね、もしかしてカムフラージュかと思ったけど違ったみたいね」
つぐみはこくりと息をのんだ。
(確かめにきたんだ、危なかった、あのまま、アパートに帰っていたら何を言われるか)
「つぐみはお前を振った元恋人のうちに泊まらなかったのか」
「泊まりました、と言うより、一緒に暮らしていました」
つぐみの言葉に光高の表情がパッと輝いた。
「そうだ、ここに引っ越してこい」
「はあ?」
「もしかして、母親が突然やってくるかもしれない」
(いやいや、ありえないでしょ)
ところが、次の瞬間、インターホンが鳴った。
光高とつぐみは顔を見合わせた。
光高はインターホンに対応した。
「光高さん、開けてちょうだい」
光高の予想通り、母親だった。
母親は遠慮せず、ずかずかと部屋に入ってきた。
「あら、居たのね、もしかしてカムフラージュかと思ったけど違ったみたいね」
つぐみはこくりと息をのんだ。
(確かめにきたんだ、危なかった、あのまま、アパートに帰っていたら何を言われるか)