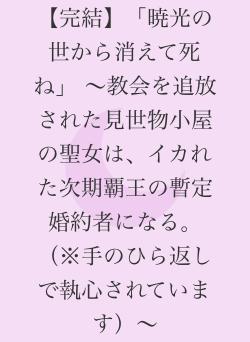「はい、ただ今戻りました」
「そう。随分と早いのね」
鈴蘭と同じクリーム色の髪を束ね、気品ある洋服を着た人は……私と鈴蘭の母。
お母さんは私から視線を逸らし、辺りを見回して疑問を口にする。
「鈴蘭は一緒ではないの?」
「はい。まだ学園に残っています」
「そう、ならいいわ」
それだけ聞くとお母さんは眉をわずかにピクリとさせ、私が来た廊下を静かに歩いて行ってしまった。
こつこつと絨毯に吸収されたような足音が辺りに響き渡る。
その音は徐々に、聞こえなくなっていった。
「……はあ」
ピリッとした空気から解放され、私の唇からは無意識に息がこぼれる。
本当に、あの空気には陰の気でも含んでいるんじゃないかってくらい恐ろしい。
鈴蘭がいるといないとじゃ、まったく雰囲気が違うんだもんな。
私の前では怖い顔のお母さんでも、鈴蘭がいればべつ。たちまち笑顔の花が咲く。
学園の生徒会の人たち同様、お母さんはなによりも鈴蘭を大切にしている。
私は、完全にお母さんに嫌われているけど。
理由は、まあ……私が落ちこぼれだからで。そのうえ見た目もこんな不気味で自分の娘だと思いたくないんだろう。
そりゃそうだよね。自分の子供が出来損ないって馬鹿にされているんだから。
「……さ、行こ」
お母さんの後ろ姿が曲がり廊下で消えるのを確認し、私も自室へと足を動かした。
二階の一番端の部屋、そこが私の部屋。
周りの部屋はすべてゲストルームで、隣の部屋も同じなので人はいない。
この部屋を選んだ理由は、家の中心から一番遠退いた位置に存在するから。
あとは、丸いガラスの天窓が気に入ってる。
「ふう……」
部屋に入った私は、柔らかなソファに腰を下ろしてまたもやため息をつく。
ドレッサーに移動し、鬱陶しい前髪を思いっきり上にあげてピンで固定した。
「……ああああ! つっかれたぁ!! はあああああ」
じつはこの部屋を選んだ最大の理由は、大声を出しても周りに気づかれる心配がないから、ということです。
*カエルの子、帰宅する*