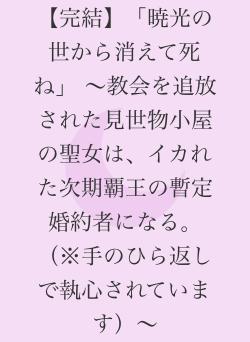静かなエンジン音。本日三度目の車内だ。
車の窓から差し込む光は、オレンジ色に輝いて夕刻の景色を作り上げていた。
たぶん鈴蘭は今日も生徒会室で手伝いをしているはず。
まだ正式な役員ではないらしいけど、生徒会補佐に欠員が出ているみたいだから近々そこに入るのだろう。いや、もう補佐になっているのかな。
でも、あまり帰りが遅くなるようならいろいろと心配だ。
いつどこに、危険があるかはわからない。
暗くなると……いろいろ、狙われやすいから、ね。
「つぼみお嬢様、到着いたしました」
「え? あ、ああ……ありがとうございます」
ハッと我に返った私は、窓の外を見てすでに車が学園内に入っていることに気がついた。
帰宅時間が被った校内には、ほかにも送迎の車が停車している。よく見てみるとほとんどが高級車だ。
「鈴蘭お嬢様は……見あたらないようですね」
「そうみたいですね。とりあえず私は教室に向かいます。途中で鈴蘭を見かけたらこちらに連れて来ますので」
「お手を煩わせて、申し訳ありません」
鈴木さんは眉尻を下げると、申し訳なさそうな表情を浮かべた。
私も忘れ物を取りに来たから、お礼を言われるほどでもないんだけどね。
車を降りて校舎内に入り、何度か生徒とすれ違いながら、私は教室へと足を進める。
すれ違う生徒たちの視線がいつにも増して強いと思ったけど。
ああ、そういえば私服で家を出ちゃったんだ。うっかりしてた。
私は悪目立ちしないようにそそくさと教室の隣にあるロッカールームに入る。室内は薄暗く、壁に手をつきながら自分の場所まで移動した。
「あった、よかった」
ギィと鈍い音を立てたロッカーに入っていたのは、真っ白な手のひらサイズの手帳。
体育以外は肌身離さず持っている物で、側にないと落ち着かない。
「……中も、大丈夫だ」
私は手帳を開いて確認し、口元に笑み浮かべると、それをポケットにしまってロッカールームを後にした。
駐車場に戻ろうとしたとき、ふいに視界の端が灯りが見えて窓の外に顔を向ける。
「あれは、生徒会室?」
窓からは、隣の棟にある生徒会室が見えた。
閉まったカーテンを通して、明かりがはっきりと確認できるということは……。
もしかして鈴蘭は、まだ生徒会室にいるの?
鈴木さんも待たせてるし、帰宅時間に気づいていないのかな。
「……面倒だけど、仕方ないかぁ」
私はほんの少しだけため息を吐き、明かりに誘われるように生徒会室へと足を向けた。