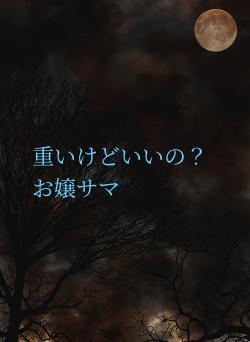「──あーあ、なんか周りの目が痛い」
「んなもん時間が経てばなんとかなんだろ」
「そういうもんか?」
「そういうもんだ。それより俺は、学校もばあちゃんも皆森の女将からも公認の付き合いで清々しいくらいだ」
「……よくそんなこと言えるな」
騒ぎがおさまるまでのことを考えると、胃が痛くなりそうだぞ私は。
今でさえなんだか居心地が悪い気がしてるって言うのに。
「だってそうだろ?こんだけ大々的に言っときゃ、お前に手ェ出そうなんて思わないだろうし、悪い虫もつかねぇ。いい牽制になるぜ」
……よくもまぁ、そんな言葉をすらすらと。
その言葉が自分に言われているって分かるから……顔が熱くなってきてる気がしなくもない。
「牽制をするほど、私はモテやしないっての。次期女将だって、旅館や学校では品よくしてるように見せてるけど、実際はずぼらでこんなんだから」
「別にいーじゃねぇか。そんなお前のことが好きだって言う男が、ここにいんだからよ。俺からモテりゃ十分だろうが」
ちげぇのかよ、なんて貴公子は聞いてくるけど、聞いたわりに顔は自信に溢れていて。
「ふふっ、違わねぇ」
「だろ?」
笑顔で返せば、貴公子も満足気に笑った。