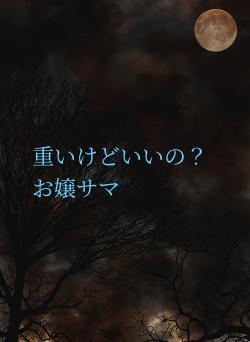「私も……まあまあ好きって言っとく。どっちの貴公子もことも」
そっと同じように震える手で、指輪を手のひらの中におさめれば、
「はぁ……こういうの、柄じゃねぇんだよっ……ほんとに!あー!安心したわ!!マジで!」
頭を掻き、しゃがみこむ貴公子。
貴公子とはちょっと違うかもだけど、人生の中で一、二をあらそう緊張感だった……。
「……みなもりー」
気の抜けた声で私を呼ぶ貴公子は、私を見上げながらまた手を伸ばしてきた。
だからぎこちなく、握ってみると、
「わっ!?」
下へと引かれ、隣にしゃがませられる。
「……近い」
「いいじゃねぇか、もう俺のだからな。……っていつもみたいに振る舞ってみたけど、やっぱ無理っぽいわ。顔あちぃし、心臓うるせぇからよ」
「わかる」
「だから、おさまるまでもう少しここにいようぜ」
「……おう」
恥ずかしいだの、熱いだの、言いながら私たちは日が暮れるまで一緒に過ごした──