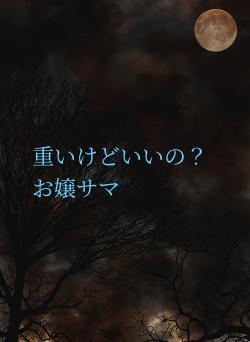「っ……わ、私がお世辞を言ってるとか思わなかったの?」
「思わなかった。……ご機嫌取りのお世辞なんか腐るほど聞いてきたからな。だから……いつの間にか、綺麗だって褒められても何も感じなくなってたんだ」
なのに、と貴公子は続けた。
「お前が俺の花を綺麗だって言った時は、そいつらが言ってた言葉と同じはずなのに……まっすぐ届いて、すげぇ嬉しかった」
貴公子は片胸に手を添えながら、くしゃりと笑うと立ち上がり、私の手をとった。
「そん時、お前に惚れた」
「……っ!」
「でもお前、全然気付いてる感じしねぇし、噂をあしらいながら当分は、片想いにでも浸ってようと思ってたんだけど……だめだったわ」
今度は困ったように笑うから、つい覗き込みそうになる。
「お前が記者に言った言葉全部で、俺が自分の中で伸ばした片想い期間ぶっ壊して来やがった」
「え?どういうこと?」
ぶっ壊したって──