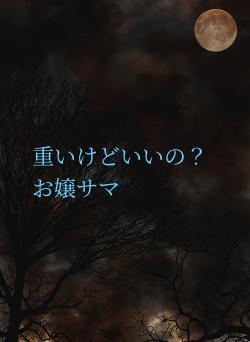「お前が真顔で言うからだろうが。……この子供たちは、ばあちゃんの華道教室に通う母親たちの子供だ。たまにこうやって遊んでやってるんだよ」
「……へぇ」
意外と面倒見良かったりするのかな。
「あん時の絆創膏は、子供のために持ってたやつがたまたま残ってたってだけだからな」
「ああ、ピンクのうさぎ柄のやつね」
「柄を言うな」
絆創膏の話題を出すってことは、まだそのこと気にしてたってこと?
だとしたら、意外とかわいらしい一面やもしれない。
「誰ー?」
パタパタと追いかけっこをしていた子供たちが、私に気付いて走ってきて、不思議そうに首をかしげる。
「お姉ちゃんの着物かわいー」
「つばさが女の子といる……あ、わかった!つばさの彼女だぁっ!」
「は!?バッ……お前ら、そんなこと言いながら走り回んな!」
私を指して彼女と連呼して、再び走り回り出す子供たち。それを止めようと、和装だってこと忘れてるのかって思うような走り方をする貴公子。
「彼女!かのじょっ!つっばさに彼女!」
「ちげっ……違うっての!」
それから、貴公子は散々彼女だと騒ぐ子供たちを掴まえて、大人しくさせるのに時間を要した。