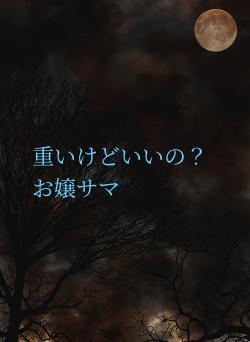「……なんて、生け花の成績がギリギリの人間に言われても、嬉しくなんかないかもしんないけどさ」
自虐的に笑ったけど、相槌も何も返ってこなくて。
「貴公子?」
目を見開いたまま固まる貴公子の前に、手をかざせば、貴公子はハッとして瞬きをした。……わりぃ、と。
「俺さ……華道界の貴公子って言われはじめた当初、同じ業界の人間の話してる言葉が聞こえてきたんだ。俺の生ける花に……"色がない"って」
「色?」
「要は……俺の花を見ても、何も感じないってことだ。いくら情熱的な表現をしても、儚げな表現をしても」
貴公子は顔を歪ませる。
「なのに、ばあちゃんといる俺の前では、綺麗だの有望だの、微塵も思ってないことべらべらぬかしやがって……」
悲しみにも怒りともとれる表情は、私を見るなり嘘のように和らいぎ、貴公子は柔和な笑みを浮かべた。
「だから……お前の成績がどうであれそんなまっすぐ、こう感じるから綺麗だと思う、なんて言われたのはじめてだ」
素の貴公子も、そんな綺麗な笑い方もするんだって、つい見惚れてしまうくらい。